尾張の国出身の天台宗の僧侶『天沢』が甲斐の国を訪れた際、当地の領主『武田信玄』に『織田信長』の人となりを訪ねられた。
そこで天沢は自分が見聞きした信長の暮らしぶり等を話して聞かせたました。
信長は武芸の鍛錬に励んでいる事、剣の師は誰々で鉄砲の師は誰々、毎日水練の鍛錬と馬を責めてすごしている事等々。
そして、『幸若舞の敦盛』を愛し、舞い唄っている事を教えました。
しかし信長は『敦盛』の唄を全てを唄う訳では無く、ある一つの部分を繰り返し繰り返し唄っていると語りました。
それがあの有名な
『人間五十年、
下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり
一度生を享け、滅せぬもののあるべきか』である。
さて、この唄の意味を御存知だろうか?
まぁ読めば大意は理解できる事でしょう。
しかし、『下天』の意味は理解していない方が多いんですね。
ドラマ等でも間違った解釈をしているのを目にした記憶があります。
『下天』(敦盛には化天とあるそうだ)とは、『天下』の事ではありません。
『下天』も『化天』も仏教の六欲天の一つであるが意味が異なる。
じゃあ、信長版敦盛の『下天』の意味は・・・と言うと
仏教において、『下天の一昼夜は人間界の50年に相当する』とされている事から来ているんです。
要は『人間の一生なんて、下天では一昼夜にすぎない儚いものだ』って意味ですね。
信長は化天を下天と変えた、替え歌を唄っていたんですね。
天沢はこんな事を信玄に話して聞かせた訳ですが、信玄は非常にしつこく信長の噂を聞きたがったそうです。
武田信玄は当時から有名な謀略家であり戦略家ですから、隣国の大名がどの様な男か知ろうとする事に不思議はありませんが
未だ若く名の通って居なかった織田信長について此処まで興味を持っていたのは、何かただならぬ物を感じて居たからでしょう。
(美濃の斉藤道三が信長と会見したのも同じ理由だろうと思われます)
この時、天沢が信長の愛唱している唄をもう一つ信玄に話し聞かせています。
信玄はその唄の詩を語らせるだけでは満足せず、嫌がる天沢に唄わせて居るんですね(笑)
そしてこの唄の方が『敦盛』よりも信長の思想を良く表しているのは明らかです。
何故ならその唄、信長の自作なんですねぇ~。
つづく

















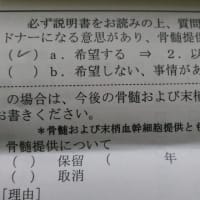
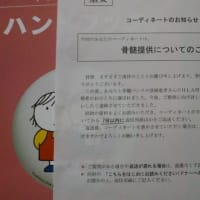
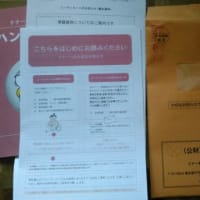
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます