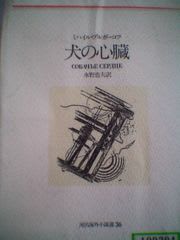レオニード・アンドレーエフ 金澤美知子訳(「バベルの図書館16」国書刊行会)
《あらすじ》
ラザロは3日間の死ののち、奇跡によって復活する。その甦りを祝って、知人たちは集まって彼に晴れ着を着せ、ごちそうと音楽を用意し、彼を祝福する。陽気だったラザロは、しかし復活のあとにはすっかり様子を変えていた。沈黙する彼のその目を覗き込んだものは、みな恐怖の、絶望のとりこになるのだった。
《この一文》
“「滅ぶ運命なのだ」と、帝は苦しい気持で考えました。「〈無限〉の暗闇の中の明るい影だ」と、恐怖の思いで考えられました。「沸々と滾り立つ血と、悲哀と大いなる歓喜を知る心臓とを盛った、脆い器だ」と、帝は優しい気持でお考えになりました。
こうして、思いをめぐらし、秤を生の側に、或いは死の側に傾けながら、帝はおもむろに息を吹き返されました。生の苦痛と歓喜の中に果てしない空虚と恐怖の暗闇からの庇護を見出そうとして。 ”
ラーゲルクヴィストの『バラバ』に、奇跡によって死から甦った男が登場するのですが、この『ラザロ』も3日間の死から息を吹き返した男です。関係があるのだろうかと思い、読んでみました。相変わらずそのあたりの知識がまったくない私。結局読み終えてみても、関係があるのかどうかは分かりませんでした(とっとと調べたらいいだけの話なのですが)。しかし、この物語は面白かった。
3日間死んでいて、そして甦った男 ラザロ。彼の復活は最初は祝福を、そして最後には恐怖と絶望を人々にもたらします。ラザロの噂を聞き付けて彼のもとを訪れる者たちは、ラザロによって大きな影響を受けることになります。この世界の美を追求し創造しようとする芸術家、愛と快楽によって幸福のうちに結びついた恋人たち、醒めることを知らぬかのように甘美な酒を味わい尽くそうとする酔っ払い、もはや恐れるものも知らぬものもないという賢者。彼等はいずれも自分たちが持っているものを誇らしげにラザロに示しますが、彼の目を覗き込んだ途端に全ては一変してしまいます。無意味と絶望とに一息にのまれてしまうのでした。
ラザロとは何者でしょうか。「死」ではないかとはじめは思いました。ですが、彼は「死よりも恐ろしい」らしい。生と死をつなぐもの。向こう側を覗いて、そして帰ってきた者。彼という存在によってあらわされているのは、いったい何でしょうか。
虚無、だろうか。生も死も、意味も無意味も超えているもの。それというのは、あるいは真理、と言うべきだろうか。それにつながるものでしょうか。だとしたらどうしてこんなに恐ろしいのだろう。全てを統べるもののその端を見たとしたら、やはり恐ろしいものなのだろうか。そうかもしれない。だけど、それはどうしてだろう。だって、私という存在もそこへ繋がっているのだろうし、その一部であると言えるのではないか。それなのに恐ろしいというのは、いったいどういうことだろう。何が、そんなに恐ろしいのだろう。何が。
上に引用したのは、ラザロを召し出したローマ皇帝の言葉です。ここに何かヒントがあるような気がします。でも、私にははっきりと何か分かるとか言えるようなことは、まだありません。この先もあるような気がしません。ずっと気になるのだろうという予感がするだけです。
こんなふうに、ちっともまとまりません。優しい語り口のほんの短い物語だったのですが、なかなかに私を離してくれそうにないのでした。
《あらすじ》
ラザロは3日間の死ののち、奇跡によって復活する。その甦りを祝って、知人たちは集まって彼に晴れ着を着せ、ごちそうと音楽を用意し、彼を祝福する。陽気だったラザロは、しかし復活のあとにはすっかり様子を変えていた。沈黙する彼のその目を覗き込んだものは、みな恐怖の、絶望のとりこになるのだった。
《この一文》
“「滅ぶ運命なのだ」と、帝は苦しい気持で考えました。「〈無限〉の暗闇の中の明るい影だ」と、恐怖の思いで考えられました。「沸々と滾り立つ血と、悲哀と大いなる歓喜を知る心臓とを盛った、脆い器だ」と、帝は優しい気持でお考えになりました。
こうして、思いをめぐらし、秤を生の側に、或いは死の側に傾けながら、帝はおもむろに息を吹き返されました。生の苦痛と歓喜の中に果てしない空虚と恐怖の暗闇からの庇護を見出そうとして。 ”
ラーゲルクヴィストの『バラバ』に、奇跡によって死から甦った男が登場するのですが、この『ラザロ』も3日間の死から息を吹き返した男です。関係があるのだろうかと思い、読んでみました。相変わらずそのあたりの知識がまったくない私。結局読み終えてみても、関係があるのかどうかは分かりませんでした(とっとと調べたらいいだけの話なのですが)。しかし、この物語は面白かった。
3日間死んでいて、そして甦った男 ラザロ。彼の復活は最初は祝福を、そして最後には恐怖と絶望を人々にもたらします。ラザロの噂を聞き付けて彼のもとを訪れる者たちは、ラザロによって大きな影響を受けることになります。この世界の美を追求し創造しようとする芸術家、愛と快楽によって幸福のうちに結びついた恋人たち、醒めることを知らぬかのように甘美な酒を味わい尽くそうとする酔っ払い、もはや恐れるものも知らぬものもないという賢者。彼等はいずれも自分たちが持っているものを誇らしげにラザロに示しますが、彼の目を覗き込んだ途端に全ては一変してしまいます。無意味と絶望とに一息にのまれてしまうのでした。
ラザロとは何者でしょうか。「死」ではないかとはじめは思いました。ですが、彼は「死よりも恐ろしい」らしい。生と死をつなぐもの。向こう側を覗いて、そして帰ってきた者。彼という存在によってあらわされているのは、いったい何でしょうか。
虚無、だろうか。生も死も、意味も無意味も超えているもの。それというのは、あるいは真理、と言うべきだろうか。それにつながるものでしょうか。だとしたらどうしてこんなに恐ろしいのだろう。全てを統べるもののその端を見たとしたら、やはり恐ろしいものなのだろうか。そうかもしれない。だけど、それはどうしてだろう。だって、私という存在もそこへ繋がっているのだろうし、その一部であると言えるのではないか。それなのに恐ろしいというのは、いったいどういうことだろう。何が、そんなに恐ろしいのだろう。何が。
上に引用したのは、ラザロを召し出したローマ皇帝の言葉です。ここに何かヒントがあるような気がします。でも、私にははっきりと何か分かるとか言えるようなことは、まだありません。この先もあるような気がしません。ずっと気になるのだろうという予感がするだけです。
こんなふうに、ちっともまとまりません。優しい語り口のほんの短い物語だったのですが、なかなかに私を離してくれそうにないのでした。