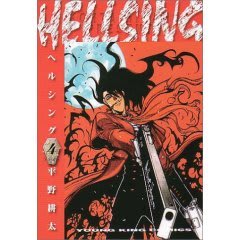(岩波文庫)
《内容》
作家アナトール・フランス(1844-1924)は思想的には懐疑主義の流れを継ぐ自由思想家といわれる。本書はその随想集。宇宙全体がはしばみの実くらいに縮んだとしても、人類はそれに気づくことはないだろうという「星」をはじめ、さまざまな題材を用いて洒脱にその人生観を述べている。芥川はこの書の影響を受けて『侏儒の言葉』を書いた。
《この一文》
“「皮肉」と「憐れみ」とはふたりのよき助言者である。前者は、ほほえみながら、人生を愛すべきものにしてくれ、後者は、泣いて、人生を聖なるものにしてくれる。わたくしがその加護を祈る「皮肉」は残酷なものではない。それは愛をも美をもあざけりはしない。それはやさしく、親切である。 ”
「やっと来た」
そう思いました。最初に読んだのは、何だったでしょう。青空文庫で読んだ「バルタザアル」だったか、岩波文庫の『少年少女』だったでしょうか。そのあと、『シルヴェストル・ボナールの罪』も買いましたが、まだ読んでいません。どこかのアンソロジーで「聖母の軽業師」を読んだ記憶があります。内容は覚えていませんが。そしてこのあいだは『ペンギンの島』を読みました。これは最高に面白かった。皮肉と諧謔と悲しみの中にも楽天を、真の楽天主義を見るようでした。それでようやく、どちらかというとお堅いイメージだったこの人の面白さに気が付いたのです。そしたら、ずっと読みたかった『エピクロスの園』が重版されたではないですか。
そういうわけで、今頃になってようやく面白い人だと分かったアナトール・フランス。この『エピクロスの園』には、私がずっと若かった頃から言いたくてもうまく言えなかったことや、理解したくてもよく理解できなかったことなどについて、まるで読みたかったそのままに書かれてありました。と思ったら、こんなふうに書かれてあります。
われわれは本を読む時には、自分の好きなように読む。本の中から自分の読みたいことだけを読む、というよりもむしろ自分の読みたいことを本の中に読む。
うーむ。まるで心を読まれているようではないか。と思ったら、こんなふうに書かれてあり…と思ったら、こんなふうに書かれてあり…と無限に繰り返してしまいそうなほど、いやもう、書かれてあることについてすごく分かってしまう。なんだか実によく分かる。それでもって、ふと胸を衝かれる。涙がこぼれそうになる。実際にすこしばかりこぼしてしまう。
というのも、読んでいると、この人はとても優しい人らしいことが伝わってくるのです。絶望や滅亡や絶叫といったものを好む暗黒趣味の私は、普段から、多くの作家がのこした社会への人類への憎悪や失望、怒りの言葉を求めたがります。不条理に満ちたこの世の中を思うならば、彼らの言い分はもっともだと思うからです。
以前同じくアナトール・フランスの『ペンギンの島』を読んだのもそういった興味からのもので、ペンギン人たちの来し方行く末を皮肉を込めて描いている物語に魅力を感じてのことでした。ところが、『ペンギンの島』を読んでみると、何と言うか、予想とは違う面白さだった。ユーモラスであるとか、それにもかかわらず悲しい物語であるとかいうだけではないのです。それだけではない何かがある。それが何なのか、その時にははっきりと分からなかったのですが(ただ、悲しみの中にも希望を見せてくれるような奇妙な楽観的さは感じたけれども)、『エピクロスの園』が教えてくれました。それは、優しさ。ありあまる優しさ。本当に、なんて優しい人なのだろう。
染み込むように、柔らかいもので撫でられるように、この人の言葉が私の中に入ってきます。別のところではあるいは厳しいことも言っているのかもしれません。実は私はまだ全部を読み終えていません。好きなところだけ、好きな順番で読んだので、たぶん半分くらいは未読です。これから時間をかけてじっくり読むつもりです。そういうことを許してくれる本だと思います。いつでも手に届くところに置いておこうと思います。厳しかったり悲しかったりする以上に優しいということが、私にはすっかり分かってしまった気持ちでいるのです。
ところで、訳者の大塚先生によるあとがきに、アナトール・フランスを熱愛した芥川についても言及されていて、それがとても面白かったです。芥川は、アナトール・フランスやメリメのように本格的な歴史小説を書きたかった(「現代人の視点からではなく、同時代人の眼をもって、この歴史の一齣を描き出し」たかった)らしい。でも出来なかった。
いえ、私が面白かったというのは、芥川が憧れたけど果たせなかったというエピソードではなく(もちろん興味深い問題ですが)、アナトール・フランスが本格的な歴史小説を描いていたという部分です。『ペンギンの島』を読んだ時、私はこんなふうに書きました。
読み終えて凄かったと思うのは、語られる時代ごとにその時代の雰囲気がぴったりと表現されていることでしょうか。それゆえに、章ごとにバラバラに読んだとしても、それぞれがひとつの物語としても十分に魅力的です。それでいて、もちろんそれぞれの物語は一続きにきちんと繋がってもいるのです。そんなのは当たり前のことかもしれませんが、凄い。圧倒的です。
うーむ、表現力のなさは諦めるとしても、我ながらこの読みの確かさには驚かされます。「その時代の雰囲気がぴったりと表現されている」。そうそう、そう思ったんでした。それはあれが「本格的な歴史小説」だったからなのか。
それにしても、私の洞察力の鋭さよりももっと驚かされることには、この本の中では、あとがきに至ってまで「読みたいことだけを読」めるということですね。ははは。
…なんてことはさておき、こんなふうに私をなだめてくれる本は、ほんとうに久しぶりのことだったなあ。