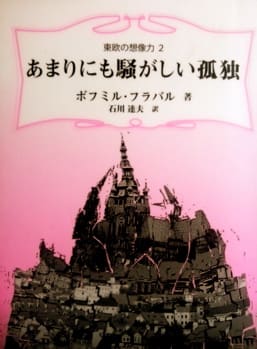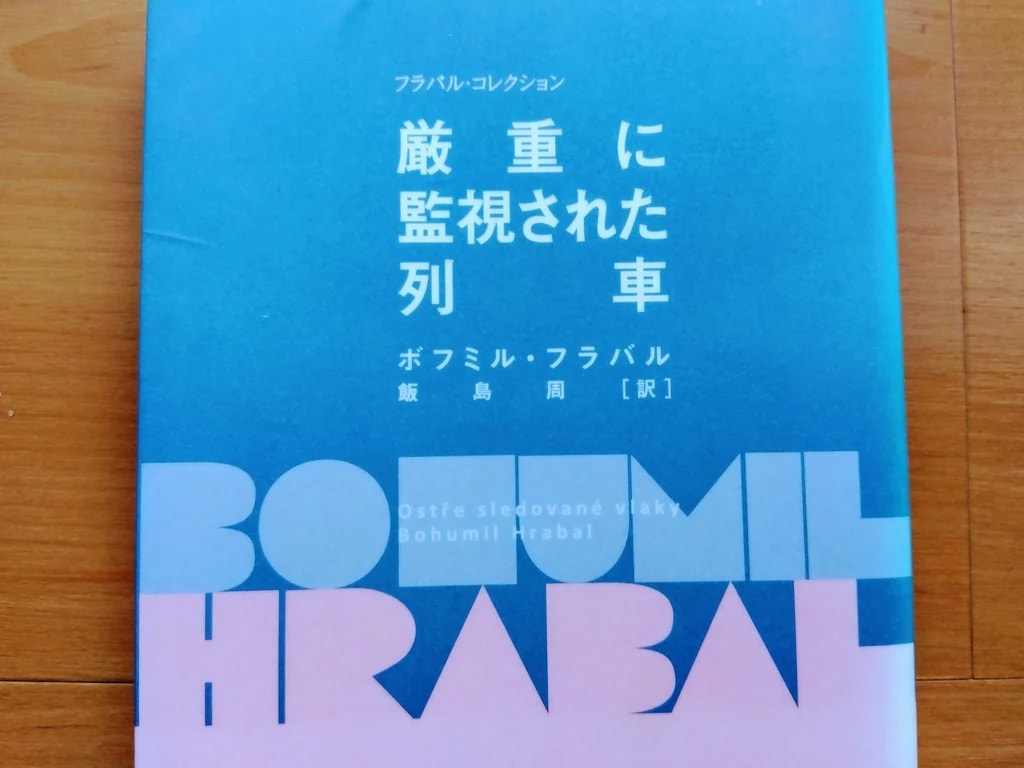
ボフミル・フラバル 飯島周訳(松籟社)
《あらすじ》
20世紀チェコの作家ボフミル・フラバルによる中編小説の日本語版。
舞台は1945年、ナチスの保護領下におかれたチェコ。若き鉄道員ミロシュは、ある失敗を苦にして自殺を図るが未遂に終わり、命をとりとめた後もなお、そのことに悩み続けている……
舞台は1945年、ナチスの保護領下におかれたチェコ。若き鉄道員ミロシュは、ある失敗を苦にして自殺を図るが未遂に終わり、命をとりとめた後もなお、そのことに悩み続けている……
《この一文》
“この二人はそんなことができっこない、二人ともこんなにかっこいいんだから。ぼくはいつも美しい人たちが怖くて、そんな人たちとまともに話すことができなかった、冷や汗が出て言葉がつっかえた、美しい顔をそれほどあがめており、目がくらむほどだったので、美しい人の顔をのぞき込むことができなかった。”
青年期を、いや青年期に限らず人生のある程度の時期を、自分にはどうしようもできないような社会の混乱の中で生きるというのはどういうものだろうか。社会がどんなに混乱していても、そこにはいつも人間の生活があるわけで。それぞれの人間の思いがあるわけで。
戦争の時代に占領された国で生きるというのはどういうものだろう。そこにある青春は。愛とか悲しみとかは。
というよりも、青春とか愛とか悲しみとかいった人間の生活の時々に、戦争が起こっていたりそうでなかったりするということか。生きる時代を自分では選べない人類の歴史は悲しいな。
語り口が鮮やかであることで、さほど長くもないこの作品でしたが、最後まで読みとおすのはなかなか苦しかったです。