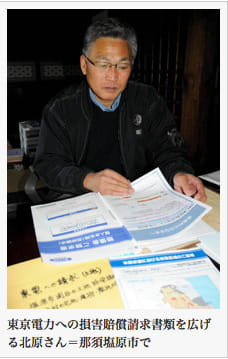117事件証拠301点紛失=総点検、書類うそ記載も―大阪府警より転載
時事通信 12月14日(金)0時10分配信
証拠品紛失に伴うすり替えなどの不祥事続出を受け、大阪府警が証拠品を総点検した結果、117事件の301点を紛失していたことが13日、分かった。府警が公表した。鑑定済みもあり、「捜査に大きな支障はない」としているが、書類にうそを記載するなどの不正も判明し、退職者を除く2人を懲戒処分とした。
刑事総務課によると、紛失したのは、1995年以降に起きた殺人や窃盗事件などの証拠品で、未解決が大半。府警が今年4月から、全83部署を対象に約1万6000事件の記録と証拠品を照合して調査し、35部署で紛失が判明した。強盗殺人の被害者が縛られた粘着テープなどが含まれ、半年ごとの点検が形骸化していたという。
凶悪事件の時効が撤廃される一方、客観証拠が重視される中、府警は4月に証拠品管理センターを新設し、長期保存の約3万7000点を警察署から移管。7署で担当者を置いて専用の赤色段ボール箱での保管を試験実施し、来年にはバーコード管理も導入する。
時事通信 12月14日(金)0時10分配信
証拠品紛失に伴うすり替えなどの不祥事続出を受け、大阪府警が証拠品を総点検した結果、117事件の301点を紛失していたことが13日、分かった。府警が公表した。鑑定済みもあり、「捜査に大きな支障はない」としているが、書類にうそを記載するなどの不正も判明し、退職者を除く2人を懲戒処分とした。
刑事総務課によると、紛失したのは、1995年以降に起きた殺人や窃盗事件などの証拠品で、未解決が大半。府警が今年4月から、全83部署を対象に約1万6000事件の記録と証拠品を照合して調査し、35部署で紛失が判明した。強盗殺人の被害者が縛られた粘着テープなどが含まれ、半年ごとの点検が形骸化していたという。
凶悪事件の時効が撤廃される一方、客観証拠が重視される中、府警は4月に証拠品管理センターを新設し、長期保存の約3万7000点を警察署から移管。7署で担当者を置いて専用の赤色段ボール箱での保管を試験実施し、来年にはバーコード管理も導入する。