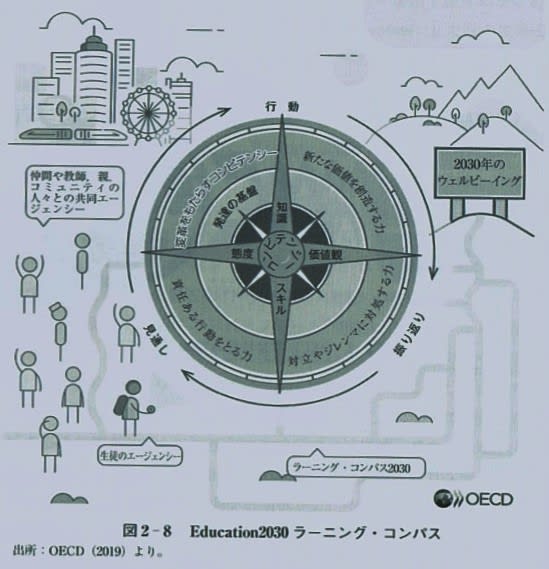のんびり八ケ岳 行者小屋テン場に下山 小さな我が家を設営 上は横岳と硫黄岳へ続く稜線
古典といってもいい寺田寅彦『柿の種』岩波書店
自然科学者の寺田は漱石の弟子という言い方もされ、名文家でもある。
この本は折々にかかれた随想をまとめたものである。
扉に
棄てた一粒の柿の種
生えるも生えぬも
甘いも渋いも
畑の土のよしあし
とある。短文が長文のように語りはじめるかは私たちにかっているのだろう。
引用、ほぼ無作為。
日常生活の世界と詩歌の世界の境界は、ただ一枚のガラス板で仕切られている。
このガラスは、初めから曇っていることもある。
生活の世界のちりによごれて曇っていることもある。
二つの世界の間の通路としては、通例、ただ小さな狭い穴が一つ明いているだけである。
しかし、始終ふたつの世界に出入していると、この穴はだんだん大きくなる。
しかしまた、この穴は、しばらく出入しないでいると、自然にだんだん狭くなって来る。
ある人は、初めからこの穴の存在を知らないか、また知っていても別にそれを捜そうともしない。
それは、ガラスが曇っていて、反対の側が見えないためか、あるいは・・・・・・あまりに忙しいために。
穴を見つけても通れない人もある。
それは、あまりからだが肥り過ぎているために……。
しかし、そんな人でも、病気をしたり、貧乏したりしてやせたために、通り抜けられるようになることはある。
まれに、きわめてまれに、天の焔を取って来てこの境界のガラス板をすっかり熔かしてしまう人がある。
(大正九年五月)
脚を切断してしまった人が、時々、なくなっている足の先のかゆみや痛みを感じることがあるそうである。
総入れ歯をした人が、どうかすると、その歯がずきずうずくように感じることもあるそうである。
こういう話を聞きながら、私はふと、出家遁世の人の心を想いみた。
生命のある限り、世を捨てるということは、とてもできそうに思われない。
(大正九年十一月)
平和会議の結果として、ドイツでは、発動機を使った飛行機の使用製作を制限された。
すると、ドイツ人はすぐに、発動機なしで、もちろん水素なども使わず、ただ風の弛張と上昇気流を利用するだけで上空を翔けり歩く研究を始めた。
最近のレコードとしては約二十分も、らくらくと空中を翔けり回った男がある。
飛んだ距離は二里近くであった。
詩人をいじめると詩が生まれるように、科学者をいじめると、いろいろな発明や発見が生まれるのである。
(大正十一年八月)
無地の鶯茶色のネクタイを捜して歩いたがなかなか見つからない。
東京という所も存外不便な所である。
このごろ石油ランプを探し歩いている。
神田や銀座はもちろん、板橋界隈も探したが、座敷用のランプは見つからない。
東京という所は存外不便な所である。
東京市民がみんな石油ランプを要求するような時期が、いつかはまためぐって来そうに思われてしかたがない。
(大正十二年七月)
(追記)大正十二年七月一日発行の「渋柿」にこれが掲載されてから、ちょうど二か月後に関東大震災が起こって、東京じゅうの電燈が役に立たなくなった。これも不思議な回りあわせであった。
「二階の欄干で、雪の降るのを見ていると、自分のからだが、二階といっしょに、だんだん空中へ上がって行くような気がする」と、今年十二になる女の子がいう。
こういう子供の頭の中には、きっとおとなの知らない詩の世界があるだろうと思った。
しかしまた、こういう種類の子供には、どこか病弱なところがあるのではないかという気がする。
(大正十三年八月)
ある日電車の中で、有機化学の本を読んでいると、突然「琉球泡盛酒」という文字が頭の中に現われたが、読んでいる本のページをいくら探してもそんな文字は見つからなかった。よく考えてみると、たぶん途中で電車の窓から外をながめたときにどこかの店先の看板にでもそういう文字が眼についた、それを不思議な錯覚で書物の中へ「投げ込んだ」ものらしい。ちょうどその時に読んでいた所がいろいろなアルコールの種類を記述したページであったためにそういう心像の位置転換が容易にできたものと思われる。
人間の頭脳のたよりなさはこの一例からでもおおよそ想像がつく。何時幾日にどこでこういう事に出会ったとか、何という書物の中にどういう事があったとか、そういう直接体験の正直な証言の中に、現在の例と同じような過程で途方もないところから紛れ込んだ異物が少しもはいっていないという断定は、神様でないかぎりだれにもできそうにない。
(昭和十年十月十四日)
蝶や鳥の雄が非常に美しい色彩をしているのは雌の視覚を喜ばせてその注意をひくためだというような説は事実に合わないものだということがいろいろの方面から説明されているようである。自分の素人考えではこの現象はあるいはむしろ次のように解釈さるべきものではないかと思う。
周囲の環境と著しく違った色彩はその動物の敵となる動物の注意をひきやすく従ってそうした敵の襲撃を受けやすいわけである。そういう攻撃を受けた場合にその危険を免れるためには感覚と運動の異常な鋭敏さを必要とするであろう。それで最も目立つ血彩をしていながら無事に敵の襲撃を免れて生き遺ることのできるような優秀な個体のみが自然淘汰の師にかけられて選り残され、そうしてその特徴をだんだんに発達させて来たものではないか。
戦争好きで、戦争に強い民族なぞの発生にいくらかこれに似た選択過程が関係しているのではないかという気がする。
(昭和十年十月十六日)
秋晴れの午後二階の病床で読書していたら、突然北側の中敷窓から何かが飛び込んで来て、何かにおつかってばたりと落ちる音がした。郵便物でも外から投げ込んだような音であったが、二階の窓に下から郵便をほうり込む人もないわけだから小鳥でも飛び込んだかしらと思ったが、からだの痛みで起き上がるのが困難だから確かめもせずにやがて忘れてしまっていた。しばらくしてから娘が二階へ上がって来て「オヤ、これどうしたの」と言いながら縁側から拾い上げて持って来たのを見ると一羽の麓の死骸である。かわいい小さなからだを簡形に強直させて死んでいる。
北窓から飛び込んで南側の庭へ抜けるつもりでガラス障子にくちばしを突き当てて脳震濫を起こして即死したのである。「まだ暖かいわ」と言いながら愛していたがどうにもならなかった。
鳥の先祖の時代にはガラスというものはこの世界になかった。ガラス戸というものができてから今日までの年月は鳥に「ガラス教育」を施すにはあまりに短かった。
人間の行路にもやはりこの「ガラス戸」のようなものがある。失敗する人はみんな眼の前の「ガラス」を見そこなって鼻柱を折る人である。
三原山火口へ投身する人の大部分がそうである。またナポレオンもウィルヘルム第二世もそうであった。
この「ガラス」の見えない人たちの独裁下に踊る国家はあぶなくて見ていられない。