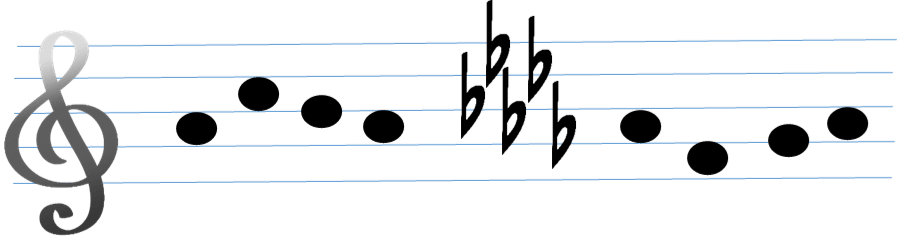1770年12月16日は、ベートーヴェンの誕生日とされている日。
12月17日に洗礼を受けたという記録が、ボンの教区教会に残された洗礼登録簿にあるため、誕生日は16日だったと推定されるのです。
今年はベートーヴェンの生誕250年となる記念の年でしたが、コロナの影響で、ベートーヴェンの曲のコンサートが軒並み中止になったようです。
私自身は、ベートーヴェンの曲はあまり得意ではないのですが、今年は7月のミニリサイタルで悲愴ソナタを弾き、9月のプロムナード・コンサートでエリーゼのためにを弾き、19日の第55回プロムナード・コンサートでは、31番のピアノ・ソナタを弾きます。
ベートーヴェンは、生涯にわたって32曲のピアノ・ソナタを作り、このソナタの作風の変化が、ベートーヴェンの作風の変化を如実に表していると言えるでしょう。
ベートーヴェンは18ン7年に亡くなっていて、ピアノ・ソナタの最後の2曲は、1822年に完成されているので、最後の5年間はピアノ・ソナタは作っていないことになります。
31番のソナタを作り始めたのは1821年で、この年の前半は体調がすぐれず、創作活動も滞っていたようですが、後半になり、体調が回復するにつれて、30番、31番、32番のソナタに取り掛かり、ミサ・ソレムニスやディアベリ変奏曲といった大曲に取り組み始めました。
31番と32番のソナタは1822年初めに完成されました。
ベートーヴェンは、ピアノ・ソナタを生涯かけて、深い内容と高度な技巧を持った芸術的な様式に高め、古典派のソナタ形式の可能性を追求し、後世に多大な影響を与えました。
という難しい話はさておいて、31番のソナタは、32曲のソナタの中でも最も好きな曲…かも知れません。21番のワルトシュタインも好きですが…。
3楽章から成り、1楽章の第1主題は非常に抒情的で美しいメロディで、1楽章全体が1篇の抒情詩と言える作品です。
ベートーヴェン自身も非常に愛着を持っていたと言われるメロディで、3楽章のフーガにも、一聴しただけでは気づかないのですが、使われています。
一般的なベートヴェン像とは全く違うので、これがベートーヴェンの曲なのか…と、思ってしまうかもしれません。
2楽章は、リズミックでスケルツォ的な性格を持った短い曲です。
スケルツォはちょっと気まぐれな要素も持ったリズミックな曲のことですので、そんな感じですね。
最初に弾いたときは、なんだなんだこの曲は!!…と思いましたから。
主要なメロディは、2編の民謡から引用されています。
以前CMにも使われて、ちょっとびっくりしました。
「明治エッセルスーパーカップSweet's」 のCMでした。
3楽章は、大きな序奏の後、嘆きの歌とフーガが交互に出てくる壮大な曲です。
最初の嘆きの歌は、果てしない悲しみの歌であり、続く後フーガは、第1楽章の甘いメロディを使って歌われます。
その後再び嘆きの歌が、疲れ果て嘆きつつ再び歌われ、再びフーガへ。
この時はフーガの主題は展開されていて、次第に元気を取り戻しながら歌われ、最後に向かって悲嘆の色を一掃するような素晴らしい高揚感のうちに曲が締めくくられます。
3楽章構成ですが、1つの曲として続けて演奏されます。
最後の楽章にフーガを持ってくるのは、ベートーヴェンだから…なのかもしれません。
ただ、バッハのフーガとは違い、非常に自由な形式になっています。
いわゆる自由フーガ…。
なので、暗譜は実に大変です。
とりあえず暗譜で弾く予定にはしていますが…。