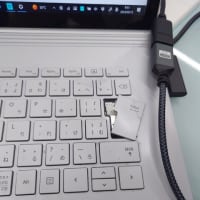おはようございます!
心地よい風が吹く@札幌です。
さて、昨夜はこんな感じで少々反省すべき食生活だったので…

僅かばかりですが罪滅ぼし的に走ってきました。
良い季節になったらやってみようと思っていた豊平川沿いの遊歩道ジョグ。
途中、幌平橋の橋の上に更に上に登れる階段があることを知り、

(こういう感じ。この写真だけgoogleマップから拝借)
煙同様高い所に登りたがる私としては登らずにはおられず、


てっぺんからパシャリ。
とまあ、枕が少々長い今日のエントリですが、
特許法等の改正案が国会通過した、というニュースが流れたのが先週の話。
前々から意匠法については幾度か言及してきていたので、今回は特許法の改正ポイントについてちょっとだけ。
経産省のリリースによると、改正の概要は以下のとおり。
(1)特許法の一部改正
① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、
被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、
裁判所に報告書を提出する制度を創設する。
② 損害賠償額算定方法の見直し
(ⅰ)侵害者が得た利益のうち、
特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
(ⅱ)ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、
特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。
条文としては、以下のようになっている(ポイントのみ)。
①について:
(査証人に対する査証の命令)
第105条の2
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
…査証≒立ち入り検査が認められるようになった、というと結構斬新に聞こえるわけですが、さて実際にはそれが認められるためのハードルはなかなかに高い。
「申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるとき」というのが具体的にどのような場面なのかなど、改正法の解説が待たれるところ。
②について:
(損害の額の推定等)
第102条
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害したものが譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額。
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
…多分馴染みのない方は途中で“目が滑る”と思うのだけど、ざっくり言うと改正前の102条1項の紛らわしかった部分=控除されるべき数量についての「受けるべき金銭」を認めた、ということ。
・・・わかりにくい、かな?
もともと規定されていたのは、
・侵害した人が売った個数 × 権利者が、“侵害が無ければ得られていた1個あたりの利益額” が基本で、
・ただしそうはいっても、例えば権利者側にそこまでの生産能力が無いなど「侵害した人が売った個数」を売る能力が無い、といった場合にはその数量に応じた額はマイナスする、というもの。
問題だったのは、
“いや、その「マイナス」した部分だって、本当は勝手に実施してよかったわけじゃないんだから、その部分はロイヤリティ相当額支払うべきでは?”
というところ。この解釈がまちまちだったので、今回きっちり規定しましたよ、というもの。
正確に表現すると上記のような条文にしかできないんだろうけど、ま、初見ではわかりづらいですよね(笑)
なおこの②の改正は、四法(特実意商)共通で適用されるとのことなのでその点も注意が必要。
心地よい風が吹く@札幌です。
さて、昨夜はこんな感じで少々反省すべき食生活だったので…

僅かばかりですが罪滅ぼし的に走ってきました。
良い季節になったらやってみようと思っていた豊平川沿いの遊歩道ジョグ。
途中、幌平橋の橋の上に更に上に登れる階段があることを知り、

(こういう感じ。この写真だけgoogleマップから拝借)
煙同様高い所に登りたがる私としては登らずにはおられず、


てっぺんからパシャリ。
とまあ、枕が少々長い今日のエントリですが、
特許法等の改正案が国会通過した、というニュースが流れたのが先週の話。
前々から意匠法については幾度か言及してきていたので、今回は特許法の改正ポイントについてちょっとだけ。
経産省のリリースによると、改正の概要は以下のとおり。
(1)特許法の一部改正
① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、
被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、
裁判所に報告書を提出する制度を創設する。
② 損害賠償額算定方法の見直し
(ⅰ)侵害者が得た利益のうち、
特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
(ⅱ)ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、
特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。
条文としては、以下のようになっている(ポイントのみ)。
①について:
(査証人に対する査証の命令)
第105条の2
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
…査証≒立ち入り検査が認められるようになった、というと結構斬新に聞こえるわけですが、さて実際にはそれが認められるためのハードルはなかなかに高い。
「申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるとき」というのが具体的にどのような場面なのかなど、改正法の解説が待たれるところ。
②について:
(損害の額の推定等)
第102条
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害したものが譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額。
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
…多分馴染みのない方は途中で“目が滑る”と思うのだけど、ざっくり言うと改正前の102条1項の紛らわしかった部分=控除されるべき数量についての「受けるべき金銭」を認めた、ということ。
・・・わかりにくい、かな?
もともと規定されていたのは、
・侵害した人が売った個数 × 権利者が、“侵害が無ければ得られていた1個あたりの利益額” が基本で、
・ただしそうはいっても、例えば権利者側にそこまでの生産能力が無いなど「侵害した人が売った個数」を売る能力が無い、といった場合にはその数量に応じた額はマイナスする、というもの。
問題だったのは、
“いや、その「マイナス」した部分だって、本当は勝手に実施してよかったわけじゃないんだから、その部分はロイヤリティ相当額支払うべきでは?”
というところ。この解釈がまちまちだったので、今回きっちり規定しましたよ、というもの。
正確に表現すると上記のような条文にしかできないんだろうけど、ま、初見ではわかりづらいですよね(笑)
なおこの②の改正は、四法(特実意商)共通で適用されるとのことなのでその点も注意が必要。