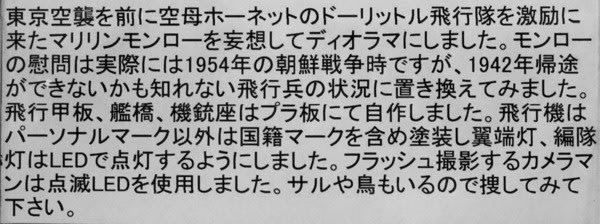7月31日(水)、「日比谷公園」に「アオノリュウゼツラン」(青の竜舌蘭)を見に行って来ました。29日と30日は危険な暑さだったので、31日に行きました。公園内は樹木が多かったので、あまり暑くありませんでした。今年は日本のあちこちで咲いているみたいでしたが、横浜市は遠いので行き易い「日比谷公園」にしました。地下鉄の「日比谷駅」A10出口の「有楽門」から入って直ぐでした。「第一花壇」の「ペリカン噴水」の横に咲いていました。
「東京都公園協会」によると、植えられた時期の詳細な記録は残っていませんが、過去の写真をさかのぼると、1960年前後に現在とほぼ同様の場所に植えられた株のようです。それが正しければ、 植えられてから約60年経過した事になります。余談ですが、2019年7月19日に同じ花壇の別の株が咲き、話題を集めたそうです。その時の子株が親株のあった場所にあります。
和名の「竜舌」は、葉が長くて厚く、先が尖っていて縁にトゲがあることから、「龍」の舌に見立てて名付けたもの。「蘭」はその花の美しさに対して付けられたもので、ラン科ではありません。葉に「斑」が入ったものが先に輸入された為、基本種である「斑」なし品種があえて「アオノリュウゼツラン」(青の竜舌蘭)という呼び名になっているそうです。別名の「アガベ」は、学名の「Agave americana」からきています。
数10年に1度、茎が急成長をして花が下の方から咲き始めます。花が咲き終わった後は枯死してしまいます。でも枯死する寸前に子株を根元の所に作っておき、しっかりと子孫を残すとの事。とても不思議な植物です。 来年も日本の何処かで咲くでしょうが、手近な所で咲くのは何時になるか分からないので、思い切って行って来ました。花は少し枯れかけていましたが、支えも無く凛々しく立っている姿に感動しました。「日比谷公園サービスセンター」の「開花までの成長記録」によると、5月19日に430cmだったものが、7月10日の開花時には高さが770cmになっていました。
ついでに「大噴水」と「鶴の噴水」も見て来ました。足を延ばして「二重橋」や「ミッドタウン日比谷」、或いは「銀ぶら」(死語?)でもしようかと思いました。しかし、暑いし俄か雨や雷雨が心配だったので、早めに帰る事にしました。後でニュースで知ったのですが、板橋区や練馬区、埼玉県南部の戸田市などではゲリラ雷雨で冠水した所もあったみたいです。
「ペリカン噴水」の後ろは「旧日比谷公園事務所 」 一番上の花も少し枯れかかっていました-

茎へ養分の転流が起こった葉 開花までの成長記録 -7月10日に開花(770cm)-

「第一花壇」の方を向いてみました 左を向くと後ろに「ミッドタウン日比谷」が見えました

大噴水 -午前8時から午後9時まで稼動 28分周期(24景)-

「雲形池」の「鶴の噴水」 -前・横・後からみた姿-