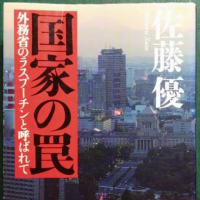佐藤優氏を知るために、初期の著作を読んでみました。
まずは、この本です。
佐藤優『国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて』

ロシア外交、北方領土をめぐるスキャンダルとして政官界を震撼させた「鈴木宗男事件」。その“断罪”の背後では、国家の大規模な路線転換が絶対矛盾を抱えながら進んでいた―。外務省きっての情報のプロとして対ロ交渉の最前線を支えていた著者が、逮捕後の検察との息詰まる応酬を再現して「国策捜査」の真相を明かす。執筆活動を続けることの新たな決意を記す文庫版あとがきを加え刊行。
国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて
□序 章 「わが家」にて
□第1章 逮捕前夜
□第2章 田中眞紀子と鈴木宗男の闘い
□第3章 作られた疑惑
□「背任」と「偽計業務妨害」
□ゴロデツキー教授との出会い
□チェルノムィルジン首相更迭情報
□プリマコフ首相の内在的ロジックとは?
■ゴロデツキー教授夫妻の訪日
□チェチェン情勢
□「エリツィン引退」騒動で明けた2000年
□小渕総理からの質問
□クレムリン、総理特使の涙
□テルアビブ国際会議
□ディーゼル事業の特殊性とは
□困窮を極めていた北方四島の生活
□篠田ロシア課長の奮闘
□サハリン州高官が漏らした本音
□複雑な連立方程式
□国後島へ
□第三の男、サスコベッツ第一副首相
□エリツィン「サウナ政治」の実態
□情報専門家としての飯野氏の実力
□川奈会談で動き始めた日露関係
□「地理重視型」と「政商型」
□飯野氏への情報提供の実態
□国後島情勢の不穏な動き
□第4章 「国策捜査」開始
□第5章 「時代のけじめ」としての「国策捜査」
□第6章 獄中から保釈、そして裁判闘争へ
□あとがき
□文庫版あとがき――国内亡命者として
※文中に登場する人物の肩書きは、特に説明のないかぎり当時のものです。
ゴロデツキー教授夫妻の訪日
1999年11月22日、午後11時頃、外務省の執務机の電話が鳴った。袴田茂樹青山学院大学教授からだった。
「佐藤さん、私たちはいま、宮崎にいます。教育テレビを見ました。ゴロデツキーさんに佐藤さんの発言を訳して説明していました」
その日、NHK教育テレビで私をメインゲストとするETV特集「混迷するロシア」が放映されたのだった。袴田氏たちは宮崎で行われた総務庁主催の北方領土問題に関する泊まりがけのシンポジウムに参加していた。
この国際シンポジウムは名目上は総務庁の主催になっているが、実際の運営は末次一郎氏が主宰する安全保障問題研究会が取り仕切っていた。その末次氏に招待されたゴロデツキー教授は再来日し、このシンポジウムに参加していた。
末次一郎氏は、旧日本軍の諜報員養成機関として知られる陸軍中野学校を卒業した元情報将校で、戦後は巣鴨プリズンに収容された戦犯の支援、青年運動団体の創設、沖縄返還運動などで活躍した社会活動家でもある。与野党政治家に広範な人脈をもち、歴代首相の相談相手も務めていた。日本人だけではなく、末次氏の高潔な人柄と、原理原則では絶対に譲らないが、利害が対立する相手とでも誠実に対話をするという姿勢に惹きつけられるロシア人も多かった。
末次氏は北方領土返還をライフワークとして活躍していたので、外務省「ロシアスクール」とは緊密に連絡を取る関係となっていた。
袴田教授は末次氏が主宰する研究会の主要メンバーのひとりだった。このときの電話で袴田氏から「ゴロデツキーさんが来年、2000年を記念してロシアの地政学的位置に関する国際学会を開くので、それに日本の学者も参加して欲しいと言っている。外務省としてもサポートしてほしい」と相談された。ゴロデツキー氏も電話口に出て、国際学会の腹案について若干説明した上で、「この問題について、あなたと東郷さんと話をしたい」と提案してきたので、私は「とてもよい話と思います。是非、話し合いましょう」と答えた。
私が学会のことをはじめて知ったのは、この袴田氏の電話によってだった。すでに秋の人事異動で、東郷氏は条約局長から北方領土交渉を直接担当する欧亜局長に異動していた。ゴロデツキー教授は東郷氏や私たちと協議するために滞在を一日延長した。 その費用は、東郷局長の“指示”に基づき支援委員会から支出した。
その後、ゴロデツキー氏と東郷氏と私の三人で、昼食をはさみ意見交換をした。ゴロデツキー氏の構想は、次のような非常に興味深いものだった。
ロシアはユーラシア国家で、西に向けた顔と東に向けた顔がある。欧米のロシア専門家は、ロシアの東に向けた顔については十分な関心をもっていない。北方領土問題についても認識が不十分である。他方、日本のロシア専門家は、アメリカのロシア研究については熟知しているが、西欧、イスラエルの研究についてはほとんど関心を払っていない。
2000年という記念の年に、欧米、日本、ロシア、イスラエルの政策に影響を与える学者がテルアビブに集い、ロシアの行方と国際秩序について議論することは、それぞれの国の専門家にとって有益であり、特に日本政府にとっては北方領土問題に対する理解を各国専門家に対して求めるよい機会である。東郷氏も私もゴロデッキー教授の構想に全面的に賛成した。
袴田教授もこのテルアビブにおける国際学会の実現にとても熱心で、末次代表と下斗米伸夫法政大学教授、更にアジア太平洋地域情勢に詳しい田中明彦東京大学教授を是非学会に参加させたいと私に働きかけてきた。
その後、私は、山内昌之東京大学教授と面会し、国際学会について話をした。山内教授は、ロシアのイスラーム問題の権威で、ロシア、中央アジア、中東情勢のみならず、日本の外交全般に通暁し、外務省が深く関与する月刊誌『外交フォーラム』の編集委員だった。また、田中氏、袴田氏とともに外務省総合外交政策局長が主宰する勉強会のメンバーで、ゴロデツキー教授が言うところの「政策に影響を与える学者」であることは間違いなかった。
前述した3月の訪日時に二人は会食したのだが、その際の議論も噛み合っていた。山内教授からは「せっかくの機会であるので、日本の指導的中東専門の学者で、しかもロシアとの関係についても研究している人を連れて行きたい」という申し出があり、私は「それはとてもよいことと思います」と答えた。
私は東郷局長に袴田氏と山内氏の要望を伝えた。
東郷氏は「それは実現したらよいと思う。それから僕もこの学会には参加したい」と大いに乗り気だった。
「この機会に外務省の若手専門家たちが一流の国際学会の雰囲気に触れ、ロシアに関する深い知識を身につけ、人脈を作ることは、外務省の情報収集・分析能力強化に貢献します」と私が提案すると、東郷氏は次のように述べてそれに同意した。
「とても良い機会なので、是非若い人たちを鍛えてやって欲しい。僕がモスクワ在勤中、若い人をメモ取りに連れて行っても、日露関係ならばきちんとした記録を作ることができるけれど、内政だと全くメモがとれない。これはロシア語力の問題ではなく、サブ能力(外務省用語でサブスタンスの略。政治、経済、安全保障などに関する専門的知識)が弱くなっているからだ。あなたのチームにはこの面での能力強化を望んでいる」
私が「カネはどこから出しますか」と尋ねると、東郷局長は「支援委員会から出せばいい。倉井(高志ロシア支援室長)には僕から言っておく」と答えた。この時点では私も東郷氏も、学会派遣費用を支援委員会から手当したことで刑事責任を追及されるとは夢にも思っていなかった。
【解説】
私が「カネはどこから出しますか」と尋ねると、東郷局長は「支援委員会から出せばいい。倉井(高志ロシア支援室長)には僕から言っておく」と答えた。この時点では私も東郷氏も、学会派遣費用を支援委員会から手当したことで刑事責任を追及されるとは夢にも思っていなかった。
ここは重要です。
テルアビブにおける国際学会の重要性は、私にも分かりました。
そこに日本の学者と佐藤氏の同僚の外務省の役人が複数派遣されることの意義も理解します。
その費用はどんどん膨らんでいきます。
しかし、それが国際機関であるロシア支援委員会から安易に手当できると東郷局長が考えたところに問題があったのかもしれません。
獅子風蓮