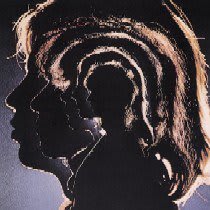巻頭言
無駄な時間 -循環し続ける思考のために-
副会長 森岡 周(畿央大学)
ある研究を創造する上での事実は、己の心(脳)に意識(自己意識)が発生することである。これは「何」かに向けての志向性であり、自らが自身で選択した心理的道具(他者、書、先行研究など)に能動的に接触することにより、時間をかけて発生する。人はコンピュータと違って、情報処理が遅いことから意識を生み出す。
人はこの世に生まれ、他者や道具から、言語を学ぶことにより、自らの心(脳)を形成し、それを基礎にあらたな創造を生む。人の脳は社会・文化的な環境の営みの中で自己組織化する。人の自己意識は、異なる複数の脳と脳の間で情報交換を通じてはじめて実存化する。
実存化する意識から、研究仮説や手法が生まれるが、果たしてこのプロセスが真の客観(すべての観察者からみて同一)であるといえるだろうか。人が行う研究である以上、自己意識からは逃れられない。であるならば、過去の科学の発見は確固たる経験主義に根ざしているといえよう。科学的な処理手続き(解析)はある程度、客観的であるかもしれないが、何かを問うという自らの視点は、個人の主観的な発想や創造に委ねられている。自らの研究において「何」を活用するのかという視点には、常に主観が付き纏う。研究においての観察とは、単に確認する(見ている)のではなく、ある視点に立つ(ある視点を生み出す)ということである。
科学的根拠に基づいた医療(EBM)が叫ばれ、はや幾年か過ぎた。そもそも「理学療法の医学的基礎研究会」の発足趣意は、理学療法に関連する事象を科学的な視点で研究することで、理学療法学としての確固たる位置づけを行うとともに、それに基づいた、その時点においての根拠ある臨床理論を提供することと認識している。この数年、臨床医学の介入研究(ランダム化比較試験:RCT)に基づいた治療介入の有効性についての報告が湯水のように増えてきたが、過去の科学的な発見は、そのほとんどがHypothesis-guided researchによるものであると私は認識している。この視点に立つと、理学療法学も今の基礎科学で証明されつつある問題を基礎あるいは臨床の場で仮説立て、それを検証し続けることが、本来の科学に立脚した根拠ある理論や治療であると思う。なぜなら、それが現在進行形だからである。人は止まってはいないし、時間的にも空間的にも同じ意識であるなんてありえるはずがない。目に見える効果や成果のみの現在完了形の臨床試験のみに盲目にならず、一方、基礎研究の反復による盲目さで、いったい「何」に向けての志向性であったか、皆目見当つかない実験にならないよう、無駄な時間と思えるかもしれないが、実験レベルでなく、思考レベルでもよいから、その両者を行ったり来たりする余裕がないといけないと昨今感じている。その余裕が新たな創造性を創発するのだと思っている。メタファーな言い方をすれば、自らの脳の連合野には、新たな情報に敏感になれるよう、少し隙間をつくっておくほうがよい。五感による情報は与えられるものでなく、自らが取りにいくものである。ヒトでなく、人間である以上、自己の意識は他者の意識、すなわち<間>から生まれる。だとすれば、己の自己意識による研究成果は、必ず他者に向けたその時代時代のメッセージでなければならない。
いずれにしても、Karl Popperの言葉を借りれば、科学的言明は反証されるべき仮説であり、できるだけすみやかに反証されるべきである。いつまでも理論なき、論点先取りなリハビリテーション思想に基づく、介入を続けるわけにはいかない。その理論を発信あるいは更新していく場所が、理学療法の医学的基礎研究会だと思っている。 思考を循環させるために、少しゆっくり歩いてみよう。そのとき、私自身の身体のすばらしさを自身の心(脳)で感じることができれば、創造性が生み出されるかもしれない。脳と身体のスペシャリストであるならば、自らの身体を感受する、そんな日常を大事にしたいものである。
自省をこめて・・・忙しいとは心を亡くすということ。
日時 平成19年2月9日(金)~11日(日)
会場 富士リハビリテーション専門学校
2/9(金)
10:30~12:00 認知運動療法~イントロダクション~ 宮本省三(高知医療学院)
13:00~15:00 脳科学と認知神経リハビリテーション 森岡 周(畿央大学)
15:10~17:10 脳卒中片麻痺に対する認知運動療法 原 修(中伊豆温泉病院)
整形外科疾患に対する認知運動療法 沖田一彦(県立広島大学)
2/10(土)
9:00~10:30 認知を生きることの意味 沖田一彦
10:40~12:00 脳の中の身体を治療するということ 森岡 周
13:00~15:00 認知運動療法における病態の捉え方Ⅰ 塚本芳久(摂南総合病院)
15:10~17:10 認知運動療法における病態の捉え方Ⅱ 内田成男(富士リハビリテーション専門学校)
2/11(日)
9:00~10:20 認知運動療法の臨床実践に向けて 宮本省三
10:30~12:00 実習:認知を評価する 原 修
13:00~14:20 実習:認知課題の設定 寺林大史(慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター)
14:30~15:30 討議