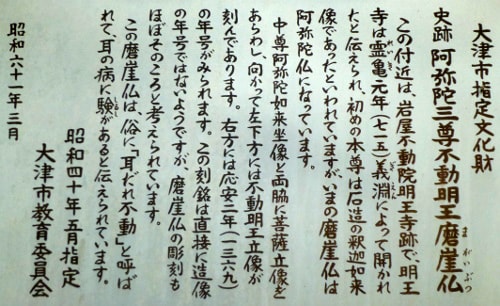野洲市歴史民俗博物館の催し
やっています、こんな秋期企画展
近江の自然災害-地震と水害の歴史-
会期:平成26年10月4日(土)~11月24日(祝)
(会期、休館日は主催者にご確認をお願いします)
 Kennyの滋賀から情報発信
Kennyの滋賀から情報発信 
この日記の掲載期間:10月17日~10月23日

当館で販売の冊子の表紙
この冊子で紹介されている内容
実例:
塩津港遺跡
寛文の大地震
明治29年の琵琶湖大洪水
昭和28年の野洲川大洪水
関連情報、事業:
近江における地震の痕跡
琵琶湖洪水と瀬田川浚(さら)え
企画展の内容、趣旨
近江における自然災害、特に地震、水害の歴史を紹介し、自然の脅威
と向き合い合ってきた近江の人々の歴史や暮らしを紹介するものです
そうか、滋賀にはこんな災害があったんだ
以下に掲載の写真は当企画展で展示の資料ではありません。私個人が保有の資料です。
記載の文面は、当冊子からその大部分を引用させて頂きました。
塩津(しおつ)港遺跡 お願いです、しお づ ではありません 

塩津港のある琵琶湖最北端(入江・湾)は早朝のなぎが美しいです
(撮影:2009年11月)
日本海(北前船などの)からの物資は揚げ地、敦賀港から塩津海道
を南下、この塩津港から琵琶湖を丸子船で湖南(堅田や坂本など)
に輸送され、現在の国道8線やIR北陸本線が開通するまではとって
も栄えた港でした。 私も小さい頃、この辺まで遊びにきていたんです。

この塩津港にあった神社が1185年に津波で破壊さ
れました。平家滅亡の年(壇ノ浦の戦)でもあります
(写真:滋賀県教育委員会、文化財保護課のHPより借用)

上下の写真、図は横田洋三先生の講座から(2012年1月28日)
(当時、私のブログで掲載のお許しを頂いております)


発掘調査: 津波で神社が押し流されて支柱が折れ北側に傾いて発掘されました

その支柱 発見された神像
私の過去のブログ: 地震と遺跡、塩津港遺跡は ここを
寛文の大地震 ・・・これは初耳!
寛文2年近江・若狭地震と呼ばれる大地震で江戸時代の寛文2年
(1662)5月1日に現在の近畿地方北部一帯に被害を与えた内陸
地震で大溝、大津、膳所、彦根等では壊滅状態になりました。

HP、「広報 ぼうさい」から拝借
この地震は、日向断層(若狭湾沿岸)と花折断層北部(琵琶湖西岸)の
連動で生じた地震と考えられています。
当広報のHPは ここを
明治29年の琵琶湖大洪水・・・こんなことも!
この大洪水で瀬田川回収工事が本格化、そして洪水防御を目的とした南郷
洗堰が明治38年(1905)に設置、同44年に改良工事は終了した。

ここまで水が 左右ともに滋賀県のHPより拝借
明治の29年の当大洪水詳細は ここを
昭和28年の野洲川大洪水(暴れ太郎、近江太郎)

現地看板の写真

新野洲川(放水路)が完成するまでは 南流、北流 の2本に分流
その二つの川の真ん中に設置された新野洲川放水路で洪水は収まった
写真:国土交通省のHPから拝借

三上山山頂付近から見た新野洲川(放水路)
(撮影:2014年9月)

野洲川、集中豪雨でもの凄い増水!! 撮影:2013年9月16日
もし、新野洲川放水路がなかったら・・・・
私の過去のブログ:野洲川の氾濫は ここを
関連情報、事業:
近江における地震の痕跡
県内の発掘調査では多数の地震痕跡が発見されている。例えば野洲の
古代遺跡からも確認されています。これらは琵琶湖周囲に集中しており、
地下水位が高く地盤が軟弱であった可能性が高い場所であることが指摘
されているとの事です。詳細は会場で写真などでの解説をご覧ください。

寒川 旭 氏
写真:HP・ 寒川 旭 氏 研究レポート:活断層・古地震研究報告から拝借
琵琶湖洪水と瀬田川浚(さら)え
琵琶湖から流れ出る唯一の自然河川、瀬田川は堆積した土砂が琵琶湖の水
位を上げて湖辺は冠水する恐れがあった。そこで江戸時代の川浚えを絵図
を掲げて、住民の苦労話も交えて紹介しています。 是非会場でお楽しみ
ください。
 該当HP ここを
該当HP ここを
瀬田川さらえに命をかけた太郎兵衛親子三代(上記HPより引用)
この企画展では
発掘された神像や土師器、箸などの実物。津波を受けて破壊した塩津港の
神社の想像図、野洲川氾濫当時の写真パネルなど数々の資料が展示されて
おり「一見に値する」に余りある企画展でした。
お断り: 当企画展で掲示の写真・絵図: このブログには借用(掲載)しておりません
博物館へのアクセス:


















































 同じ団地の仲間です。
同じ団地の仲間です。