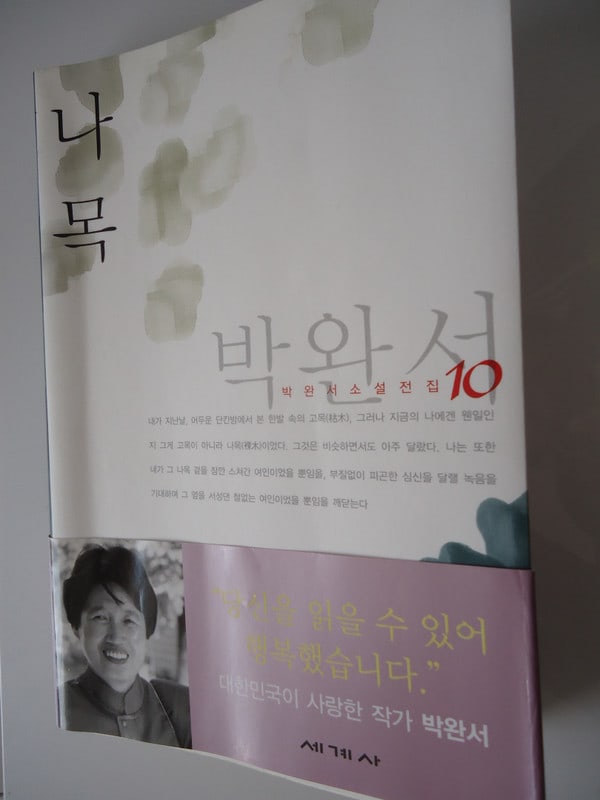翻訳 朴ワンソの「裸木」41<o:p></o:p>
128頁2行目から130頁最後まで<o:p></o:p>
私は息を殺した。そして全身の感覚でこの岩のような男が体の中で震えているのを感じた。いつの間にか私も震えていた。彼に掴まれた手がとても新しい感覚を伝えてきた。私は少しの間その新しい感覚に抵抗を感じた。彼に掴まれた手を抜き取ろうと思ったが、意外にも彼は頑強だった。有無を言わせず彼から男を感じた。<o:p></o:p>
心臓が早鐘を打ち始めた。私は彼に掴まれていない片方の手で左胸を抑えた。心臓が別個の生物になって、自分を閉じ込めている肋骨を蹴って飛び出すような危機を感じた。私は慌てて足を踏み外し、彼に引っ張られるようになっていた。彼は不安なほど強かった。ついに衝動的に止まって悲しい彼は飛び出しそうな私の心臓を、どっしりした自分の体重で押さえた。<o:p></o:p>
私はもう一度とても近くから彼の熱気を見て感じた。<o:p></o:p>
「気の毒に冷たく…震えているね」<o:p></o:p>
彼はとても震える声で私の耳殻がくすぐったいほど近くで囁いた。私は彼が何かとても恐れているのがわかった。そして私も同じく彼が恐れていることを怖がっていることを。<o:p></o:p>
私は怖いことが来るのを怖がりながら待った。彼の息遣いがためらいながら、それでも間違いなくやってくるのを感じた。私は首を後ろに反らして、彼の息遣いを受け入れる前に、高くそびえる聖堂の尖塔を見た。そうすると、いつかその前で忘れていた詩の一節が、異常なほど鮮明に浮かんだ。<o:p></o:p>
いつの間にか私は一息吐くように、それをとぎれとぎれに吟じていた。<o:p></o:p>
―マリア、あなただけは私達に情け深いです。あなたの血管で生まれた私達であります。憧れがどんなに胸を痛めるかを、あなたでなければ誰が知っているでしょうかー<o:p></o:p>
いずれにしてもその大事な瞬間を、そんな照れくさい振る舞いで台無しにしてしまったかもしれないのだ。<o:p></o:p>
彼の息遣いはそれ以上やってこなかった。私は物足りなさと安堵を同時に感じた。私達は再び歩きはじめた。ゆっくりとうつむいて曲がり角を回った。<o:p></o:p>
「寒い?」<o:p></o:p>
「ええ、とても寒いです」<o:p></o:p>
「今日が恐らく小寒だよ」<o:p></o:p>
「小寒の寒さが大寒の寒さよりもっと寒いのは変ですよね?」<o:p></o:p>
「私達の先祖のトリックだよ。真夏にこっそり立秋を入れたり、語感で酷寒や酷暑の苦しさを減らすという自然なトリックさ」<o:p></o:p>
「そうなんですね」<o:p></o:p>
実は私達もトリックを使っていた。私達は今になって小寒の寒さで震えていたように、震えも熱気もすべて小寒の寒さにして安心した。<o:p></o:p>
私達は一緒に道を渡って、何も話さずに路地を通り過ぎた。<o:p></o:p>
「零下何度ぐらいになるかしら?」<o:p></o:p>
「さあ、今朝が15℃だと言っていたが…」<o:p></o:p>
時々くだらない対話をぽつりぽつり交わしながら、平静さを取り戻していった。結局さっきの聖堂の前の会話を続けられないまま、私達は礼儀正しく挨拶を交わして別れた。<o:p></o:p>
家の前には馴染みのないジープが止まっていた。廃屋のように崩れ落ちた自宅の前に止まったジープは、まるで現実が迷子になって夢の中へ飛び込んだように非現実的に見えた。私は家に入るのを躊躇いながら、この不意の侵入者が私を煩わしくさせることに苛立ったが、外は零下15℃だった。私は全く寒さのために震えたくなかった。表門は開けたままで、石段には艶々した軍靴と粗末な軍靴が並んでいた。直ぐに本家のチンイ兄さんが来ているのがわかった。私は靴を脱ぎながら、二足の靴にびっしり開いた靴紐の穴があまりにも多く、靴紐をしても長く、そんな靴を履いて脱がなければならないチンイ兄さんが不憫に思われた。<o:p></o:p>
少しでも彼を不憫に思えるのはとても幸運だった。大きな心配事であったチンイ兄さんとの対決が、かなり容易に思われたのだ。<o:p></o:p>
チンイ兄さんは向かいの部屋の上座にごろっと横たわっていて、運転兵のような作業服の下士が、下座にぎこちない姿勢で座っていた。<o:p></o:p>
「いつもこんなに遅く帰るのかい?」<o:p></o:p>
生欠伸をしながら起き上って座ったチンイ兄さんは、初めから穏当でない気配がありありと見えた。<o:p></o:p>
「今日はちょっと遅くなりました」<o:p></o:p>
彼の前でしょげて元気がなくなるのは、以前からの習慣で今日も仕方なかった。靴の紐の穴が助けになるはずもなかった。<o:p></o:p>
ハンサムな顔が軍人らしくなく白く、相変わらず威厳があり貴族的な態度だった。中領という階級が見くびることが出来ない階級なのでではなく、軍人だったか将校だったかどうか、そんなこととは関係ない、彼独特の品位と威厳は、例え彼を公衆浴場の中に投げ込んだとしても、相変わらずだったろう。<o:p></o:p>
俗に国連ジャンパーと呼ばれる、中国の服のような格好悪い防寒服が、チンイ兄さんにはその高貴な態度をいささかも損傷させることなく、とてもよく似合った。<o:p></o:p>
私はオーバーを脱いで掛けたり、弁当箱を取り出したりする間、ひっきりなしにチンイ兄さんのその貴族的な顔にとてもよく似合っている、他人をちょっと見くびるような、やや斜め加減の笑いが私を追っているのを感じていた。しかしそんな不自由から脱け出す方法は絶望的だった。<o:p></o:p>
私は凍った手をチンイ兄さんが敷いているおくるみの下に置いて、下座の下士にまず声をかけた。<o:p></o:p>
「寒いのに、こちらにいらっしゃらないのね」<o:p></o:p>
及び腰のぎこちない姿で座っていた彼を、私は親密な同類のように感じた。しかし、彼は不当に扱われたように慌てて尻をもっと後ろに下げた。<o:p></o:p>
「職場が我慢できるかい?」<o:p></o:p>
「ええ、どうにか」<o:p></o:p>
しばらく話題が切れて、安らかな姿勢で座っていても、私は下座の下士と同じぐらいぎこちなかった。<o:p></o:p>
-続―<o:p></o:p>
★クリックをお願いします☆