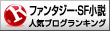残月剣 -秘抄- 水本爽涼
《旅立ち》第二回
市之進の下には二歳違いの源五郎という、常松にとってもう一人の兄がい た。その源五郎は、自らの名を忌み嫌った。虫のゲンゴロウと同じ名ということで、幼い頃から遊び仲間達から、『虫の源五郎!』と口々に揶揄(やゆ)され、常松が五歳になった頃には、七歳の兄は、すっかり外で遊ばなくなっていたのである。事はそれだけに止(とど)まらない。結果として常松は、兄の恰好の遊び相手にされてしまった。或る種、鬱積した不満の捌(は)け口が、常松に向けられたといっても過言ではない。幸いなことに、常松は未だ幼かったから、深慮する感情を持ち合わせておらず、故に救われたのである。
「竹刀(しない)は、こう持つのじゃ、常松!」
見よう見真似に竹刀を握り、相手をする常松に、源五郎は近づくや、竹刀の握り方を教えた。五歳の常松には、そう握らねばならない意味など分かる由もなかった。が、兄の云う通りにしなければ拙いのだ…と迄は分かった。それ故、云われるままに源五郎の相手をしていた。
ある時、勤めを終えて帰宅した父の清志郎が、渡り廊下を偶然、横切って、その様子を目の当たりにした。そして、清志郎は常松の非凡な太刀捌きを、己が眼に焼きつけることになったのである。源五郎の剣術稽古は時折り眼にしていた清志郎であったが、上達が早いと感じたものの、それ以上は何も思わなかった。だが、常松の太刀捌きは、明らかに源五郎の比ではなく、異質の勝れた何ものかを持ち合わせているように思えた。確かに、初めて竹刀を握る常松の手は震えており覚束(おぼつか)なかったが、源五郎へ打ち込むことは出来ないまでも、源五郎の太刀を、ことごとく打ち返したのである。