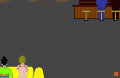残月剣 -秘抄- 水本爽涼
《惜別》第十七回
「おお…。当の本人を忘れていたわ。この話は左馬介から出たのだったな」
「はい…」
午後は稽古をせず、薪割りをする旨を長谷川が鴨下に告げた。
冬場の薪が些か春までは持たないと云う。左馬介も手伝う積もりだったが、その必要はないと長谷川があっさり蹴った。斧が二本しかないことも、その因か…と左馬介には思えた。刻限は既に未の刻近くになっていた。二人が薪割りをし、左馬介は権十を訪うことで決着し、三人は堂所を出た。
権十は百姓だから、訪なえば田畑にいるか、家にいるだろう…と考える。これは誰しもが思うところだ。ところが葛西の権十は、世間に数多(あまた)いる百姓とは少し違った。脚力に優れ、世間の噂には、めっぽう詳しかった。脚力を利用して、様々な場所へ出入りするから、当然のこととして、情報通になる。そこへ加えて権十は記憶力にも長けたから、葛西では生き字引と目された。だから、この堀川道場にしろ、野菜や米を持って差し入れた当時は、大男の神代などから耳寄りな話を入手したりしていた。ただ、それらを金蔓(かねづる)にしようとする下卑た魂胆は、さらさら持ち合わせていない、心根のいい男であった。