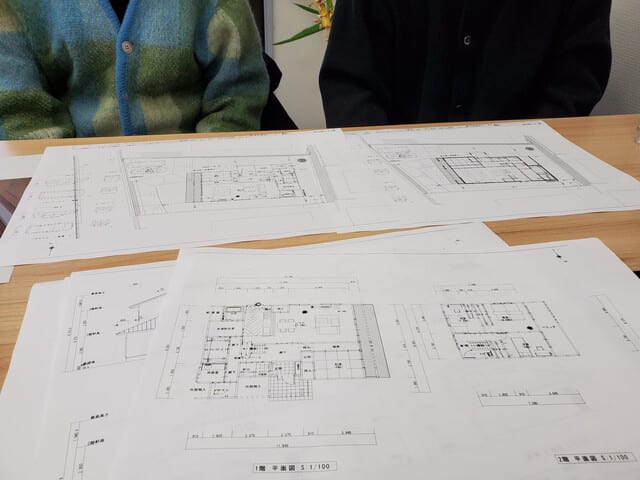広くて、日当たりがよくて、
景色が最高な土地。

※土地探しにて土地所有者・仲介業者了承の下で地盤調査中(地面下の軟硬)
そんな土地がいいな。
と土地探しをされている方、
なかなか希望の土地が出てこないなと
毎日インターネットで探されている方。
それぞれの事情を踏まえた
家造りに適した土地を探すためには、
コツがあります。
ちょっとしたコツですが、
知っていると知らないとでは
大違いです。
でも、
不思議とご説明する方法を
実践された方は
120点まではいかなくても
今まで探して見つけた土地が
60点だったとしたら90点くらいまでには
なるかも知れません。
実は土地を探すためには
順番と必要な準備があります。
これをしっかりと行わないと
希望の暮らしを実現できる土地に
巡り合う確率が上がる事はありません。
今回は土地を探していくための
コツをお伝えするblogになります。
土地を探そうと思われたとき
勿論・・・直接、
不動産会社窓口に出向く事も
あると思いますし
インターネットで
大手土地情報サイト等を使って
検索をされると思います。
まずは、取り組みやすくて
自由に検索できるので、
それらを行われると思います。
優秀な土地紹介サイトがあるので、
at homeさんや、
suumoさんも含めて、
皆さま「不動産会社の土地情報」を
チェックされていると思います。
実は、
多くの土地情報サイトに
掲載されている情報以外にも、
土地の資料を入手する方法があります。
でも今回は、
もう少し前段階のお話を
整理したいと思います。
冒頭に必要な
「順番」と「準備」があるということを
ご説明させていただきました。
これらに取り組んで、
初めて自分たちにとって
正解が近い土地資料を
手に入れる方法が
有効になってきます。
取り組むための
「順番」と「準備」が必要なのです。
土地探しに疲れてしまわれないように、
お伝えしたいと思います。
では、
それはどういったことを
行うことが良いのか?。
あくまで、
「世間的には自由設計と呼ばれる建て方」や
「本来の意味での注文住宅」で
住まいをご計画の方に向けた
方法をお伝えいたします。
建売住宅、規格住宅をご希望の方には
当てはまらないこともあるかもしれません。
箇条書きで示すと
① 建物を含めた総額の資金計画の目安
② 土地を選ぶ「基準(ものさし)」を持つこと。
③ 都市計画法・建築基準法をメインに
法律の知識が豊富で家を建てる為の土地探しの
実績のある建築士(建築家)と一緒に
土地を探すこと(土地の隠れた不安要素を見極める)
④ ○○○をチェックすること
⑤ ▲▲▲を行うこと。
という内容に集約されます。
残念ながら、④、⑤までは、
blogではご紹介ができません。
(気になる方は、相談にてお話をお伺いしながらご説明いたします)
えっそんなこと?
と思われる方も多いと思いますが、
ご説明させていただき、
取り組みをされた方は、
早い方では、1週間で
土地を見つけられた方もいらっしゃいます。
意外と、「そんなこと」ということが、
基本の「き」だったりするものです。
まず初めに、
① 建物を含めた、
総額の資金計画ができていること。
土地もないのに、
建物も計画していないのに、
総額なんてわからないという
声も飛んできそうですが、
ここがとても大切です。
なぜなら、
土地を探していくときに、
いくらの土地にすべきなのか?
ということがわからないと、
対象物の無いものを
探すことになります。
たとえば、
2000万円の土地がよいのか?
小学校が近い土地が良いのか?
駅が違い土地が良いのか?
土地を探していくための
条件によっては、
そもそも、
希望エリアに存在する土地なのか?
ということも含め、
建物を含めて金額がおさまるのか?
ということを考えていないと、
探すことができず、
当てのない迷宮に
迷い込むことになります。
実は、「気軽に土地を探しますよ」で
スタートするパターンから行きつく先が、
迷宮入りのケースになるように
感じています。
そして、
いくら探しても出てこない・・・・・。
希望の土地に巡り合えない。
土地探しに疲れた。
となることも。
これらは、
探すといっても、
「何を」「どのエリアで」「いくらで」
探してよいのかわからないことになり、
自分が何を探しているのかさえ、
わからなくなってしまうことがあるようです。
これでは、気の毒です。
そうならないように、
① 建物を含めた、
総額の資金計画を行うことはとても大切です。
家計のやりくりを預かる方にとっても、
全体像の予算が
しっかりとわかることが
安心にもつながっていきます。
総額の資金計画を検討していないと、
時には、
希望の場所で土地は探したけど、
高すぎて
建物が満足いく内容では建築できない
なんてことも・・・・・。
資金計画をして、
土地を探して、
ちょっと高い金額の土地では、
資金計画をやり直してみて・・・・・。
まずは「資金計画が大切です。」
では、そうやって
いくつか新しく巡りあえた
土地があったとしたとき、
次なる不安が出てきます。
それが、
次のフェーズになります。
② 土地を選ぶ「基準(ものさし)」を持つこと」
①を実践されてみて、
「土地を探すぞ」といって、
インターネットで情報を集めたり、
色々な土地、
現地を見に行った時に、
起こりうる現象です。
土地を見たけれど、
どう良いのかがわからない。
この土地を買っていいものか・・・?
などこういった事症状に
悩んでしまうことも。
この土地を買っていいものか・・・・・?」
いう症状が特にそうなのですが、
これは、
実現したい「こんな暮らしを実現したい」ということも
検討しておかないと、
「基準(ものさし)」がないから、
土地を住まい手さん自身が「はかる(判断)」事が
できないからになります。
こういったことに陥らないように、
おこなっている事があります。
それが、「コンセプト設計(コンセプトマップ)」です。
どんな住まいにしたいのか?。
どんな暮らしを実現したいのか?。
設計事務所ならではの判断で、
住まいの新しい要望を
コンセプトにまとめます。
「コンセプト」がご家族様で
共有出来ている事で、
家を建てる事によって得る
何が重要なのか?
土地を探す情報力・巡り合える機会は
加速します。
そうして、「コンセプト」を基に、
巡り合えた土地を
じっくりと観察して、
判断していくなかで、「コンセプト」があると、
ご家族様どうしでも、
土地のなんとなくの理想の形が
見えてくるはずです。
そして、
今回の最後に登場するのが、
③ 土地探しの実績のある建築士・建築家と
一緒に土地を探すという事になります。
土地を見つけてから、
建築士・建築家を連れていくことが
手順では?。
と思われる方もいらっしゃいますが、
そうではありません。
勿論先に「土地」購入済みのケースもあります。
それは既に「判断」が住んでいる訳ですが
一部「誤解」の上で購入されているケースもあります。
世の中の土地(分譲地も含めて)は、
どこでも、
当たり前のように、
住宅が建設できるように見えますが、
そうではありません。
その土地、
その場所特有の規制や、
法律が絡むので、
良さそうな広さの土地だけれど、
建物を建てるには、
予想外の法律の壁により
金額が別で必要になったり
土地と建物の比率の法律や
屋根形状や使用する材料の制限等、
思わぬハードルが現れることもあります。
※実際に市町村による水道の
新規本管埋設不可のケース(100メートル以上自己負担)や
電柱からの新規引き込み不可距離等ありました。
②でおこなった、「コンセプト」作りにもとづいた内容が、
この土地は、○○ができるけど、▲▲はできにくいかも。
この土地は、明るくてとても良いけど、
コンセプトにした●●はできないかも。
などが発生する事も。
後者の場合は、
「コンセプトを再度検討する。」ということもアリですが、
片方のコンセプトができるけど、
もう片方のやりたかったことは
出来ないかもしれない等。
土地だけではなくて
建築を計画する建築士・建築家の
職能だから提案できて、
分析できることもあります。
時には土地を踏まえて、
再度コンセプトを練り直すことも
必要になります。
長文になってしまいましたが、
土地を探すうえで、
行き詰ってしまった、
ちょっと土地探しにつかれた。
という方にとって、
少しでもヒントになれましたら幸いです。
今回ご紹介した手順のほかにも、
大切な土地探しの必須手順もあります。
「こんな暮らしを実現したい。」を
リアル化して考えてみると
見えてくる事もあると思います。
住まいの新築・リフォーム
リノベーションのご相談・ご質問・ご依頼は
■やまぐち建築設計室■
ホームぺージ・Contact/お問い合わせフォームから
気軽にご連絡ください。
-------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
https://www.y-kenchiku.jp/
-------------------------------------