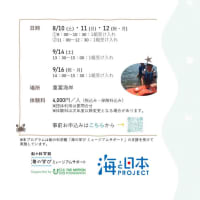安定しないのが春の空模様なのでしょうか。
昨日は、気持ちよく晴れ渡っていましたが、今日は雨が降りそうな、降らなそうな微妙な空模様です。
強風が吹くからか、鹿児島の海岸にクジラが打ち上がったり、
イルカが打ち上がったりしています。
春の嵐がはやく落ち着くといいですね。
Facebookで紹介されていたブログがあります。
てらっこ塾瓦版
このブログを読んで、支援クラスに在籍し、
支援学校の高等部に進学したお子さんのことを思い出しました。
その子は、勉強はおそらく、普通にできる子だったのですが、
弱視だったことと、そこからくる引っ込み思案の性格から、中学校では支援クラスに在籍していました。
支援クラスではのびのびと物をいい、勉強の意欲もあるのですが、
親学級では同級生たちが「話すところをみたことない!」と言うほどに、
じっっとして、物も言わずに過ごしているような子でした。
負けず嫌いで、漢字を覚えることが苦手でしたが、
漢字のお手本を大きく拡大してコピーし、漢字の意味を考える学習をしていくと、
面白くなったようで、漢字検定のプリントに挑戦するようになりました。
その子の進路は、だいぶ悩んでいたようでしたが、
「クラスの人数が少ない方がいい」ということ、「就職できるように」ということが、
本人と保護者さんの進路選択で重要事項だったことから、
支援学校の高等部に行くことになりました。
その子は、入試が終わってからも「将来に向けて!」と、
大好きな数学と少し楽しくなりはじめた漢字検定の学習を中学卒業まで取組んでいました。
入学して、半年以上経ってから、その子の行った支援学校の高等部に、
私はその子の後輩になるであろう子どもたちと体験入学の行事で訪れました。
そこで、会った高等部で1年生となった子が、
私に言った第一声は、
「数学の続きもないし、漢検とかもない高校だったよ。勉強ないんだよ。」と言うことでした。
進路を決めるときに、「もっと勉強できる学校もあるし、そういう選択肢もあるよ。」ということは、
その子の学力を考えて、担任の先生も話されていたように思います。
でも支援学校の高等部に行くことで、知的欲求を満たす部分とは、ばっさり、縁遠くなってしまう。
それでも、いいのか?そんなことは子どもに聞くことはなかったように思います。
別の支援学校の高等部に行った子も「宿題ないんだよ…」と、
夏休みに会ったときに真っ先に話してくれましたが、晴れやかではないその顔に、
その子の知的欲求の満たされなさを思い、なにかできないかなぁ、と思ったことでした。
高校を卒業すると仕事をする子も多くいます。
支援学校の高等部に行く子たちも、そんな子たちと同様、といえば同様かもしれません。
でも、凸凹の多い子どもたちが、ゆっくりと学習の面白さや自分の好きな教科、
知的好奇心をくすぐる何者かを得たときに、ばっさりとそことの縁を切られてしまうのが、
支援学校での就職メインの学習なのかもしれません。
働くことも大切ですが、自分の知的好奇心を満たす術を育てることも、
人生の中では大切なことだと思います。
知的障害があっても、重度の障害があっても、
その子には、その時、その時の、興味関心があり、知的欲求があるということを
支援者としては、忘れないようにしたいものだなぁ、と思います。
昨日は、気持ちよく晴れ渡っていましたが、今日は雨が降りそうな、降らなそうな微妙な空模様です。
強風が吹くからか、鹿児島の海岸にクジラが打ち上がったり、
イルカが打ち上がったりしています。
春の嵐がはやく落ち着くといいですね。
Facebookで紹介されていたブログがあります。
てらっこ塾瓦版
このブログを読んで、支援クラスに在籍し、
支援学校の高等部に進学したお子さんのことを思い出しました。
その子は、勉強はおそらく、普通にできる子だったのですが、
弱視だったことと、そこからくる引っ込み思案の性格から、中学校では支援クラスに在籍していました。
支援クラスではのびのびと物をいい、勉強の意欲もあるのですが、
親学級では同級生たちが「話すところをみたことない!」と言うほどに、
じっっとして、物も言わずに過ごしているような子でした。
負けず嫌いで、漢字を覚えることが苦手でしたが、
漢字のお手本を大きく拡大してコピーし、漢字の意味を考える学習をしていくと、
面白くなったようで、漢字検定のプリントに挑戦するようになりました。
その子の進路は、だいぶ悩んでいたようでしたが、
「クラスの人数が少ない方がいい」ということ、「就職できるように」ということが、
本人と保護者さんの進路選択で重要事項だったことから、
支援学校の高等部に行くことになりました。
その子は、入試が終わってからも「将来に向けて!」と、
大好きな数学と少し楽しくなりはじめた漢字検定の学習を中学卒業まで取組んでいました。
入学して、半年以上経ってから、その子の行った支援学校の高等部に、
私はその子の後輩になるであろう子どもたちと体験入学の行事で訪れました。
そこで、会った高等部で1年生となった子が、
私に言った第一声は、
「数学の続きもないし、漢検とかもない高校だったよ。勉強ないんだよ。」と言うことでした。
進路を決めるときに、「もっと勉強できる学校もあるし、そういう選択肢もあるよ。」ということは、
その子の学力を考えて、担任の先生も話されていたように思います。
でも支援学校の高等部に行くことで、知的欲求を満たす部分とは、ばっさり、縁遠くなってしまう。
それでも、いいのか?そんなことは子どもに聞くことはなかったように思います。
別の支援学校の高等部に行った子も「宿題ないんだよ…」と、
夏休みに会ったときに真っ先に話してくれましたが、晴れやかではないその顔に、
その子の知的欲求の満たされなさを思い、なにかできないかなぁ、と思ったことでした。
高校を卒業すると仕事をする子も多くいます。
支援学校の高等部に行く子たちも、そんな子たちと同様、といえば同様かもしれません。
でも、凸凹の多い子どもたちが、ゆっくりと学習の面白さや自分の好きな教科、
知的好奇心をくすぐる何者かを得たときに、ばっさりとそことの縁を切られてしまうのが、
支援学校での就職メインの学習なのかもしれません。
働くことも大切ですが、自分の知的好奇心を満たす術を育てることも、
人生の中では大切なことだと思います。
知的障害があっても、重度の障害があっても、
その子には、その時、その時の、興味関心があり、知的欲求があるということを
支援者としては、忘れないようにしたいものだなぁ、と思います。