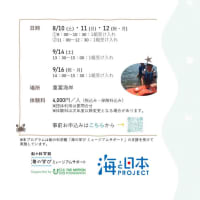早朝の仕事が休みだと、
「あれもしよう、これもしよう」と思っています。
が、普段早起きの私に付合っている猫たちが、
「あれ、今日、居るの?」と膝に乗ってきたり、
私の足を枕に寛いでいるのを見ると、
ついつい、いっしょにだらりモード。
猫に引っぱられる人間です。
数の習得については、
算数、数学の方面からの研究が多いのでしょうが、
認知心理学という方面からも色々研究がなされているようです。
認知心理学の研究からも、
乳児は、3つまでの数は見てすぐにわかり、
人間は生まれながらに数の能力をもっているといえるというのです。
その実験は、10~12ヶ月の乳児に目の前のスクリーンに、
2頭の馬の絵、2体の人形の絵と同じ数の絵を繰り返し見せていき、
乳児が絵を見ている時間を測定します。
乳児は飽きてくると絵を凝視する時間が短くなるのですが、
そこに3匹の犬の絵と、対象の数を変えて見せると、
乳児がその新しい刺激に関心を示して、凝視時間が長くなることから、
乳児は2と3を区別しているという結果を得たそうです。
ちなみに、3と4、4と5では凝視の時間に違いは見いだされなかったそうです。
このような、乳児の生まれながらの能力は、
後の数の概念の獲得の基礎になっているとも考えられると、
認知心理学の中では考えられているようです。
これは、昨日のブログでも書いた、
「1~3は直観でつかめる数字」ということにもつながるのでしょう。
計算や数が苦手な子どもさんは、
まず、この3までの数で色々と遊ぶと、
生まれながらに備わっている数の能力の強化につながって、
その後の数の獲得への橋渡しになるのではないかと思います。
遊びもブロックを1つのもの2つ繋げたものや3つ繋げたものを分類したり、
3までのカードを使っての神経衰弱やお互いにカードを出し合って勝負をしたり、
1、2、3でジャンプしたり、ボールを投げて1、2、3と手を叩いたり、
なんでも、良いと思います。
そんな幼稚な遊びを…と思うかもしれませんが、
子どもは案外、飽きずに遊びます。
「3までじゃなくても…」と思う大人心ですが、
安心してください、飽きれば子どもが勝手に数を増やします。
こうして、算数と近からず、遠からずの場所で、
数と遊ぶことが計算への道へとつながっていきます。
「あれもしよう、これもしよう」と思っています。
が、普段早起きの私に付合っている猫たちが、
「あれ、今日、居るの?」と膝に乗ってきたり、
私の足を枕に寛いでいるのを見ると、
ついつい、いっしょにだらりモード。
猫に引っぱられる人間です。
数の習得については、
算数、数学の方面からの研究が多いのでしょうが、
認知心理学という方面からも色々研究がなされているようです。
認知心理学の研究からも、
乳児は、3つまでの数は見てすぐにわかり、
人間は生まれながらに数の能力をもっているといえるというのです。
その実験は、10~12ヶ月の乳児に目の前のスクリーンに、
2頭の馬の絵、2体の人形の絵と同じ数の絵を繰り返し見せていき、
乳児が絵を見ている時間を測定します。
乳児は飽きてくると絵を凝視する時間が短くなるのですが、
そこに3匹の犬の絵と、対象の数を変えて見せると、
乳児がその新しい刺激に関心を示して、凝視時間が長くなることから、
乳児は2と3を区別しているという結果を得たそうです。
ちなみに、3と4、4と5では凝視の時間に違いは見いだされなかったそうです。
このような、乳児の生まれながらの能力は、
後の数の概念の獲得の基礎になっているとも考えられると、
認知心理学の中では考えられているようです。
これは、昨日のブログでも書いた、
「1~3は直観でつかめる数字」ということにもつながるのでしょう。
計算や数が苦手な子どもさんは、
まず、この3までの数で色々と遊ぶと、
生まれながらに備わっている数の能力の強化につながって、
その後の数の獲得への橋渡しになるのではないかと思います。
遊びもブロックを1つのもの2つ繋げたものや3つ繋げたものを分類したり、
3までのカードを使っての神経衰弱やお互いにカードを出し合って勝負をしたり、
1、2、3でジャンプしたり、ボールを投げて1、2、3と手を叩いたり、
なんでも、良いと思います。
そんな幼稚な遊びを…と思うかもしれませんが、
子どもは案外、飽きずに遊びます。
「3までじゃなくても…」と思う大人心ですが、
安心してください、飽きれば子どもが勝手に数を増やします。
こうして、算数と近からず、遠からずの場所で、
数と遊ぶことが計算への道へとつながっていきます。