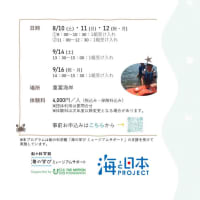蝉が朝は鳴いていますが、日が高くなり暑さが増すとピタリと鳴かなくなります。
蝉も暑くならないうちに鳴いて、暑さ増す時間はお昼寝でしょうかねぇ。
さて、背骨メモの続きです。
私たちは、転倒や打撲などで無理な姿勢をとってしまっても、特に支障なく日常生活を送ることができます。
これは背骨のS字カーブや関節など様々なサスペンション機能が身体に備わっていて、それらの機能が身体にかかる負荷をバランスよく吸収してくれているからです。
しかし、骨折や外傷で極端に身体が損傷を受けると身体のバランスは崩れてしまいます。
また、普段の生活や仕事などで、いつも同じ姿勢をとり続けることでも、身体が過度に負荷を受け続けることになり、身体のバランスは崩れてしまいます。
身体に過度な負担がかかると、背骨はその構造が破綻をきたし、前後左右に無理な姿勢を自然にとってしまい、S字カーブの維持が難しくなります。
その結果、局所的な筋肉のコリが生じたり、血行不良が起こったりと身体の不調が連鎖的に生じることになります。
一見、姿勢の維持とこれらの症状は無関係に感じますが、背骨には血管、リンパ管、神経が通っています。
背骨が歪むと圧迫を受けている神経支配の内臓のはたらきを鈍らせます。また、血流の流れを悪くして全身に酸素や栄養が供給されにくい状態を作り出します。
すると、細胞内の老廃物が排出されにくくなり、身体が不調をきたすことになります。
今日はここまで!次回で最後です。
極端に背骨が曲がったり、歪んだりしていなくても身体への慢性的な不調がある場合、自分の常日頃の姿勢、姿勢の癖を見直してみるといいかもしれないですね。