(呉春筆 蕪村像)
蕪村の俳句を評論した文集は多い。江戸期後半には、俳人として、ほぼ無視されていた蕪村俳句を掘り起こしたのは、明治になって正岡子規である。以来、多数の俳人あるいは評論家が蕪村の俳句を独自の視点で解釈・評論している。それぞれの特徴を取り出し、その評価と批判を行なった。
1) 中村稔「与謝蕪村考」(青土社)2023
著者は弁護士さんのようである。弁護士の俳句評論とは、かかるものかと納得した。著者は、まず他の評者の意見を紹介し、裁判における相手側の陳述書に対するように、これに反論していく。たとえば蕪村「春風馬堤曲」の章では尾形功の解釈を紹介し、たまに同意することもあるが、ほとんどケチをつけている。その立場は、有体に言って弁護士リアリストとしてのもので、揚げ足取りで面白くない。たとえば、俳詩「春風馬堤曲」に登城する主人公を軽佻浮薄な女の子の道行ととらえている。中村は、「尾形は学者のくせに想像力が過剰すぎる」と批判してるが、尾形の解釈の方が、ずっと豊かで楽しい。ようするに面白くないのだ。かといって弁護士的リアリズムに徹しているかというと、そうでもない。たとえば、蕪村の「離別(さら)れたる身を踏込んで田植えかな」の解釈を、離縁された女性が田植え時期に員数合わせで婚家に呼び寄せられ手伝う情景としている。これは、珍しく尾形の「蕪村全集」での校註に従ったようだが、常識的にはありえない話だ。藤田真一は、出戻ってきた娘が実家の田植えの作業に参加するときの複雑な心境としている。これが普通の解釈であろう。また、蕪村「鮎くれてよらで過行く夜半の門」の句でも、中村は「くれて」と「過行く」の措辞が矛盾していると述べている。しかし「過行く」は家に入らないでという意味に決まっているではないか。それに、この句の主人公は友人でも家の主人でもなく「鮎」であることを忘れている。釣り上げて足の速い鮎を配る友人の心遣いが、よみとれないようでは駄目だ。ただ、本書は、蕪村の生活句を「境涯詠」などに分類するなど、いままでにみられない新たな分類を行った点で評価できる。子規や朔太郎は生活者としての蕪村の句をまとめなかった。100点満点で65点。
2)藤田真一 「蕪村」(岩波文庫705)2000
これは蕪村俳句の評論集ではなく、俳人蕪村を多角的に分析した評伝のような構成になっている。藤田は当時、京都府大の教授であった。春風馬堤曲の鑑賞においては、藪入り少女のちょっとはしゃいだ気持ちと故郷への想いが錯綜した道行きとして無理なく解説されている。「融通無碍な発想があって、そのくせ人間らしい心が、ふわっと伝わる蕪村の俳諧世界を紹介したい」と著者はいっている。学者の評論であるが、蕪村のほのぼのとした人柄を伝える佳作である。藤田には他に「蕪村の名句を読む」(河出書房)や「風呂で読む蕪村」(世界思想社)がある。いずれも蕪村自身の独白でもって、代表句を紹介するユニークな著書である。この中の蕪村「滝口に燈を呼声やはるの雨」は、貴人と武士が経験する時間の対比論で鑑賞した名解釈である。90点。
3)正岡子規 「俳人蕪村」(講談社文芸文庫)1999
明治30年4月13日から11月15日まで、子規が「日本」及び「日本付録通報」に連載したものである(底本は明治32年「ほととぎす発行)。子規によると生存中、蕪村は画人としてより俳人として有名だったそうだ。それが死後、画人蕪村として知られ、その俳句はほとんど評価されなかったそうだ。しかし子規派の再評価により、その俳名が再び画名を上回ってきたと自画自賛している。ここでは、蕪村の俳句を「積極的美」「客観的美」「人事的美」「複雑的美」「理想的美」などに分類し、用語の自由性、句法の革新性、句調の斬新性、味のある特殊な文法(間違った文法なのに句に趣をあたえている)、材料の特殊性を挙げている。そして、それぞれの項目で該当する例句を挙げている(材料の特殊性では「公達に狐ばけたり宵の春」など)。すべての句をくまなく読み込んで整理したのであろうが、おそるべき気力と分析力である。春風馬堤曲に関しては、あまり詳しい解説はないが、「蕪村を知るこよなきもので、俳句以外に蕪村の文学としてはこれ以外にはない」としているが、一方で新体詩の先駆けを開けなかったことを惜しいんでいる。
この著の圧巻は蕪村の「創造的文法誤謬」論である。蕪村は結構、文法を無視した作品を作った。「をさな子の寺なつかしむ銀杏かな」の「なつかしむ」について子規は次のように語る。
「これは蕪村の創造した動詞であろう。果たしてそうとすると蕪村は傍若無人の振る舞いをした者といえる。しかしながら、百年後の今に至ってこの”なつかしむ”を引き続き用いている者は多数いる。蕪村の造語はいつか辞書にも載るようになるだろう。英雄の事業というものはこのようなものである」(筆者口語訳)
ともかく、この評論や他著「蕪村と几董」などによって、埋もれていた蕪村俳句は、近代によみがえった。只一点ケチをつけると、子規は最後の方で「蕪村の悪句は埋没して佳句のみのこりたるか。俳句における技量は俳句界を横絶せり、ついに芭蕉其角の及ぶ所に非ず」としているが、蕪村俳句全集をみるに必ずしもそうでない。駄句、凡句も結構ある。99点。
4)萩原朔太郎 「郷愁の詩人・与謝蕪村」岩波文庫 1988
詩想(ポエジイ)にあふれたセンチメンタリストとしての蕪村を定着させた朔太郎の有名な書である。個人誌「生理」に昭和8-10年連載された。ここでは、まず子規派が、蕪村俳句を写生主義として規定してしまったことを批判している。しかしこれは明らかに誤解である。前の「俳人蕪村」を読んでも、たしかに「直ちにもって絵画となしうべき」ような作品を「客観的美」として分類しているが、それは蕪村俳句のジャンヌの一つにすぎない。ほかに人事句など、あまりロマンにみちたものではないのも子規は紹介している。朔太郎も「我をいとふ隣家寒夜に鍋を鳴らす」を紹介しているが、これなんかロマンどころか生活がにじみ出た俳句だ。むしろ、リリシズムの極致である「花茨故郷の路に似たるかな」の引用を抜かしている。これを抜かしてはいかん。蕪村はクリスタルグラスのような多面体である。時代のせいかも知れないが、朔太郎の読みは浅いのではないか。ただ蕪村の飄逸な書体を評して、彼を「炬燵の詩人」としたのは慧眼である。90点、
5) 竹西寛子「竹西寛子の松尾芭蕉集 与謝蕪村集」集英社 1996
竹西寛子は原爆体験をもった小説家であり文学評論家である。ここで竹西寛子は蕪村の俳句を一句づつ解釈していくが、その内容は極めて良識的で納得できるものである。壮大な「菜の花や月は東に日は西に」から生活句「菜の花や笋見ゆる小風呂敷」まで蕪村世界を無難にこなしている。「鮎くれてよらで過行く夜半の門」の夜半は夜中ではなく、夜半亭の事だとする宮地伝三郎(京大教授で動物学者)の説も紹介している。それなりに勉強したということであろう。ただ驚くほど新鮮な解釈を披露しているわけでない。80点
6) 小西甚一 「俳句の世界(第七章 蕪村)」 講談社学術文庫 1995
俳諧の起源から説きはじめた俳句の歴史書における蕪村論である。「樟の根をしずかにぬなすしぐれかな」の「しずかに」の用法が当句を名品に仕上げたという解説には感じいった。断章での解説であるせいか、評論対象の選句が自由で斬新な雰囲気ではあるが、短いのでものたりない。75点。
7) 森本哲郎 「詩人与謝蕪村の世界」講談社学術文庫 1996
森本哲郎(1925-2014)は)新聞記者を経て評論家となり東京女子大教授。「世界の旅」など多数の著書がある。俳人でも文学者でもない政治畑のジャーナリストの蕪村論である。雑誌「国文学」に掲載されたものをまとめたらしいが、理由はあとがきを読んでもよくわからない。ただ「私は蕪村が好きだ。蕪村の世界をこのうえなく美しいと思う」と述べている。好きでなかったら書けない。テーマ別に18章で構成されている。どれも蕪村俳句を様々な角度から解説するが、著者の博覧強記にはおどろくほかない。「島原の草履にちかきこてふかな」の句について、プラトンのイデア論を挽きつつ、「世界は仮の相であり、夢であり、幻であり、影であるというあの荘子の哲学は、蕪村の芸樹の中では独特の美学となり十七文字に結晶している」と述べている。子規、朔太郎の評論に次ぐ記念すべき書である。95点。
8)高橋治 「蕪村春秋」朝日文庫 2001
高橋治(1929-2015)直木賞作家、映画監督。「蕪村に狂う人、蕪村を知らずに終わる人。世の中には二種類の人間しかいない」と強烈なフレーズで始まる映像作家の蕪村論。「鮎くれてよらで過行く夜半の門」は夜釣り、火振り漁としているが、鮎を渡す手元から家の門を遠景にしたズームアウトの手法が凄いと言っている。また「花野」の項で日本人は本当は自然を大事にしないのに、その美を「仮託」する悪いくせがあり、近代においてはさんざん環境破壊を繰り返してきたと述べている。同感である。85点
9)稲垣克己 「蕪村のまなざし」 風媒社 2009
作者は1929生まれの銀行勤務経験者。「守ろうシデコブシ」(中日新聞)などの著書がある。前半は句評で後半は蕪村の事績の紀行集になっている。蕪村は京都で四条烏丸東イル、室町綾小路下ル、仏光寺釘隠町に転々と寓居を変えたそうである。
蜻蛉や村なつかしき壁の色
いな妻や波もてゆえる秋津島
屋根ひくき宿うれしさよ冬ごもり
咲くべくもおもわであるを石路花
これらの句は他の評者は取り上げていない。これをみても庶民派蕪村を現代の蕪村が誠実に紹介している。80点。
10)佐々木丞平、佐々木正子、小林恭二、野中昭夫 「蕪村:放浪する文人」新潮社
蕪村句の評論集というより蕪村作品(絵画を含む)の写真集といった本である。蕪村句そのものの評論は中村氏による1章「俳人蕪村の実力」という短い一章がある。蕪村句はほとんど駄句であるが、中にはホームラン級のがあると言っている。駄句や凡句もあるが、言い過ぎだろう。あまり元気のでる話ではない。70点。














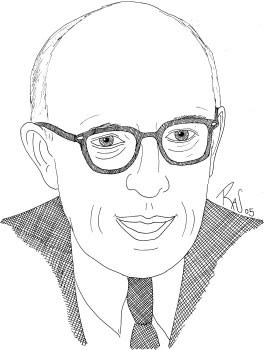

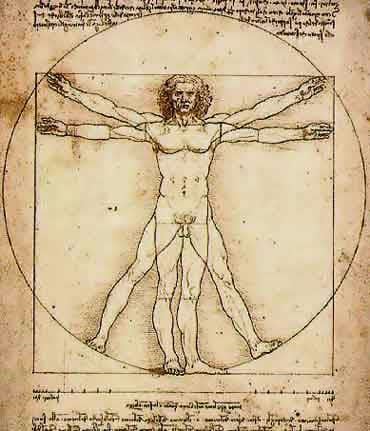

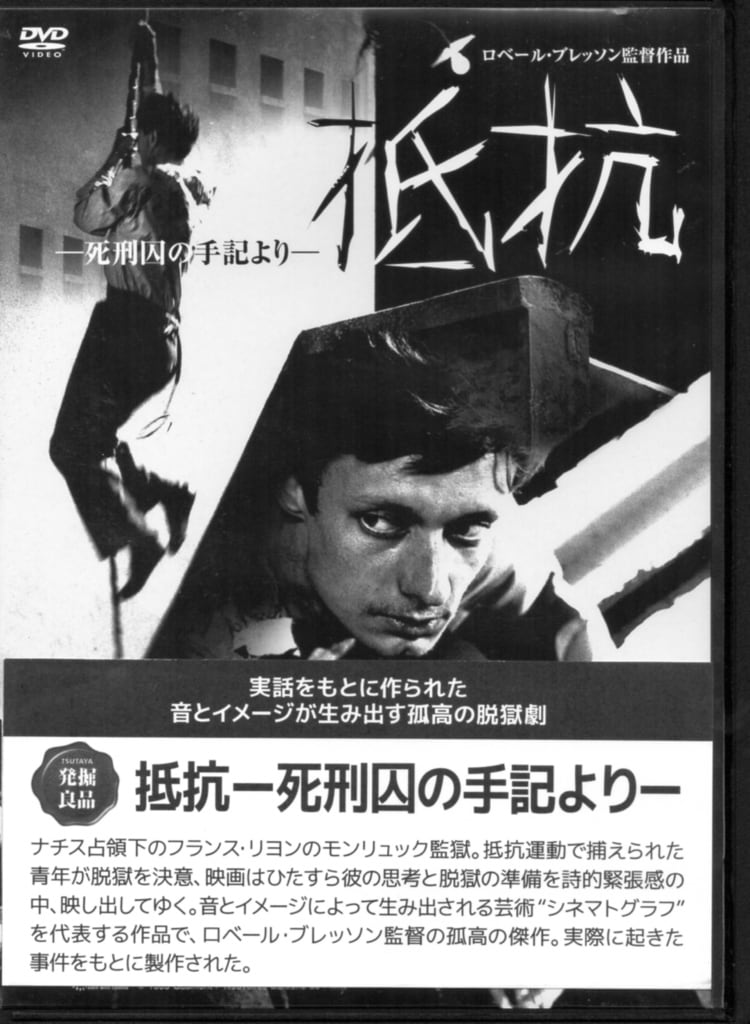








 (写真 1)
(写真 1) (写真 2)
(写真 2) (写真」3)
(写真」3) (写真 4)
(写真 4) (写真 5)
(写真 5)










