ロボットによる外科手術というと、まだ未来の話と考える方が多いと思いますが、実は既にアメリカ、ヨーロッパで2千台近くの医療ロボットが稼働し、通常診療としておこなわれています。この手術支援ロボットは、アメリカで1990年代から、傷ついた兵士を米国本土や空母から医師が遠隔操作で手術するという発想から開発が始まり、2000年に承認されたシステムです。解剖学の分野でも業績を残したイタリアの天才の名を取って「ダ・ヴィンチ」と名付けられました。韓国でも2005年から始まり、現在30台以上が導入され、保有台数は、アメリカ、イタリアに次いで世界3位、年間4000件以上の手術がこの医療ロボットにより施行されています。特に泌尿器分野で多く利用され、欧米では前立腺癌の手術の70%以上が「ダ・ヴィンチ」による手術です。
一方、ロボット先進国日本ではというと、このシステムが薬事法上の承認を受けたのが、ようやく2年前で、国内では6台ほどが導入され、実際の手術も研究目的が主で、本格的な治療はこれからという段階です。日本の場合、厚労省での新薬や新しい医療機器治療、治療法に関しては慎重で、審査やその承認には、他国と比べてかなり時間が必要で、高度先進医療の臨床部分での導入が遅れがちであるという声も聞こえます。また、保険と自費の混合診療が認められておらず、ある疾患の治療に、一部自費負担で行うということができない為、いきなり全額負担となり、その面でも「ダ・ヴィンチ」の導入が進まない理由があるかも知れません。こうした状況で追い打ちをかけるように、昨年9月に名古屋大学でこのシステムを使用して胃がん手術を行った男性患者が手術後に亡くなるという発表がありました。ロボット手術と言っても、外科医が3D画像を見ながら、やや離れたコックビットでロボットアームを操作して行う内視鏡手術であり、当然 医師の熟練と経験が必要なものです。手振れが少ない、より繊細な内視鏡操作が可能とされ、直接手動でやるより有利性も多い反面、全ての手術が可能ではなく、適応判断が必要です。医療において安全性は何より優先されるべきですが、新しい治療法の開発と進歩には、どうしてもある程度のリスクが伴うということは、常に医学における課題でしょう。
‘健康に生きるには’という問いに、ダ・ヴィンチはこんな言葉を残しています。「医者を割けよ。その薬は錬金術の一種。それを飲むものは間違った忠告を受け入れている。」当時の医学レベルの問題か、彼が医者嫌いだったのかは解りません。














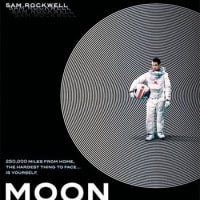
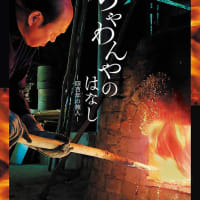










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます