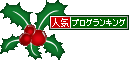大人の社会見学 コンペイトウ“ツノ”の秘密は?(産経新聞) - goo ニュース
□大阪糖菓 大阪府八尾市
カラフルで、甘くて、昔懐かしいお菓子、コンペイトウ。いまでは全国でも数少ないといわれるメーカーのひとつが大阪府八尾市の大阪糖菓だ。表面に“ツノが生える”秘密や、隠れた職人技…。工場をのぞくと、コンペイトウがゆっくり、じっくり大きくなる様子に驚かされる。(文・川西健士郎)
◆1日1ミリ成長
工場には直径1.8メートルの巨大な釜が16基も並んでいる。それぞれが100度以上の高熱に熱せられ、室内の温度計は47度を示している。
釜は30~40度に傾きながら常に回転している。すべての釜にコンペイトウの丸い粒がたくさん入っていて、数秒かけて上に上がり、ザーという音をたてて下にずり落ちる動作を繰り返している。そこに一定の間隔で機械から蜜が噴射され、コンペイトウの表面に行きわたることで大きくなっていくのだ。
釜の高熱で蜜の水分が飛ばされるため、粒が大きくなるスピードは直径でいうと1日わずか1ミリほど。芯の役割をする数ミリ大のグラニュー糖から、コンペイトウが完成するまでには10日~2週間がかかるという。
◆職人技で24個
こうしてコンペイトウが大きくなる過程でツノが生えてくるというが、いったいどうやって…。工場の職人によると、蜜がかかった粒がぶつかり合うことで、1粒に約50個の小さな突起ができる。さらに蜜がかかるとツノは太く長くなるものと、消えていくものに二分される。不思議なことに、コンペイトウ1個につき、24個のツノができるという。
コンペイトウの最大の特徴であるツノをうまく隆起させるのはコンペイトウ職人の腕の見せどころ。季節や天候に応じた釜の角度の微調整や蜜をかけるタイミングができ映えに影響するという。
製造課長の藤野昌司さん(46)は「うまく調整ができているかは、蜜の乾き具合やコンペイトウの転がり具合でわかります」と話す。
◆南蛮文化が原点
本社工場には、コンペイトウの歴史を学んだり、“マイ・コンペイトウ”を作る「コンペイトウミュージアムやお」が併設されている。
そこに登場するのは怪しげな南蛮人。フロイス野村と称するこの人、実は大阪糖菓の野村卓社長だ。見学者の前にふらっと現れてコンペイトウの知識を解説したり、ギターで南蛮音楽を披露したりするのだが、どうして南蛮人なのか。
社長によると、コンペイトウは16世紀にポルトガル人宣教師のルイス・フロイスによって日本に持ち込まれたという。江戸時代に長崎の町人が国産化、明治に大阪で量産化が始まり、古き良き昭和には駄菓子屋に並んだ。しかしいまは、チョコレートやスナック菓子におされっぱなし。
「このままではコンペイトウはなくなってしまう」
そんな社長の危機的な思いもあって、直径1ミリなのにちゃんとツノがある世界一小っちゃなものや、伝来当時の味を再現した「信長の金平糖」などのアイデアを次々と商品化。コンペイトウの新たな魅力を発信している。
【会社概要】大阪糖菓
大阪府八尾市若林町2の88。昭和15年創業。コンペイトウづくりの体験工房「コンペイトウミュージアムやお」が工場に併設され、平日は工場見学も可能。10人以上からで料金は千円。堺市の同社堺工場の体験工房は3人以上からで800円。いずれも事前予約((電)072・948・1339)が必要。
出来上がるまで10日から2週間もかかるとは驚きです。
ふdsん何気なく食べているお菓子にも職人技が生かされているものがあることは驚きます。
☟クリックしていただけると嬉しいです。
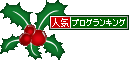
□大阪糖菓 大阪府八尾市
カラフルで、甘くて、昔懐かしいお菓子、コンペイトウ。いまでは全国でも数少ないといわれるメーカーのひとつが大阪府八尾市の大阪糖菓だ。表面に“ツノが生える”秘密や、隠れた職人技…。工場をのぞくと、コンペイトウがゆっくり、じっくり大きくなる様子に驚かされる。(文・川西健士郎)
◆1日1ミリ成長
工場には直径1.8メートルの巨大な釜が16基も並んでいる。それぞれが100度以上の高熱に熱せられ、室内の温度計は47度を示している。
釜は30~40度に傾きながら常に回転している。すべての釜にコンペイトウの丸い粒がたくさん入っていて、数秒かけて上に上がり、ザーという音をたてて下にずり落ちる動作を繰り返している。そこに一定の間隔で機械から蜜が噴射され、コンペイトウの表面に行きわたることで大きくなっていくのだ。
釜の高熱で蜜の水分が飛ばされるため、粒が大きくなるスピードは直径でいうと1日わずか1ミリほど。芯の役割をする数ミリ大のグラニュー糖から、コンペイトウが完成するまでには10日~2週間がかかるという。
◆職人技で24個
こうしてコンペイトウが大きくなる過程でツノが生えてくるというが、いったいどうやって…。工場の職人によると、蜜がかかった粒がぶつかり合うことで、1粒に約50個の小さな突起ができる。さらに蜜がかかるとツノは太く長くなるものと、消えていくものに二分される。不思議なことに、コンペイトウ1個につき、24個のツノができるという。
コンペイトウの最大の特徴であるツノをうまく隆起させるのはコンペイトウ職人の腕の見せどころ。季節や天候に応じた釜の角度の微調整や蜜をかけるタイミングができ映えに影響するという。
製造課長の藤野昌司さん(46)は「うまく調整ができているかは、蜜の乾き具合やコンペイトウの転がり具合でわかります」と話す。
◆南蛮文化が原点
本社工場には、コンペイトウの歴史を学んだり、“マイ・コンペイトウ”を作る「コンペイトウミュージアムやお」が併設されている。
そこに登場するのは怪しげな南蛮人。フロイス野村と称するこの人、実は大阪糖菓の野村卓社長だ。見学者の前にふらっと現れてコンペイトウの知識を解説したり、ギターで南蛮音楽を披露したりするのだが、どうして南蛮人なのか。
社長によると、コンペイトウは16世紀にポルトガル人宣教師のルイス・フロイスによって日本に持ち込まれたという。江戸時代に長崎の町人が国産化、明治に大阪で量産化が始まり、古き良き昭和には駄菓子屋に並んだ。しかしいまは、チョコレートやスナック菓子におされっぱなし。
「このままではコンペイトウはなくなってしまう」
そんな社長の危機的な思いもあって、直径1ミリなのにちゃんとツノがある世界一小っちゃなものや、伝来当時の味を再現した「信長の金平糖」などのアイデアを次々と商品化。コンペイトウの新たな魅力を発信している。
【会社概要】大阪糖菓
大阪府八尾市若林町2の88。昭和15年創業。コンペイトウづくりの体験工房「コンペイトウミュージアムやお」が工場に併設され、平日は工場見学も可能。10人以上からで料金は千円。堺市の同社堺工場の体験工房は3人以上からで800円。いずれも事前予約((電)072・948・1339)が必要。
出来上がるまで10日から2週間もかかるとは驚きです。
ふdsん何気なく食べているお菓子にも職人技が生かされているものがあることは驚きます。
☟クリックしていただけると嬉しいです。