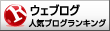つ
つ
『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出書房新社)は、ホモ・サピエンスの誕生前からホモ・サピエンス後の予想まで、超長期の歴史のマクロな流れをユニークな視点で辿っている。
下巻は宗教に関する論考で始まる。アニミズム、多神教、二元論、一神教を比較した後で、「神への無関心を特徴」とし「自然法則を重んじる」宗教というカテゴリーを提示し、その代表として仏教を考察している。
著者はこう書いている。(曽我の要約)
苦は、神の気まぐれによって生じるのではなく、自分の中の渇愛から生じると、ゴータマ(釈尊)は悟った。快を経験すればさらにそれを渇愛し、不快を経験すればその除去を渇愛する。渇愛は常に不満足をもたらし、心を不安定にする。これは、仏教徒にとって、神からの啓示ではなく、普遍的な自然の法則である。渇愛せずに現実をあるがままに受け入れるために、「何を経験していたいか」ではなく「今何を経験しているか」に注意を向ける鍛錬、瞑想術を開発した。渇愛を消火すれば、完全な満足と平穏の涅槃が訪れる。
今後さらに遺伝子操作やクローン技術が開発、応用され、様々なデバイスが人体に組み込まれ、寿命という概念がなくなり、人々の脳がデジタル技術でネットワーク化されるなど、科学技術が進展していけば、単純にバラ色の未来が開けるのではなく、逆に、現代社会の基礎にある様々な共通の理念が、深刻な動揺に見舞われることになるだろう。そう著者は推察する。人権、平等、格差、差別、責任、死すべき有限な存在としての自己認識、アイデンティティ、共同体など、根本的な常識が揺らぎ、法制度の混乱や倫理上の論争に陥りかねない。
さらには、増殖、進化するようにゼロから設計されたDNAの研究も始まっているし、学習し進化、増殖するコンピュータ・プログラムやウィルスが、ネットワーク・システムとして新たな「生命」となり、ホモ・サピエンスを超え頂点に立つかもしれない。
科学技術の発展、応用が、予想しない深刻な結果を招きかねないのに、有効な対応ができないのは、なんであれ、我々は、なにができるかだけではしゃいでしまい、なんのためにそれを行うのか、それが何をもたらすのか、それはよいことなのか、深く考えないまま取り掛かるからだ。そういった判断の基準を持っていないのである。新たな科学技術が開発されれば、例えば遺伝子組み換え作物に見られるように、目先の効能で一儲けしようという資本主義の思惑がすぐさま走り出す。
科学技術が指数関数的に猛スピードで発展し、世界を造り変える大きな力を発揮する中で、深く考えた判断基準のないまま、副作用を軽視して、「渇愛」(私の普段の言い方なら、執着)で目先の利得を競い合って追い求めるのは、たいへん恐ろしいことだ。
著者も、ひとつ前の章で「文明は人類を幸福にしたのか」と問うている。科学技術のみならず、人類の文明そのものが、一貫して執着に駆動されてきたのであって、真の幸せについて問うことのないまま、ここまで来てしまった。
そう考えると、執着の無益さ、愚かさに気づき、苦の生産を停止する術を説いてくれた釈尊の教えは、今再び学び直すべき価値がある。これはまさしくこのサイトのテーマであるが、改めてそう思った。