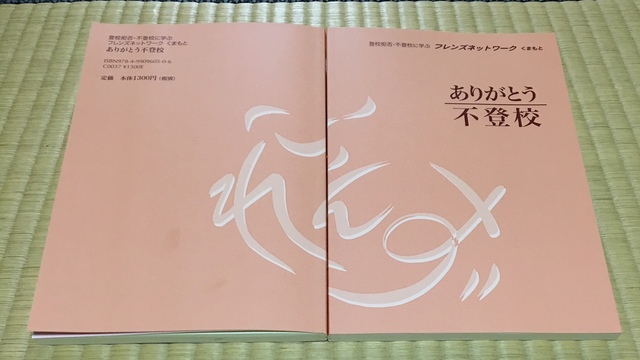10年前の会報より
フレンズ親の会 報告
第119回 フレンズ親の会 09年7月11日 13:30-16:30 パレア10F和室
参加者16名 (初参加者3名)
今回は会場が空いてなくて初めて使用するパレア10階の和室でした。40畳に板の間と大鏡のついた踊りでもできそうな部屋で、会場費もちょっと高めでした。産文会館が建て替えとかで4月より使えなくなり、とても不便になりました。しかし今年の冬より大江の交通局跡にできたウェルパルが使えるようになったそうです。
今回は梅雨のさなか、皆さん傘をさしておいでいただきました。
・・・一部省略・・・
3 “キレた”時の子どもの気持ちは?
D母:息子は一人息子で何でも出来る子だったので親の期待が大きくて、特に主人は完璧主義者で子どもに厳しかったですね。母親は一流の大学にやって一流のコ-スに乗せようと、小学校のときは塾漬けでしたから可愛そうなことをしましたよ。中2で不登校になったとき親も受け入れられず、してはいけないことや間違ったことを何でもしました。当時は家庭内暴力で大変でした。優等生の姉がいまして、その姉に対する嫌がらせをしていました。年度始めに母親が息子の教科書をそろえます。そのとき姉が「お母さんが苦労して準備してくれているのに何で教科書を開かないの」と言いました。息子はそれまで姉は自分の味方だと思っていましたから、その言葉に腹を立て教科書を破ってしまい、姉の部屋のガラスを割りベッドの上をガラスだらけにしました。それから自分の部屋に引きこもってしまいました。食事にも出てこないので、息子のご飯はドアの前に置いていました。夜みんなが寝てしまってから食べていたようです。
いろいろありましたが今思うと懐かしい思い出です。本人も「人間落ちるときは徹底して落ちたがいい」と言っています。家族のほうも、そういう地獄のような暮らしがあったから県外にいる子どもたちともつながりが強くなったと思っています。
C母:うちは真っ只中にいるので台風がいつ去るかと耐えています。気分に波があって娘は溜めるほうだから、爆発したらもう大変です。いつの間にか壁に穴が開いていたりします。そのときのことは覚えていないと言います。息子さんが窓を割った時はどういう気持ちなのでしょうか。溜ったものを発散するのですか?
D母:そうですね、うちの子も頭が真っ白になると言っていました。目はつり上って顔つきが変るんですよ。そんな時「アーっそんなことしてダメでしょう」と言ったり、親が怖がったり脅えたりすると子どもは不安になるんでしょうね。さらにひどくなりました。息子は父親に刃物を向けたこともあったんですよ。父親に対する最後の反抗手段だったのでしょうね。一歩間違えば新聞沙汰でした。父親は逃げずに息子の前に立ちはだかったんですよ。父親が逃げなかったから息子は変ったと思います。今では息子は「オヤジを尊敬している」と言います。