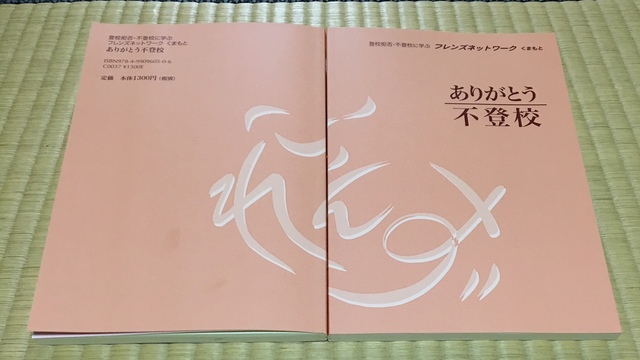会報から
お便りコーナー
「不登校」と向き直しの機会に
石井嘉寿絵
今回、大勢の人の前で40分話すという大仕事を、代表のスケジュールが合わないということで引き受けたのですが、結果はどうであれ、私にとっては間違いなくいい経験になりました。
不登校について語るということで、先入観をなるべく取っ払って「不登校」と向き合ってみようと思い、我が子が休み始めた時からを振り返る作業をしました。
そのなかで、息子が26才の時に書いてくれた手記を読み直してみたのですが、当時受け取ったものとは少し違うものを感じました。書かれている文字が変化しているなんてことは全くないわけですが、私は自分の想いに引き寄せて読みとっていたようです。息子の言いたいことをしっかり受け取れていなかったと反省しました。
彼の文章は少しくどいほどに熱く綴られ、その中に怒りや、悲しみや、学びたいという情熱がにじみ出ているのです。推こうしてもっと整理し、読みやすくした方がいいと思える所もありますが、そうしてしまうと、この溢れる想いが薄まるのではないかと感じるほどです。当時(不登校になって16年後)の彼の想いをかみしめる機会になりました。
人の想いをそのまま受け取ることは、とても難しいことだと改めて感じ、そのことが今回一番の収穫だったと思っています。その手記が載っているのは「届け!!文科省まで」という私が友人と自費出版した本ですが、その一部を引用して話を進めました。その中から一部をここに紹介します。息子は「学校教育」について次のように書いています。
その時の社会や情報も、受験に過熱する学歴社会を批判し、これからは手に職をもち個性を大切にすることが大切だという空気を子どもの私でも感じられた。学校の先生も同じようなことを口にしていた。だが実際はどうだ。先生が黒板の前で繰り返すことは、黒板に書くことをただノートに書き写させ、テストに出てきそうなキーワードに赤線をつけ覚えさせるだけのテストのための勉強(すべての先生がそうとは言わないが)、子ども一人一人の個性や好きな事を重要視しているとは到底思えないカリキュラム。特に受験と関係のない美術などの創作系の課目は学校によっては減らす、またはなくしてしまうことも珍しくないことだった。そんな矛盾だらけの教育の現場に、自分が最も成長する大切な時間の大半をゆだねるほどの価値をみつけられるはずもない。
学校に行く価値がないと判断すると、頭よりも先に体が反応(適応)し学校に行くために朝早く起きるということを体が勝手にやめる。私はそのようにして、頭と体両方が自然と「学校へ行く」という選択をしなくなった。
そしてこうも書いています。
「学校に行かないと生きていくために困る」ではなく、「学校に行くと生きていく力が奪われる」そんな感覚だった。と書いています。
「学校に行くと生きていく力が奪われる」と感じるのは息子ばかりではないと思います。こんなふうに感じさせてしまう現状を少しでも良くしたいと「不登校」に関わってきたつもりですけど、今回の「代理の講演」を機に、改めて謙虚に向き直していこうと思いました。