中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
与えることの難しさ(田中貴.com)
与えることの難しさ(田中貴.com)
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
コメント ( 0 )
過去問の結果を記録する
過去問の勉強は、その学校の出題傾向を知ることを目的としています。学校によってやはり出題傾向というのは、はっきりしている場合が多く、その特徴をつかんでおくことは有効な対策です。最近は各塾でも学校別対策に力をいれています。ただ、過去問は自宅でやる塾が多いのも事実。したがって、その記録をしっかりとっておきましょう。
今回も使うのはスプレッドシートです。
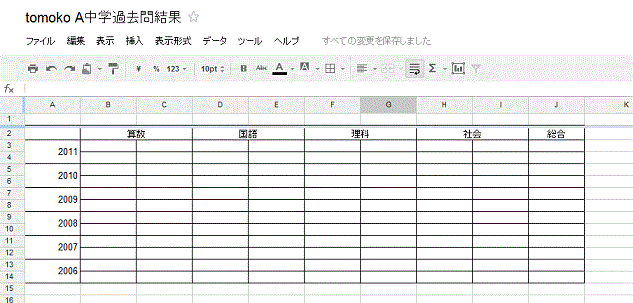
夏休みからであれば、各科目で3つ欄が必要になりますが、今回は2つにしてあります。受験前、あと2回できればいい方かもしれません。上の段が日付、下の段が点数です。あるいは正解率でもいいかもしれません。
夏休み中の過去問の勉強は、どちらかといえば解法を理解することが中心になります。時間をかけても、なかなかできない問題があるでしょう。この時期はまだ、一通りカリキュラムが終わったばかりですから、むしろできないのが当たり前だと思っていただいてかまいません。だから、しっかり解答を読んで、解き方を理解することが大事です。特に算数は、解き方が複数組み合わさっていますから、それをしっかり分解して理解する必要があります。応用問題というのは、大体が3つから4つの要素が組み合わさってできています。問題はその構造をグラフや図を書いたり、例を書き上げてみたりしながらつかんでいかなければならないのです。ですから、夏の間は解き明かすというよりは、理解するということに力をいれていってください。
そして、この勉強がしっかりできると秋以降に過去問をやるとき、力になります。もちろん2回目では、まだ勉強が不十分ですから、全部できるところまではなかなかいきません。できないところは、相変わらずできないということもあるかもしれません。しかし、それをがっかりしてもいけないのです。今回は時間をはかっていますから、決められた時間の中で、何とかしなければならないのです。「確か、こうだった」「こうやったはずなんだけど」失敗はあると思いますが、その失敗から学ぶことが多いのです。
お父さん、お母さんが子どもの答案を採点してみると、こんなことにぶつかるかもしれません。間違えた問題をやり直させてみると、次はできるのです。間違いの原因は、計算間違いだったり、問題の読み違いだったり。あるいは自分の書いた数字を読み違えて、答えがでなくなったりすることがあるのです。
なぜ、こんなことを間違えるのか、腹が立つかもしれません。しかし、それが一般的な話だということを覚えておいてください。時間を計り始めると、まず間違いなくこのような症状が起こってきます。だからこそ、その対策を考えなければならないのです。
例えば、算数について私が子どもたちによく言っていたのは次の3つです。
1) 式を書いて、答えが出たらその数字が何を意味するのかメモすること。
2) 検算はその場ですること。
3) 答えが出たと思ったら、もう一度問題を読み直すこと。
その他、問題文の数字が書いてあるところに下線をひく、数字をつかったら、その横にチェックマークをいれるなど、細かい注意をいれるとまだまだありますが、上の3つだけでもかなりミスは減ります。特に2)はその場ですることによって、自分がどこまでもどればよいのか、考えられます。
よく子どもたちがやるのは、間違えたとわかるとすべてを消してしまうことです。これではいくら時間があっても間に合いません。間違えたと思ったとき、いったいどこまでもどらなければならないのかを考えるのです。すぐ消しゴムをだして消すのではなく、もう一度見直してみることの方が大事です。
このような注意は、問題をやるにつれて適宜、出してあげるとよいでしょう。注意事項という文書をgoogle documentsに作っておくと、子どもに適切なアドバイスを与えることができます。
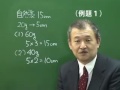
「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
今回も使うのはスプレッドシートです。
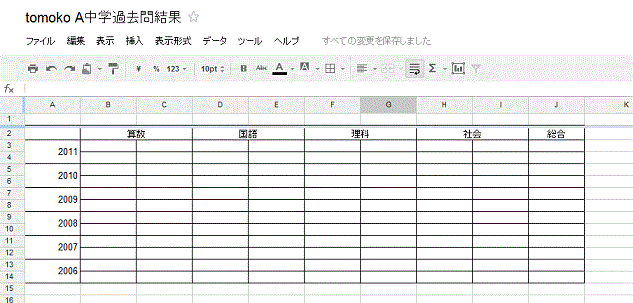
夏休みからであれば、各科目で3つ欄が必要になりますが、今回は2つにしてあります。受験前、あと2回できればいい方かもしれません。上の段が日付、下の段が点数です。あるいは正解率でもいいかもしれません。
夏休み中の過去問の勉強は、どちらかといえば解法を理解することが中心になります。時間をかけても、なかなかできない問題があるでしょう。この時期はまだ、一通りカリキュラムが終わったばかりですから、むしろできないのが当たり前だと思っていただいてかまいません。だから、しっかり解答を読んで、解き方を理解することが大事です。特に算数は、解き方が複数組み合わさっていますから、それをしっかり分解して理解する必要があります。応用問題というのは、大体が3つから4つの要素が組み合わさってできています。問題はその構造をグラフや図を書いたり、例を書き上げてみたりしながらつかんでいかなければならないのです。ですから、夏の間は解き明かすというよりは、理解するということに力をいれていってください。
そして、この勉強がしっかりできると秋以降に過去問をやるとき、力になります。もちろん2回目では、まだ勉強が不十分ですから、全部できるところまではなかなかいきません。できないところは、相変わらずできないということもあるかもしれません。しかし、それをがっかりしてもいけないのです。今回は時間をはかっていますから、決められた時間の中で、何とかしなければならないのです。「確か、こうだった」「こうやったはずなんだけど」失敗はあると思いますが、その失敗から学ぶことが多いのです。
お父さん、お母さんが子どもの答案を採点してみると、こんなことにぶつかるかもしれません。間違えた問題をやり直させてみると、次はできるのです。間違いの原因は、計算間違いだったり、問題の読み違いだったり。あるいは自分の書いた数字を読み違えて、答えがでなくなったりすることがあるのです。
なぜ、こんなことを間違えるのか、腹が立つかもしれません。しかし、それが一般的な話だということを覚えておいてください。時間を計り始めると、まず間違いなくこのような症状が起こってきます。だからこそ、その対策を考えなければならないのです。
例えば、算数について私が子どもたちによく言っていたのは次の3つです。
1) 式を書いて、答えが出たらその数字が何を意味するのかメモすること。
2) 検算はその場ですること。
3) 答えが出たと思ったら、もう一度問題を読み直すこと。
その他、問題文の数字が書いてあるところに下線をひく、数字をつかったら、その横にチェックマークをいれるなど、細かい注意をいれるとまだまだありますが、上の3つだけでもかなりミスは減ります。特に2)はその場ですることによって、自分がどこまでもどればよいのか、考えられます。
よく子どもたちがやるのは、間違えたとわかるとすべてを消してしまうことです。これではいくら時間があっても間に合いません。間違えたと思ったとき、いったいどこまでもどらなければならないのかを考えるのです。すぐ消しゴムをだして消すのではなく、もう一度見直してみることの方が大事です。
このような注意は、問題をやるにつれて適宜、出してあげるとよいでしょう。注意事項という文書をgoogle documentsに作っておくと、子どもに適切なアドバイスを与えることができます。
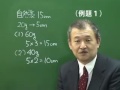
「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
 | 親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート |
| クリエーター情報なし | |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン |
コメント ( 0 )





