中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
データから考えるべきこと
中学入試はいわゆる独自入試です。
独自入試というのは、その学校ごとで問題の内容が違う、ということです。当たり前のようですが、例えば高校受験の場合、公立高校は一斉入試で、問題はどこでもいっしょというところが多いので、学校別の対策というのはそれほど重要ではありません。
しかし中学受験は各校の問題が違います。そして問題を作るのは学校の先生ですし、問題は学校がどういう子をほしいかということで決まってくるので、それなりに学校別の傾向がはっきりしています。
例えば中学に入ってレポートの多い学校があります。こういう学校に入ってものを書くことができない、と本当につらくなる。だから入試の段階で国語にとどまらず、社会や理科でも記述の問題を出す。理科の生物を出す学校というのは、中学に進んでその観察が多い、など、やはり理由あってのことなのです。
逆に記号式が多いところは、受験人員が多い、という事情があります。例えば2日以降で受験人員が多くなると、すぐに結論を出すためには、なるべく採点に時間のかかからないようにしたい。コンピューターで採点をする、というところもあるでしょう。大学付属などは、大学入試のためにそういうシステムを持っているので、利用させてもらっている学校もあるようです。
で、これだけ明確に傾向が出ているのだから、それを研究しない手はない。
しかも、東京、神奈川の入試解禁日は2月1日で、2月3日までにおおよその学校の入試は終わってしまいます。ということは受けられる学校は午後入試を含めても限られます。そのうち、絶対入るという滑り止めを考えると、対策をしなければいけない学校はわずか。
条件が整っているのです。だから中学入試は他の入試に比べて、学校別対策をする意味が非常に大きいのです。
子どもが過去問をやっているときに、その横で、どんな問題がでているのか、傾向はどうなのか、保護者のみなさんも研究してみてください。
例えば過去10年で見てみると、傾向は実にはっきりしていることに気がつくと思います。
多くの学校で言えば、だいたい長文が2題、と漢字の書き取りでしょう。文章はひとつが物語。ひとつが随筆か説明文。記述の割合が多い、少ないは学校によってさまざまですが、だいたい形が決まっているはずです。
そして学校にはある理由があるから出題傾向が決まってくるので、それはそう頻繁に変わることはない。大きく変わる場合は必ず説明会で事前の説明があるはずです。
それがない以上、大きな変更はないと見ていい。となれば、今の子どもの実力から考えて何をやればいいのか、自然、見えてくるものなのです。
例えば算数の出題。大問が6題と決まっていたら、そのうちどの問題がどのくらいのレベルなのかを調べていくと、だいたい子どもの課題というのが見えてくるでしょう。
4題までは比較的取れていれば、あと1題解けるかどうかが問題になりますが、その4題でミスが多ければそれに関する対策をしないといけないことになります。またジャンルによって、速さの問題が良く出ているが、なかなかそれができないということになれば、そこに対策の中心を持っていく必要がでてくるわけです。
それを考えず、ただひたすら塾の課題だけに応じていても、実際は遠回りをする可能性が出てきます。
受ける学校の傾向は親がまずしっかり研究し、子どものデータと比べてみて、残りの時間の課題を整理すべきでしょう。それをやるとやらないとでは、結果に大きな違いがでます。
中学受験が親と子の受験だ、といわれるのは実はこういうところにあるのです。高校受験であれば、子どもがそういうことを考えられるようになってきますが、小学生ではまだそこまで行かない。だから親の出番があるわけです。
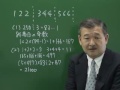
「映像教材、これでわかる数の問題」(田中貴)
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
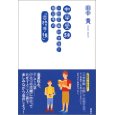 中学受験、これで成功する!母と子の合格手帳(講談社)
中学受験、これで成功する!母と子の合格手帳(講談社)
独自入試というのは、その学校ごとで問題の内容が違う、ということです。当たり前のようですが、例えば高校受験の場合、公立高校は一斉入試で、問題はどこでもいっしょというところが多いので、学校別の対策というのはそれほど重要ではありません。
しかし中学受験は各校の問題が違います。そして問題を作るのは学校の先生ですし、問題は学校がどういう子をほしいかということで決まってくるので、それなりに学校別の傾向がはっきりしています。
例えば中学に入ってレポートの多い学校があります。こういう学校に入ってものを書くことができない、と本当につらくなる。だから入試の段階で国語にとどまらず、社会や理科でも記述の問題を出す。理科の生物を出す学校というのは、中学に進んでその観察が多い、など、やはり理由あってのことなのです。
逆に記号式が多いところは、受験人員が多い、という事情があります。例えば2日以降で受験人員が多くなると、すぐに結論を出すためには、なるべく採点に時間のかかからないようにしたい。コンピューターで採点をする、というところもあるでしょう。大学付属などは、大学入試のためにそういうシステムを持っているので、利用させてもらっている学校もあるようです。
で、これだけ明確に傾向が出ているのだから、それを研究しない手はない。
しかも、東京、神奈川の入試解禁日は2月1日で、2月3日までにおおよその学校の入試は終わってしまいます。ということは受けられる学校は午後入試を含めても限られます。そのうち、絶対入るという滑り止めを考えると、対策をしなければいけない学校はわずか。
条件が整っているのです。だから中学入試は他の入試に比べて、学校別対策をする意味が非常に大きいのです。
子どもが過去問をやっているときに、その横で、どんな問題がでているのか、傾向はどうなのか、保護者のみなさんも研究してみてください。
例えば過去10年で見てみると、傾向は実にはっきりしていることに気がつくと思います。
多くの学校で言えば、だいたい長文が2題、と漢字の書き取りでしょう。文章はひとつが物語。ひとつが随筆か説明文。記述の割合が多い、少ないは学校によってさまざまですが、だいたい形が決まっているはずです。
そして学校にはある理由があるから出題傾向が決まってくるので、それはそう頻繁に変わることはない。大きく変わる場合は必ず説明会で事前の説明があるはずです。
それがない以上、大きな変更はないと見ていい。となれば、今の子どもの実力から考えて何をやればいいのか、自然、見えてくるものなのです。
例えば算数の出題。大問が6題と決まっていたら、そのうちどの問題がどのくらいのレベルなのかを調べていくと、だいたい子どもの課題というのが見えてくるでしょう。
4題までは比較的取れていれば、あと1題解けるかどうかが問題になりますが、その4題でミスが多ければそれに関する対策をしないといけないことになります。またジャンルによって、速さの問題が良く出ているが、なかなかそれができないということになれば、そこに対策の中心を持っていく必要がでてくるわけです。
それを考えず、ただひたすら塾の課題だけに応じていても、実際は遠回りをする可能性が出てきます。
受ける学校の傾向は親がまずしっかり研究し、子どものデータと比べてみて、残りの時間の課題を整理すべきでしょう。それをやるとやらないとでは、結果に大きな違いがでます。
中学受験が親と子の受験だ、といわれるのは実はこういうところにあるのです。高校受験であれば、子どもがそういうことを考えられるようになってきますが、小学生ではまだそこまで行かない。だから親の出番があるわけです。
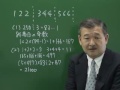
「映像教材、これでわかる数の問題」(田中貴)
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
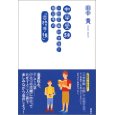 中学受験、これで成功する!母と子の合格手帳(講談社)
中学受験、これで成功する!母と子の合格手帳(講談社)コメント ( 0 )




