中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
学校説明会・文化祭のポイント
2学期にはいると各校で学校説明会が行われます。同じ日程、時間にかなりの数の学校が重なります。予定をしっかりたてておかないと、つい行きそびれるということがあるかもしれません。しっかりスケジュールを書き込んで、準備しましょう。念のため、ホームページで確認したり、学校に電話で問い合わせてください。
学校説明会は近年、非常に多様化してきました。校長先生が説明するだけではなく、授業見学会があったり、クラブ活動を紹介してくれたり、子どもたちが学校を経験できるオープンキャンパスのような企画もあります。
これらの説明会はぜひ出かけて、情報を集めてください。
まず聞いておかなければならないことは、学校のトップの話です。学校の責任者がどういう目標をおいて、学校運営をしているのかは、よく聞いておかなければなりません。
私学というのは、特別な教育目標があってできた学校です。その目的にしたがって寄付行為が起きて、設立されるのです。その中心は宗教法人、企業、個人などいろいろです。一般に宗教法人はわかりやすいと思います。キリスト教系でもカソリック系、プロテスタント系など背景となる宗教法人はいろいろです。
ただ、これらの宗教法人による学校は、信教を強制することはまったくありません。もちろん、布教の目的はありますから、たとえば聖書の時間とか座禅の時間とか、あるところもあります。ただ、だからといって信者でなければ受け入れないということは一切ありません。
問題は、その学校がいったい何をやろうとしているのかということをしっかりつかむということが大事です。よく、学校を訪問して、いろいろなお話を伺うのですが、宗教法人がバックグラウンドにある学校は育てたいという人間観がしっかりしていることが多いようです。これはある意味、宗教法人だからこそという面もあるかもしれません。
一方、宗教とは一切関係がない学校法人もあります。企業が学校法人を作った場合は、どちらかといえば、人材の育成に力点があります。国際的な視野を持つとか、自由な想像力を持つとか、それぞれの企業が考える人材像があります。
これらの話がしっかり出てくる学校は信頼がおけます。それが自分の子に合うか、合わないかという問題はありますが、少なくとも判断ができる話をしてくださることは大変ありがたいことです。
ただ、最近は大学の合格実績の話をする学校が増えてきました。もちろん出口がどうなるのか、当然気になるところではありますが、そればかりというのも魅力がありません。これから公立の中高一貫校が出てきます。当然、公立という制約はあるものの、新しく生まれてくるわけですから、それなりの特徴をかねそなえてくるはずです。これからの少子化の時代では、学校は自分の特徴をアピールできなければ、生き残れません。その意味で大学の合格実績が魅力にはなりません。当然のことながら、優秀な子供たちが集まった学校は特に何をしなくても、進学実績は良いのです。それにそういう学校がある年、実績が悪くても、次の年は浪人が合格するので、実績が戻りますから、その増減に気を使う必要も本当はありません。 よく春に東大の合格実績が良いと、その次の年の入試が難しくなるという風潮がありましたが、私は、あまり意味のないことだと思っています。
学校というのは、それだけではないのです。もちろん勉強の指導も大事ですが、いろいろな可能性を開いてくれるかどうかが大事なのです。
その意味では文化祭も非常に役に立ちます。
子どもたちがある意味自由に作っている文化祭は、明らかに活気があります。活気があるということは、子どもたちの想像力が引き出されているということです。演劇があったり、いろいろなイベントがあったり、ごらんになるとよくおわかりになると思います。
男子御三家の文化祭に行ってみると、まあ、よくここまでごたごたしているなとあきれる一方で、やはり大きなエネルギーを感じます。何か、やりたいことを思いっきりやろうという子どもたちの意思があるのです。子どもたちは当然、誰しもがそういうものを持っているのですが、それが引き出されるかどうかは、やはり学校の環境だと思います。見比べてみると、それぞれ校風の違いがはっきりします。整然と行われているのは、やはり学校側のおさえが利いている学校。管理型といっても良いかもしれません。逆にがちゃがちゃしているのは、子どもたちの意思を割と尊重する学校であることが多く、子どもたちが楽しそうにやっています。
同じことは体育祭や運動会にも言えます。開成の運動会は有名ですが、男子校の荒っぽさがいい意味で出ています。
文化祭はぜひ子どもといっしょにでかけてください。子どもたちは文化祭に行けば、自分の興味に合った展示物を見たいものです。将棋が好きな子は、将棋部で将棋をさしたいでしょうし、サッカーの好きな子はやはり試合を見たいでしょう。これはこれで大事な視点です。小学校6年生にもなれば、自分の好きな分野はある程度あります。もちろんそれがずーっと続くのかどうかはわかりません。しかし、自分の好きなクラブや同好会があるだけで、その学校に入りたいという動機付けがでてくるでしょう。
一方で、お母さんが見ておかなければいけないのはその学校の生徒の様子です。ただここで見ておかなければならないのは、躾が行き届いているとか、身だしなみがいいとかいうことではなく、お子さんに合うだろうかという点です。 お子さんが本当に楽しんで通えるかどうかは、非常に重要です。
活発な子どもの場合は、やはり放任型の方が学校生活は楽しいに決まっています。その分、どこでブレーキがかかるのかは親として心配なところ。だから学校の先生方が子どもたちにどう関わっているのかしっかり見届けておかなければなりません。放任型にも2つタイプがあって、学校の先生がまったく無関心である場合と、しっかり目を配りながらしかし、子どもたちの意思を尊重する場合があります。当然、親としては後者の方が安心です。ですから、文化祭の中で先生方がどう動いているのかを見てみると、その学校のカラーがはっきりすると思います。
おとなしい子どもの場合、人数が多く、自由放任の学校だと埋もれてしまうことが多く、その子の可能性を引き出すチャンスが少なくなる可能性があります。したがって、そういうタイプの子どもたちが、どんな役割を文化祭で担っているのか見ておくと、とても参考になります。なんとなく晩成(おくて)だなと思われるタイプの子でもいきいき活動していれば、それなりにケアが行われているのでしょうし、そうでなければ、やはりお子さんには合わないかもしれません。
文化祭は、お子さんがこの学校にきたら、どんなことをするだろうか?ということを考えながら、ごらんになってください。きっとあの子のようになるだろうなというイメージがわいて、それがとても素敵に思えたら、その学校は多分お子さんには合う学校だろうと思います。お母さんのそういうイメージはとても大切ですから、ぜひしっかりご覧いただきたいと思います。
お帰りになったところで、もう一度整理してみましょう。そして、学校別にデータをまとめながら感じたことをメモしていかれると良いでしょう。
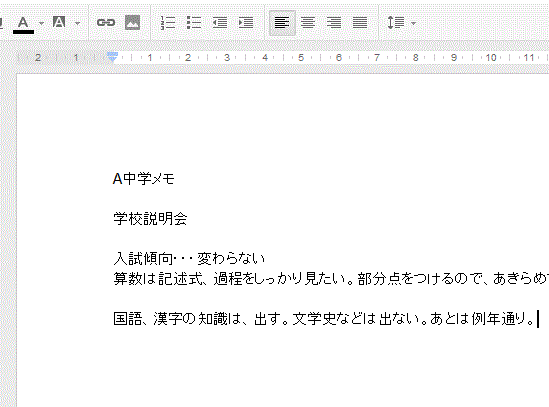
これは学校情報とともに時系列で書かれていくと良いと思います。説明会、文化祭、普段の日、だんだんその学校との付き合いが増えていくにつれて、いろいろな点が見えてきます。そのデータの中から、やはり子どもに合うという学校を選んであげてください。
学校説明会は近年、非常に多様化してきました。校長先生が説明するだけではなく、授業見学会があったり、クラブ活動を紹介してくれたり、子どもたちが学校を経験できるオープンキャンパスのような企画もあります。
これらの説明会はぜひ出かけて、情報を集めてください。
まず聞いておかなければならないことは、学校のトップの話です。学校の責任者がどういう目標をおいて、学校運営をしているのかは、よく聞いておかなければなりません。
私学というのは、特別な教育目標があってできた学校です。その目的にしたがって寄付行為が起きて、設立されるのです。その中心は宗教法人、企業、個人などいろいろです。一般に宗教法人はわかりやすいと思います。キリスト教系でもカソリック系、プロテスタント系など背景となる宗教法人はいろいろです。
ただ、これらの宗教法人による学校は、信教を強制することはまったくありません。もちろん、布教の目的はありますから、たとえば聖書の時間とか座禅の時間とか、あるところもあります。ただ、だからといって信者でなければ受け入れないということは一切ありません。
問題は、その学校がいったい何をやろうとしているのかということをしっかりつかむということが大事です。よく、学校を訪問して、いろいろなお話を伺うのですが、宗教法人がバックグラウンドにある学校は育てたいという人間観がしっかりしていることが多いようです。これはある意味、宗教法人だからこそという面もあるかもしれません。
一方、宗教とは一切関係がない学校法人もあります。企業が学校法人を作った場合は、どちらかといえば、人材の育成に力点があります。国際的な視野を持つとか、自由な想像力を持つとか、それぞれの企業が考える人材像があります。
これらの話がしっかり出てくる学校は信頼がおけます。それが自分の子に合うか、合わないかという問題はありますが、少なくとも判断ができる話をしてくださることは大変ありがたいことです。
ただ、最近は大学の合格実績の話をする学校が増えてきました。もちろん出口がどうなるのか、当然気になるところではありますが、そればかりというのも魅力がありません。これから公立の中高一貫校が出てきます。当然、公立という制約はあるものの、新しく生まれてくるわけですから、それなりの特徴をかねそなえてくるはずです。これからの少子化の時代では、学校は自分の特徴をアピールできなければ、生き残れません。その意味で大学の合格実績が魅力にはなりません。当然のことながら、優秀な子供たちが集まった学校は特に何をしなくても、進学実績は良いのです。それにそういう学校がある年、実績が悪くても、次の年は浪人が合格するので、実績が戻りますから、その増減に気を使う必要も本当はありません。 よく春に東大の合格実績が良いと、その次の年の入試が難しくなるという風潮がありましたが、私は、あまり意味のないことだと思っています。
学校というのは、それだけではないのです。もちろん勉強の指導も大事ですが、いろいろな可能性を開いてくれるかどうかが大事なのです。
その意味では文化祭も非常に役に立ちます。
子どもたちがある意味自由に作っている文化祭は、明らかに活気があります。活気があるということは、子どもたちの想像力が引き出されているということです。演劇があったり、いろいろなイベントがあったり、ごらんになるとよくおわかりになると思います。
男子御三家の文化祭に行ってみると、まあ、よくここまでごたごたしているなとあきれる一方で、やはり大きなエネルギーを感じます。何か、やりたいことを思いっきりやろうという子どもたちの意思があるのです。子どもたちは当然、誰しもがそういうものを持っているのですが、それが引き出されるかどうかは、やはり学校の環境だと思います。見比べてみると、それぞれ校風の違いがはっきりします。整然と行われているのは、やはり学校側のおさえが利いている学校。管理型といっても良いかもしれません。逆にがちゃがちゃしているのは、子どもたちの意思を割と尊重する学校であることが多く、子どもたちが楽しそうにやっています。
同じことは体育祭や運動会にも言えます。開成の運動会は有名ですが、男子校の荒っぽさがいい意味で出ています。
文化祭はぜひ子どもといっしょにでかけてください。子どもたちは文化祭に行けば、自分の興味に合った展示物を見たいものです。将棋が好きな子は、将棋部で将棋をさしたいでしょうし、サッカーの好きな子はやはり試合を見たいでしょう。これはこれで大事な視点です。小学校6年生にもなれば、自分の好きな分野はある程度あります。もちろんそれがずーっと続くのかどうかはわかりません。しかし、自分の好きなクラブや同好会があるだけで、その学校に入りたいという動機付けがでてくるでしょう。
一方で、お母さんが見ておかなければいけないのはその学校の生徒の様子です。ただここで見ておかなければならないのは、躾が行き届いているとか、身だしなみがいいとかいうことではなく、お子さんに合うだろうかという点です。 お子さんが本当に楽しんで通えるかどうかは、非常に重要です。
活発な子どもの場合は、やはり放任型の方が学校生活は楽しいに決まっています。その分、どこでブレーキがかかるのかは親として心配なところ。だから学校の先生方が子どもたちにどう関わっているのかしっかり見届けておかなければなりません。放任型にも2つタイプがあって、学校の先生がまったく無関心である場合と、しっかり目を配りながらしかし、子どもたちの意思を尊重する場合があります。当然、親としては後者の方が安心です。ですから、文化祭の中で先生方がどう動いているのかを見てみると、その学校のカラーがはっきりすると思います。
おとなしい子どもの場合、人数が多く、自由放任の学校だと埋もれてしまうことが多く、その子の可能性を引き出すチャンスが少なくなる可能性があります。したがって、そういうタイプの子どもたちが、どんな役割を文化祭で担っているのか見ておくと、とても参考になります。なんとなく晩成(おくて)だなと思われるタイプの子でもいきいき活動していれば、それなりにケアが行われているのでしょうし、そうでなければ、やはりお子さんには合わないかもしれません。
文化祭は、お子さんがこの学校にきたら、どんなことをするだろうか?ということを考えながら、ごらんになってください。きっとあの子のようになるだろうなというイメージがわいて、それがとても素敵に思えたら、その学校は多分お子さんには合う学校だろうと思います。お母さんのそういうイメージはとても大切ですから、ぜひしっかりご覧いただきたいと思います。
お帰りになったところで、もう一度整理してみましょう。そして、学校別にデータをまとめながら感じたことをメモしていかれると良いでしょう。
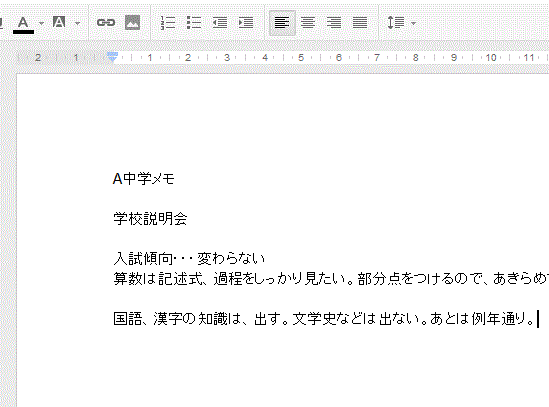
これは学校情報とともに時系列で書かれていくと良いと思います。説明会、文化祭、普段の日、だんだんその学校との付き合いが増えていくにつれて、いろいろな点が見えてきます。そのデータの中から、やはり子どもに合うという学校を選んであげてください。
コメント ( 0 )
与えることの難しさ(田中貴.com)
与えることの難しさ(田中貴.com)
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
コメント ( 0 )
過去問の結果を記録する
過去問の勉強は、その学校の出題傾向を知ることを目的としています。学校によってやはり出題傾向というのは、はっきりしている場合が多く、その特徴をつかんでおくことは有効な対策です。最近は各塾でも学校別対策に力をいれています。ただ、過去問は自宅でやる塾が多いのも事実。したがって、その記録をしっかりとっておきましょう。
今回も使うのはスプレッドシートです。
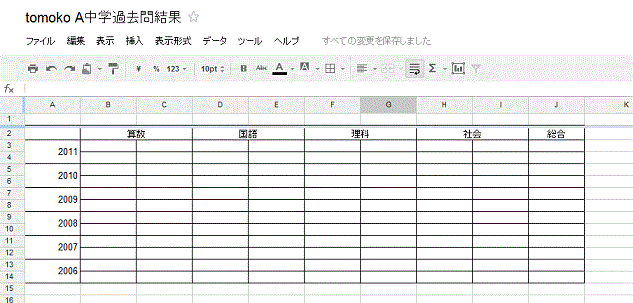
夏休みからであれば、各科目で3つ欄が必要になりますが、今回は2つにしてあります。受験前、あと2回できればいい方かもしれません。上の段が日付、下の段が点数です。あるいは正解率でもいいかもしれません。
夏休み中の過去問の勉強は、どちらかといえば解法を理解することが中心になります。時間をかけても、なかなかできない問題があるでしょう。この時期はまだ、一通りカリキュラムが終わったばかりですから、むしろできないのが当たり前だと思っていただいてかまいません。だから、しっかり解答を読んで、解き方を理解することが大事です。特に算数は、解き方が複数組み合わさっていますから、それをしっかり分解して理解する必要があります。応用問題というのは、大体が3つから4つの要素が組み合わさってできています。問題はその構造をグラフや図を書いたり、例を書き上げてみたりしながらつかんでいかなければならないのです。ですから、夏の間は解き明かすというよりは、理解するということに力をいれていってください。
そして、この勉強がしっかりできると秋以降に過去問をやるとき、力になります。もちろん2回目では、まだ勉強が不十分ですから、全部できるところまではなかなかいきません。できないところは、相変わらずできないということもあるかもしれません。しかし、それをがっかりしてもいけないのです。今回は時間をはかっていますから、決められた時間の中で、何とかしなければならないのです。「確か、こうだった」「こうやったはずなんだけど」失敗はあると思いますが、その失敗から学ぶことが多いのです。
お父さん、お母さんが子どもの答案を採点してみると、こんなことにぶつかるかもしれません。間違えた問題をやり直させてみると、次はできるのです。間違いの原因は、計算間違いだったり、問題の読み違いだったり。あるいは自分の書いた数字を読み違えて、答えがでなくなったりすることがあるのです。
なぜ、こんなことを間違えるのか、腹が立つかもしれません。しかし、それが一般的な話だということを覚えておいてください。時間を計り始めると、まず間違いなくこのような症状が起こってきます。だからこそ、その対策を考えなければならないのです。
例えば、算数について私が子どもたちによく言っていたのは次の3つです。
1) 式を書いて、答えが出たらその数字が何を意味するのかメモすること。
2) 検算はその場ですること。
3) 答えが出たと思ったら、もう一度問題を読み直すこと。
その他、問題文の数字が書いてあるところに下線をひく、数字をつかったら、その横にチェックマークをいれるなど、細かい注意をいれるとまだまだありますが、上の3つだけでもかなりミスは減ります。特に2)はその場ですることによって、自分がどこまでもどればよいのか、考えられます。
よく子どもたちがやるのは、間違えたとわかるとすべてを消してしまうことです。これではいくら時間があっても間に合いません。間違えたと思ったとき、いったいどこまでもどらなければならないのかを考えるのです。すぐ消しゴムをだして消すのではなく、もう一度見直してみることの方が大事です。
このような注意は、問題をやるにつれて適宜、出してあげるとよいでしょう。注意事項という文書をgoogle documentsに作っておくと、子どもに適切なアドバイスを与えることができます。
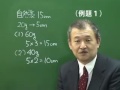
「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
今回も使うのはスプレッドシートです。
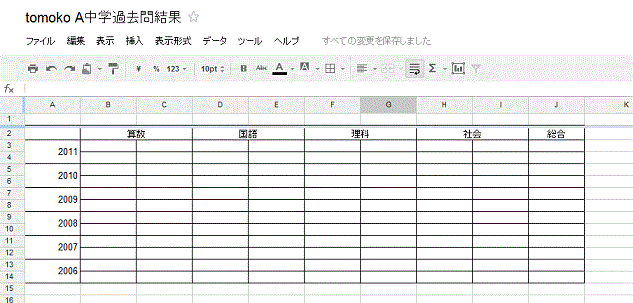
夏休みからであれば、各科目で3つ欄が必要になりますが、今回は2つにしてあります。受験前、あと2回できればいい方かもしれません。上の段が日付、下の段が点数です。あるいは正解率でもいいかもしれません。
夏休み中の過去問の勉強は、どちらかといえば解法を理解することが中心になります。時間をかけても、なかなかできない問題があるでしょう。この時期はまだ、一通りカリキュラムが終わったばかりですから、むしろできないのが当たり前だと思っていただいてかまいません。だから、しっかり解答を読んで、解き方を理解することが大事です。特に算数は、解き方が複数組み合わさっていますから、それをしっかり分解して理解する必要があります。応用問題というのは、大体が3つから4つの要素が組み合わさってできています。問題はその構造をグラフや図を書いたり、例を書き上げてみたりしながらつかんでいかなければならないのです。ですから、夏の間は解き明かすというよりは、理解するということに力をいれていってください。
そして、この勉強がしっかりできると秋以降に過去問をやるとき、力になります。もちろん2回目では、まだ勉強が不十分ですから、全部できるところまではなかなかいきません。できないところは、相変わらずできないということもあるかもしれません。しかし、それをがっかりしてもいけないのです。今回は時間をはかっていますから、決められた時間の中で、何とかしなければならないのです。「確か、こうだった」「こうやったはずなんだけど」失敗はあると思いますが、その失敗から学ぶことが多いのです。
お父さん、お母さんが子どもの答案を採点してみると、こんなことにぶつかるかもしれません。間違えた問題をやり直させてみると、次はできるのです。間違いの原因は、計算間違いだったり、問題の読み違いだったり。あるいは自分の書いた数字を読み違えて、答えがでなくなったりすることがあるのです。
なぜ、こんなことを間違えるのか、腹が立つかもしれません。しかし、それが一般的な話だということを覚えておいてください。時間を計り始めると、まず間違いなくこのような症状が起こってきます。だからこそ、その対策を考えなければならないのです。
例えば、算数について私が子どもたちによく言っていたのは次の3つです。
1) 式を書いて、答えが出たらその数字が何を意味するのかメモすること。
2) 検算はその場ですること。
3) 答えが出たと思ったら、もう一度問題を読み直すこと。
その他、問題文の数字が書いてあるところに下線をひく、数字をつかったら、その横にチェックマークをいれるなど、細かい注意をいれるとまだまだありますが、上の3つだけでもかなりミスは減ります。特に2)はその場ですることによって、自分がどこまでもどればよいのか、考えられます。
よく子どもたちがやるのは、間違えたとわかるとすべてを消してしまうことです。これではいくら時間があっても間に合いません。間違えたと思ったとき、いったいどこまでもどらなければならないのかを考えるのです。すぐ消しゴムをだして消すのではなく、もう一度見直してみることの方が大事です。
このような注意は、問題をやるにつれて適宜、出してあげるとよいでしょう。注意事項という文書をgoogle documentsに作っておくと、子どもに適切なアドバイスを与えることができます。
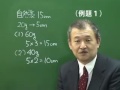
「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
 | 親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート |
| クリエーター情報なし | |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン |
コメント ( 0 )
「解法を覚える」では力がつかない
「解法を覚える」では力がつかない(田中貴.com)
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
コメント ( 0 )
子どもに試験結果のレポートを書かせる
今日は祝日ですから、6年生のみなさんは模擬試験に出かけているでしょう。
これが11月の最後の試験になるでしょうか。12月もありますが、そろそろ結果を見て、親はいろいろ考えを整理しなければなりませんね。
第一志望をどこにするか、受験校をどう並べるか、1月校はどこにするか、学校によっては内申や親の作文を出さないといけないところもありますから、早めに準備をしておかなければいけませんが。
さて、昨日、試験結果の整理を親がする話をしましたが、実際に親がやっても子どもがピンときていないとまったく意味がありません。なので、たとえば今日、試験が終わったら、試験の感覚があるうちに子どもにレポートをさせたらどうでしょうか。
うまくいった点
うまくいかなかった点
工夫すべきだと感じた点
以上3点をまとめておいて、本人が手書きをしたなら、それを写真なりスキャナーでとっておきましょう。(もちろん現物でもかまいませんが、私は最近、なんでもデジタルにしたがる傾向があります。パソコンの中になんでもしまっとこう、と思っているんですが。)
そして、復習。
これはすぐにやり直した方が良いでしょうね。そして、もう一度反省レポートを書いてみる。
そうすると、工夫すべき点がまた出てくるかもしれない。
親の分析とは別に子どもの分析を記録しておくと、実際に何を注意しなければいけないか、は明確になってきます。
先日、ある小学校受験の先生と話をしていました。実は小学校受験というのは、教える塾側が型にはまってしまっていて、実際に入学試験に出ないことまでさせられてしまうのが多いんだそうです。
時間は短いので、出ないこと、あるいはできていることに時間を費やす必要はありません。
試験には出て、ここでしっかり変えられることに集中する必要があるのです。
例えば来月までに絶対にクリアしたい勉強がはっきりしていますか?
塾のいう通りやっているだけではだめです。塾が教えてくれているのは、やはり最大公約数的な部分。だから、我が子の個別の問題については、多少、親がしっかり考えておかないといけない。
そこでgoogle documentsからスプレッドシートでも文書でもかまいませんから、12月までに成し遂げたいことを、ランダムに書き上げてください。
12月の目標とでもしておきましょうか。
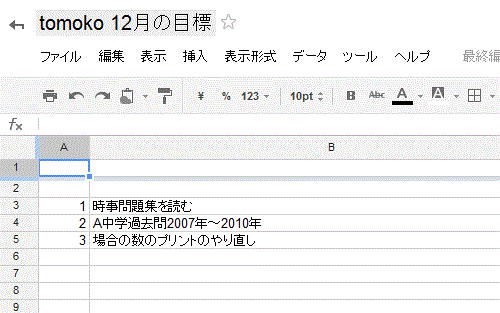
スプレッドシートでも文書でもコピペであとから順番を入れ替えられるでしょうから、ランダムに書き上げて、そのあと、優先順位をつけてください。
この優先順位が大事です。
全部やろうとしたって、書き出したものすべてができるわけはありません。
だから、優先順位を考えておくのです。時間的にできないものは、できないので、次に回すか、あきらめるかのどちらかでしょう。
こういうことはコーチ役としては明確にしておく必要があります。
そして先のスケジュールの中に入れ込んでいってください。

「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
これが11月の最後の試験になるでしょうか。12月もありますが、そろそろ結果を見て、親はいろいろ考えを整理しなければなりませんね。
第一志望をどこにするか、受験校をどう並べるか、1月校はどこにするか、学校によっては内申や親の作文を出さないといけないところもありますから、早めに準備をしておかなければいけませんが。
さて、昨日、試験結果の整理を親がする話をしましたが、実際に親がやっても子どもがピンときていないとまったく意味がありません。なので、たとえば今日、試験が終わったら、試験の感覚があるうちに子どもにレポートをさせたらどうでしょうか。
うまくいった点
うまくいかなかった点
工夫すべきだと感じた点
以上3点をまとめておいて、本人が手書きをしたなら、それを写真なりスキャナーでとっておきましょう。(もちろん現物でもかまいませんが、私は最近、なんでもデジタルにしたがる傾向があります。パソコンの中になんでもしまっとこう、と思っているんですが。)
そして、復習。
これはすぐにやり直した方が良いでしょうね。そして、もう一度反省レポートを書いてみる。
そうすると、工夫すべき点がまた出てくるかもしれない。
親の分析とは別に子どもの分析を記録しておくと、実際に何を注意しなければいけないか、は明確になってきます。
先日、ある小学校受験の先生と話をしていました。実は小学校受験というのは、教える塾側が型にはまってしまっていて、実際に入学試験に出ないことまでさせられてしまうのが多いんだそうです。
時間は短いので、出ないこと、あるいはできていることに時間を費やす必要はありません。
試験には出て、ここでしっかり変えられることに集中する必要があるのです。
例えば来月までに絶対にクリアしたい勉強がはっきりしていますか?
塾のいう通りやっているだけではだめです。塾が教えてくれているのは、やはり最大公約数的な部分。だから、我が子の個別の問題については、多少、親がしっかり考えておかないといけない。
そこでgoogle documentsからスプレッドシートでも文書でもかまいませんから、12月までに成し遂げたいことを、ランダムに書き上げてください。
12月の目標とでもしておきましょうか。
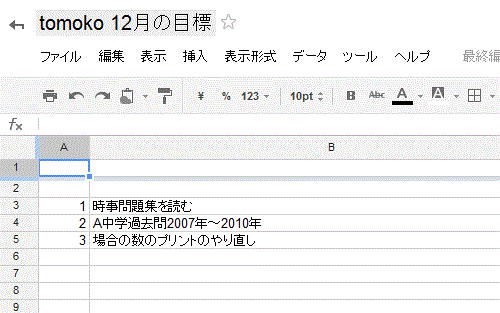
スプレッドシートでも文書でもコピペであとから順番を入れ替えられるでしょうから、ランダムに書き上げて、そのあと、優先順位をつけてください。
この優先順位が大事です。
全部やろうとしたって、書き出したものすべてができるわけはありません。
だから、優先順位を考えておくのです。時間的にできないものは、できないので、次に回すか、あきらめるかのどちらかでしょう。
こういうことはコーチ役としては明確にしておく必要があります。
そして先のスケジュールの中に入れ込んでいってください。

「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
コメント ( 0 )
苦手をつぶす勉強法 1 まずはデータから
苦手をつぶす勉強法 1 まずはデータから(田中貴.com)
 | 親子で受かる! 中学受験手帳 |
| クリエーター情報なし | |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン |
コメント ( 0 )
試験を記録する
何のために、こんなに勉強するのか?
という話になると、当然、今の6年生は動機ができているでしょう。
しかし5年生以下の子どもたちは、そうではありませんね。しかも毎週、新たなカリキュラムがやってくるので、出来不出来には波があります。
例えば記録として、今週のテストの記録は当然、デジタル化されてきています。
塾でもマイページを持つところが多くなりました。WEBでログインすると、自分の過去の成績の一覧が出てくるわけですが、実際はこれが味気ない、というか、うまく利用しなければなりません。
でエクセルを用意するのですが、そんなものはやったことがない、という方もいらっしゃるでしょうか。
そこで使うのがgoogle documentsです。
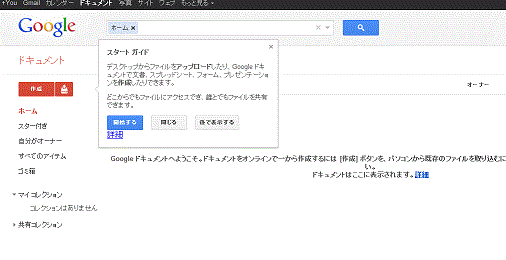
アカウントを作っていますので、google documentsのリンクを押せば、ここに来ます。左側の「作成」をクリックしてください。
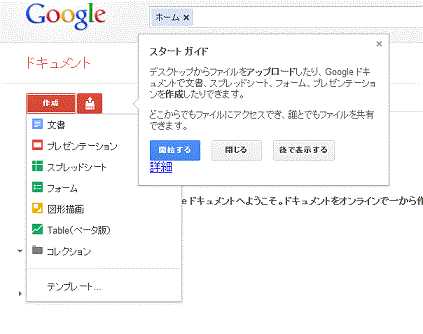
このうちスプレッドシートがエクセルのような表計算ソフトです。子どもたちの成績を扱うには十分すぎる能力を持っていますし、WEBさえあれば、どこでも見られます。スマートホンでもチェックできますから、簡単です。
開いてみましょう。
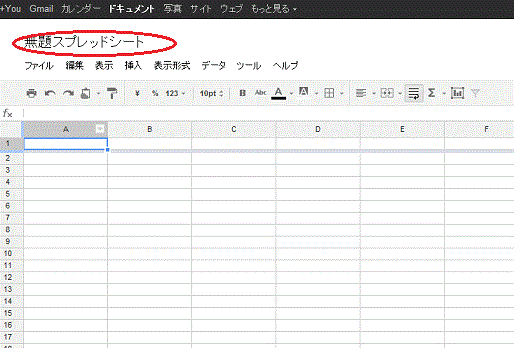
無題とかいてあるところをクリックすると、題名を変えることができます。
「tomokoの戦績」(例)
で、そのあとは表をつけるように、(エクセルがお分かりの方はいつものエクセルの要領で)成績を入力してください。
マイページから一気にコピペしてしまってもいいでしょう。
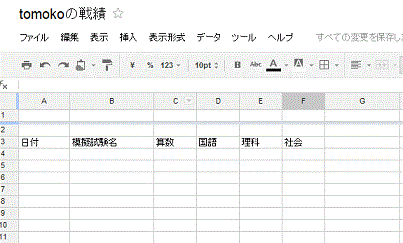
ただ、一番のポイントはデータではありません。実は何を間違えたのか、の記録なのです。
この表にそれを記してもいいですし、あるいはドキュメントの文書から、痛烈なレポートを書いておいてもいいかもしれません。(お母さんのストレス解消になりますか?)
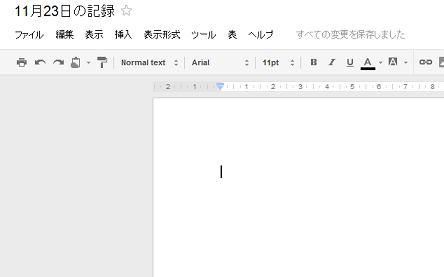
特に、ミスの原因はどうやって矯正するのか、考えなければいけない項目です。
例えば、計算間違いをしていた問題があったとします。ミスはどうしても出るものですが、それでも防ぐ方法はあります。計算を大きく書く、あるいはその場で検算するなどです。そういう方法を実際にやっているのか、答案には結果が出ているのです。多くの子どもたちが問題のすきまに、小さく計算しているのが現状でしょう。「ミスをしてはいけない」と怒るより、どうやればミスが少なくなるのかを子どもといっしょに考えて、変えていかなければなりません。
まず子どもたちには、成績が返ってきたら、すぐ解きなおしてもらってください。そして、できなかったところは、必ず解答を見ながら復習してもらいましょう。その中で、どうしてできなかったのかを考えてみます。「時間がなくてできなかった」場合もあるでしょうし、「まだよくわかっていない」からできなかった場合もあるでしょう。そういうことを、次の試験までに対策していくことが大切です。
次の試験では具体的に何をやるか、も記録してください。そして試験前に必ず子どもと打ち合わせをしましょう。(いいですか、打ち合わせですよ。また怒りを彷彿させてはいけません。)
「今回は計算の場所は決めて、もう一度見直す、が目標よ。」
その具体的な項目をしっかり打ち合わせて、確実にできるようにすることが大事です。
子どもはミスをします。ミスをするのが当たり前ではありますが、その率をいかに小さくするか、ここはコーチ役の腕の見せ所です。
ですから、具体的なポイントを記録しておいてください。これは過去の分を今、やっても大丈夫です。9月からの成績、振り返ってみましょう。
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
という話になると、当然、今の6年生は動機ができているでしょう。
しかし5年生以下の子どもたちは、そうではありませんね。しかも毎週、新たなカリキュラムがやってくるので、出来不出来には波があります。
例えば記録として、今週のテストの記録は当然、デジタル化されてきています。
塾でもマイページを持つところが多くなりました。WEBでログインすると、自分の過去の成績の一覧が出てくるわけですが、実際はこれが味気ない、というか、うまく利用しなければなりません。
でエクセルを用意するのですが、そんなものはやったことがない、という方もいらっしゃるでしょうか。
そこで使うのがgoogle documentsです。
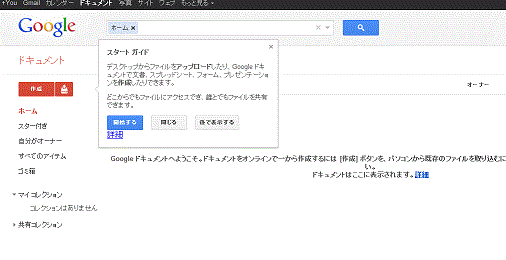
アカウントを作っていますので、google documentsのリンクを押せば、ここに来ます。左側の「作成」をクリックしてください。
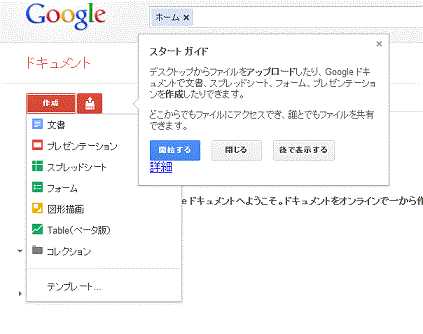
このうちスプレッドシートがエクセルのような表計算ソフトです。子どもたちの成績を扱うには十分すぎる能力を持っていますし、WEBさえあれば、どこでも見られます。スマートホンでもチェックできますから、簡単です。
開いてみましょう。
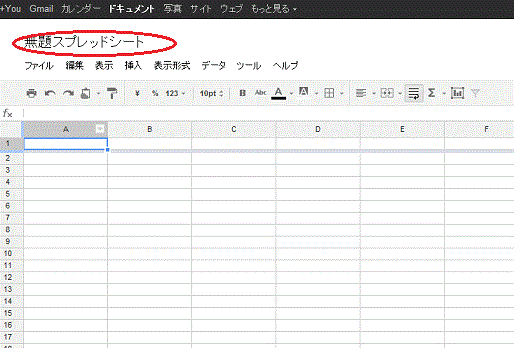
無題とかいてあるところをクリックすると、題名を変えることができます。
「tomokoの戦績」(例)
で、そのあとは表をつけるように、(エクセルがお分かりの方はいつものエクセルの要領で)成績を入力してください。
マイページから一気にコピペしてしまってもいいでしょう。
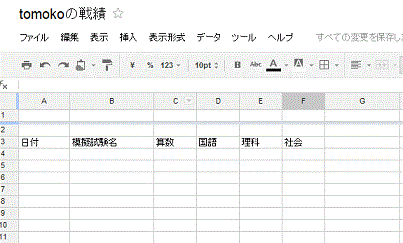
ただ、一番のポイントはデータではありません。実は何を間違えたのか、の記録なのです。
この表にそれを記してもいいですし、あるいはドキュメントの文書から、痛烈なレポートを書いておいてもいいかもしれません。(お母さんのストレス解消になりますか?)
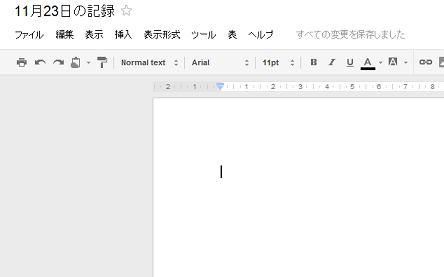
特に、ミスの原因はどうやって矯正するのか、考えなければいけない項目です。
例えば、計算間違いをしていた問題があったとします。ミスはどうしても出るものですが、それでも防ぐ方法はあります。計算を大きく書く、あるいはその場で検算するなどです。そういう方法を実際にやっているのか、答案には結果が出ているのです。多くの子どもたちが問題のすきまに、小さく計算しているのが現状でしょう。「ミスをしてはいけない」と怒るより、どうやればミスが少なくなるのかを子どもといっしょに考えて、変えていかなければなりません。
まず子どもたちには、成績が返ってきたら、すぐ解きなおしてもらってください。そして、できなかったところは、必ず解答を見ながら復習してもらいましょう。その中で、どうしてできなかったのかを考えてみます。「時間がなくてできなかった」場合もあるでしょうし、「まだよくわかっていない」からできなかった場合もあるでしょう。そういうことを、次の試験までに対策していくことが大切です。
次の試験では具体的に何をやるか、も記録してください。そして試験前に必ず子どもと打ち合わせをしましょう。(いいですか、打ち合わせですよ。また怒りを彷彿させてはいけません。)
「今回は計算の場所は決めて、もう一度見直す、が目標よ。」
その具体的な項目をしっかり打ち合わせて、確実にできるようにすることが大事です。
子どもはミスをします。ミスをするのが当たり前ではありますが、その率をいかに小さくするか、ここはコーチ役の腕の見せ所です。
ですから、具体的なポイントを記録しておいてください。これは過去の分を今、やっても大丈夫です。9月からの成績、振り返ってみましょう。
お知らせ
12月から田中貴.com通信を発刊します。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
コメント ( 0 )
田中貴.com通信
平成14年6月から田中貴.net通信を月刊で発行します。
このnet通信では、学校情報、塾情報、学習アドバイスなど、適宜 掲載してまいります。→見本(pdf)
ご購読希望の方は以下より、ご登録ください
携帯のメールも承ります。
なお、ご購読中止の場合も以下よりご送信ください。
田中貴.com通信ページ
このnet通信では、学校情報、塾情報、学習アドバイスなど、適宜 掲載してまいります。→見本(pdf)
ご購読希望の方は以下より、ご登録ください
携帯のメールも承ります。
なお、ご購読中止の場合も以下よりご送信ください。
田中貴.com通信ページ
コメント ( 0 )
失敗した学校選び(田中貴.com)
失敗した学校選び(田中貴.com)
 | 親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート |
| クリエーター情報なし | |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン |
コメント ( 0 )
plan do see
してみせて、いってきかせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ
山本五十六のことばです。よくビジネス書に出てくるのですが、子どもたちにもよくあてはまります。(ぜひ、これも受験手帳に書き込んでおいてください。)
「勉強しなさい」だけでは、わからない子どもはたくさんいます。ですから、してみせなければなりません。さらにくわしい解説がいるでしょうし、それも何回か繰り返さなければならないでしょう。
そして自分でさせてみて、最後が大事ですね。「ほめてやらねば」ダメなのです。
その意味においては、私はお母さんが子どもたちといっしょに勉強することを楽しむことが大事だと思います。中学校に入ったら、子どもといっしょに勉強するなんて時間はまずありません。ご自分の経験を振り返られても、まずないことだと思います。ですから、小学生の時間はとても貴重なのです。
うちの子どもたちももう大きくなってしまいましたから、勉強を教えることなどまずなくなりました。それはそれで大きくなったということなのですが、やはりさみしいものです。ですから、この機会をどうぞ楽しんでください。お母さんも勉強しれみれば、良いと思います。そしてぜひ子どもたちがやっている勉強の大変さを理解してあげてください。
私も中学受験をした口ですが、今の子どもたちがやっているほど絶対に勉強しませんでした。塾に入ったとき、こんなに難しくなったのかと改めて感心したほどです。大変だと理解できれば、ほめることばも多くなります。
お母様たちのことばは、子どもたちには割と辛らつです。これは身近に生活していていろいろな欠点が見え、それを何回注意しても直らないから、だんだん辛らつになっていくのでしょう。
しかし、子どもを育てる上で一番、大事なことば、「ほめることば」を増やすということです。ほめられれば、子どもたちには自信がつきます。「そんなことをいったらのぼせてしまう」と心配されている方もいらっしゃるかと思いますが、お母さんがほめることばを多くすれば、必ず子どもたちは積極的になります。
ですから、どうぞほめてあげてください。ほめるのが照れくさい方は、1日1回必ずほめようと決めてください。きっと、子どもたちに対する見方がだんだん変わってくるでしょうし、さらには子どもたちも変わってくると思います。
ビジネスの上ではよくplan do seeということばが使われます。計画し、実行し、確認するという意味ですが、子どもの勉強に関しても同じことが言えます。何が終わったのか、お母さんはちゃんと子どものノートを見て確認すべきです。ただ言葉だけのやりとりで、
「勉強やったの」
「うん、やった」
「そう、えらかったわね。」
これは受け取り側の子どもによっては効果がまったく違います。一生懸命がんばった子は、ほめられたからまだしも、一生懸命がんばらなかった子は「そうか。これでも通るんだ」と経験してしまいます。
ほめられるのであれば、もっと具体的にほめられた方がほめられる方もうれしいに決まっています。
「あら、こんな問題もできるようになったの」
とか
「ずいぶん、きれいな字になったわね。」
とか、どうぞ見つけてください。このことが後で非常に、子どもたちの成長に役立ちます。
やはりseeはしっかりと確認すべきです。別にお母さんがそこで教える必要はありません。わからないことがあるのであれば、今度、塾の先生に聞いてきてね。ということでもかまいません。たとえば、わからなかった問題を受験手帳に書きとめておいて、あとで先生に尋ねたかどうかを確認してあげてもいいのです。忘れそうな男の子なら、5×3のカードに書いて、先生に渡してもらってもよいかもしれません。長くやる必要はありませんが、子どもたちが自分で意識を持つまでは必要なことだと思います。ポイントはお母さんが子どもたちの勉強を把握しているということです。中学生や高校生になれば、当然、これを自分でやるわけですが、まだ小さいですから、なかなか自分でコントロールすることはできないのです。ですから、それを肩代わりしてあげてください。
だからといって子どもを罵倒しては、ぜったいにいけません。その意味で、親戚の子を預かったくらいの距離感をお持ちになるとよいかもしれません。
それとseeではもうひとつ大事なことがあります。それはことばではやさしく、態度はきびしくということです。例えば、本来は4時から勉強することになっていたのに、友達と遊びに行ってしまって、その日の予定が終わらないということはままあるものです。
このとき大抵のお母さんは
「だから、いったでしょう。もうこんなに遅くなって、早く寝なさい。」
とおっしゃると思います。
これが言葉で厳しく、態度があまい例。
本来は
「そう、大変ね。がんばってね。お母さん、先に寝るから。」
とおっしゃっていただきたいところです。
言葉は優しいですが、「約束は守ってね。」と態度は厳しいですね。
これを聞いた子どもはどう思うでしょうか?
「ちゃんと、やんなきゃ、寝れないんだ」
そういうことが積み重なってくると、子どもにも自覚が出てきます。
できることを積み重ねることが子どもの勉強にはどうしても必要です。塾で課題を出されても、スケジュールに入りきらなかったら、塾の先生にぜひ相談して、やり切れる内容にしぼりこんでもらってください。
山本五十六のことばです。よくビジネス書に出てくるのですが、子どもたちにもよくあてはまります。(ぜひ、これも受験手帳に書き込んでおいてください。)
「勉強しなさい」だけでは、わからない子どもはたくさんいます。ですから、してみせなければなりません。さらにくわしい解説がいるでしょうし、それも何回か繰り返さなければならないでしょう。
そして自分でさせてみて、最後が大事ですね。「ほめてやらねば」ダメなのです。
その意味においては、私はお母さんが子どもたちといっしょに勉強することを楽しむことが大事だと思います。中学校に入ったら、子どもといっしょに勉強するなんて時間はまずありません。ご自分の経験を振り返られても、まずないことだと思います。ですから、小学生の時間はとても貴重なのです。
うちの子どもたちももう大きくなってしまいましたから、勉強を教えることなどまずなくなりました。それはそれで大きくなったということなのですが、やはりさみしいものです。ですから、この機会をどうぞ楽しんでください。お母さんも勉強しれみれば、良いと思います。そしてぜひ子どもたちがやっている勉強の大変さを理解してあげてください。
私も中学受験をした口ですが、今の子どもたちがやっているほど絶対に勉強しませんでした。塾に入ったとき、こんなに難しくなったのかと改めて感心したほどです。大変だと理解できれば、ほめることばも多くなります。
お母様たちのことばは、子どもたちには割と辛らつです。これは身近に生活していていろいろな欠点が見え、それを何回注意しても直らないから、だんだん辛らつになっていくのでしょう。
しかし、子どもを育てる上で一番、大事なことば、「ほめることば」を増やすということです。ほめられれば、子どもたちには自信がつきます。「そんなことをいったらのぼせてしまう」と心配されている方もいらっしゃるかと思いますが、お母さんがほめることばを多くすれば、必ず子どもたちは積極的になります。
ですから、どうぞほめてあげてください。ほめるのが照れくさい方は、1日1回必ずほめようと決めてください。きっと、子どもたちに対する見方がだんだん変わってくるでしょうし、さらには子どもたちも変わってくると思います。
ビジネスの上ではよくplan do seeということばが使われます。計画し、実行し、確認するという意味ですが、子どもの勉強に関しても同じことが言えます。何が終わったのか、お母さんはちゃんと子どものノートを見て確認すべきです。ただ言葉だけのやりとりで、
「勉強やったの」
「うん、やった」
「そう、えらかったわね。」
これは受け取り側の子どもによっては効果がまったく違います。一生懸命がんばった子は、ほめられたからまだしも、一生懸命がんばらなかった子は「そうか。これでも通るんだ」と経験してしまいます。
ほめられるのであれば、もっと具体的にほめられた方がほめられる方もうれしいに決まっています。
「あら、こんな問題もできるようになったの」
とか
「ずいぶん、きれいな字になったわね。」
とか、どうぞ見つけてください。このことが後で非常に、子どもたちの成長に役立ちます。
やはりseeはしっかりと確認すべきです。別にお母さんがそこで教える必要はありません。わからないことがあるのであれば、今度、塾の先生に聞いてきてね。ということでもかまいません。たとえば、わからなかった問題を受験手帳に書きとめておいて、あとで先生に尋ねたかどうかを確認してあげてもいいのです。忘れそうな男の子なら、5×3のカードに書いて、先生に渡してもらってもよいかもしれません。長くやる必要はありませんが、子どもたちが自分で意識を持つまでは必要なことだと思います。ポイントはお母さんが子どもたちの勉強を把握しているということです。中学生や高校生になれば、当然、これを自分でやるわけですが、まだ小さいですから、なかなか自分でコントロールすることはできないのです。ですから、それを肩代わりしてあげてください。
だからといって子どもを罵倒しては、ぜったいにいけません。その意味で、親戚の子を預かったくらいの距離感をお持ちになるとよいかもしれません。
それとseeではもうひとつ大事なことがあります。それはことばではやさしく、態度はきびしくということです。例えば、本来は4時から勉強することになっていたのに、友達と遊びに行ってしまって、その日の予定が終わらないということはままあるものです。
このとき大抵のお母さんは
「だから、いったでしょう。もうこんなに遅くなって、早く寝なさい。」
とおっしゃると思います。
これが言葉で厳しく、態度があまい例。
本来は
「そう、大変ね。がんばってね。お母さん、先に寝るから。」
とおっしゃっていただきたいところです。
言葉は優しいですが、「約束は守ってね。」と態度は厳しいですね。
これを聞いた子どもはどう思うでしょうか?
「ちゃんと、やんなきゃ、寝れないんだ」
そういうことが積み重なってくると、子どもにも自覚が出てきます。
できることを積み重ねることが子どもの勉強にはどうしても必要です。塾で課題を出されても、スケジュールに入りきらなかったら、塾の先生にぜひ相談して、やり切れる内容にしぼりこんでもらってください。
 | 親子で受かる! 中学受験手帳 |
| クリエーター情報なし | |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン |
コメント ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |





