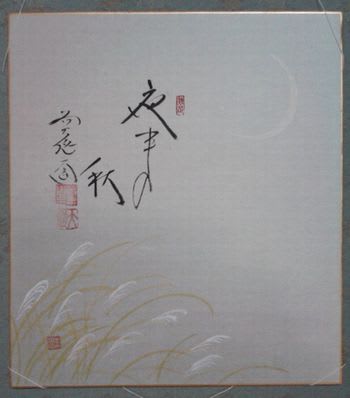★ 茶の湯とはただ湯を沸かし茶をたてて
のむばかりなる事としるべし (利休道歌より)
茶道にかかわって40数年、
いまだにこの歌の周りをうろうろしています。
行きつ戻りつ、なかなか居直れません。
この世界ではまだまだひょっこですから、仕方がないですね。
今日は稽古のために準備した道具で、
一人奥伝の点前をしてみました。
終わった後はちょっとすっきりして、
頭と体と心の体操になったようです。
社中の方の中に、
前回の東京オリンピックの開会式の日に生まれた方がいらっしゃいました。
ですからオリンピックの年には56才ということです。
その因縁で、7年後のオリンピックには、
何かの形でか関われることになのかもしれませんね。
聖火ランナーの一人に選ばれるとか、開会式に抽選で招待されるとか。
ない話でもありませんね。
私もできたら「おもてなし」の一環に加わってみたいですが。
急速に周囲が変わっていく予感。
何よりもまず、そのためにも震災からの完全復活が目標ですが。
若い人にも、高齢者にも、突然に降ってわいた7年後という目標。
まだ先のようでも、きっとすぐ来てしまうでしょう。
七年後には、私も少し変わっているでしょうか。
↓ここをぽちっと!