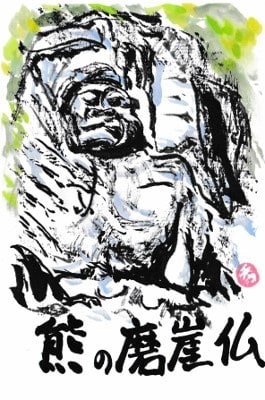
大分県の「熊の磨崖仏」(タイトル)です。
坂道の階段を登りきったところにありました。
よくぞ、適当な岩を見つけました。
今日のタイトルは、「伝える」です。
悩んだときに、先輩の一言で助かった。
入社したての頃、弁当の片づけをしていました。
別に決められたことではありませんでした。
「なんで、俺ばっかり」と言った一言に、長年勤めている女性から、
「やらなきゃいいじゃない」と反応がありました。
今思うと、「やらせていただきます」ではなかったな。
伝えるとは、
①つたわらせる
言葉を取りつぐ。また、(ひろく)言い知らせる。
次々に後代に言い知らせる。語りつぐ。
学問や技芸などを教え授ける。
物事を渡し授ける。譲り渡す。
はこぶ。もたらす。また(作用を一方から他方へ)移す。
②受け継がれて来る。ものをうけとめる。
聞いて知る。伝聞する。
学問や技術などの伝授をうける。うけつぐ。
物事をひきつぐ。
(広辞苑より)
私達は、「①つたわらせる」に重きをおきがちです。
田舎では、過疎にならぬよう、現状維持のため何かを後世に伝える。
都会では、個人レベルでは何を伝えようとしているのか明確ではない。
それは、個人より行政の仕事です。
なぜなら、都会ではあまりにも多くの人々が出入りするからです。
良かれと思っても、受け手は次々に動き、情報も頻繁に変わり、人々の集中度は分散される。
個に埋没し、互いは無関心となる。
心配なのは、伝えようとする流れが上流から下流へと決まっていること。
下流から上流への動きは封じられる。
下流は、上流からの情報の受け手として、情報を取捨選択する自由はある。
しかも都会の上流と田舎の上流は交じり合わない。
都会の上流が圧倒的に大河な故に、田舎の小さな流れはなきがごとく。
田舎の上流は、社会全体では無視される。
受け手について書いてみたい。
仮に、学生時代だけ田舎で暮らすことができたらどうなるだろう。
学生時代を都会で暮らすことはよくあることです。
受け手としての経験の幅が広がるだろうか。
私は、受け手を鍛えたい。
田舎で暮らす学生が、一日三便のバスを利用して生き抜いていく。
一時間に一本だけ走る列車を利用する。
不便極まりない。受け手の学生はどうするだろう。
勉強の合間にアルバイトをしたい。働く場所は限られている。
学生でありながら、起業する人も増えてくる。無いものは作るしかない。
耕作放棄地を見て、グループで野菜を作るものも出てくるだろう。
田舎だって、若い労働力と知恵を見過ごすわけがない。大いに活用しようと試みるだろう。
田舎では、人財不足のはずである。
情報の流れを、上流から下流へと書いてみた。
例えば、運河のようなものができ、下流であっても上流のような流れができるのではないかと考える。
高速道路のように、いったん東京へ戻った方が目的地に早く着く。
これは一昔前で、何重にも環状線ができている。しかし、あくまで東京の交通緩和にしか見えない。
運河に目的地が無ければ、流れは出来ない。
(ここで中断。残り飯で炒飯を作った。
プロが作る炒飯は、すべての飯がばらばらでしかも卵がまとわりついている。
さすればと、卵飯(事前に卵を溶きからめた)にして炒飯を作ってみた。
プロと同じ炒飯の形にできた。あとは味付けだけである)
大分県は、移住者を大いに呼び込んでいる。移住者の町が点在するようになった。
大分県庁は、動き出した。移住者を呼び込まない場所も通過点とみなし整備した。
点在する移住者の拠点が、ベルト状になっている。
そのうち、福岡県とも熊本県やその他の県と連携を始めることだろう。
やがては九州全体がユニークな移住者の楽園になることであろう。
有名な企業は、卒論に「町の活性化」に取り組んだ学生を積極的に採用した。
すべての授業を英語でやる大学の学生を採用した。この大学は、留学生が半数を占める。
同時に、留学生は日本語も習得でき、日本人学生は国際交流ができた。
過疎の町に来た学生の卒論は、「空き家の再生」や「シャッター街の活性化」などのテーマとする。
再生できた空き家に住んで、隣接する耕作放棄地で日々食べる食材を作る。
専門家(建築学部、工学部、農学部など)の卵は余るほどいるし、彼らにとっても貴重な実践フィールドである。
机上の学問に比較し、必要なものは多いが、流した汗と見た情報は格段に生きるはずである。
学生が、代々自治権を持ち管理する空き家に住めばよい。小さくて高いアパートに住む必要はない。
不便を体験することが、やがて上流になって流す情報の質が変化する。
逆に都会の空き家に、田舎から来た学生が住めばよい。互いの自治体が積極的に斡旋する。
ドイツの学校では、両親が教えてくれても単位となり卒業できる。学校に行くだけが教育ではない。
庭の花を見て、数学を学び科学を学ぶ。汗を流して体力を鍛える。
虫と共に音楽を聴き、花を愛でる。
どこにも青山ありです。
キーワード 探すが未来 ヒントなり
2020年6月29日

















