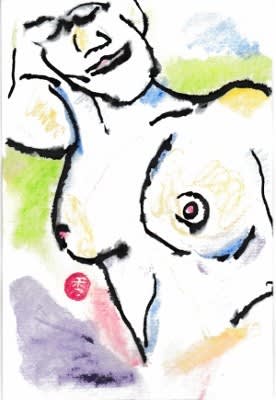故郷を離れて早40年。私は、故郷に何かの恩返しをしたい。

可愛い「孫娘」です。
お盆まで描いてね。と頼まれました。
キュートな唇です。
今日のタイトルは、「お盆」です。
東京にいるときは、新盆でした。
なすやきゅうりの馬が玄関先に飾ってありました。
送り火です。今日は何の日だっけとなりました。
夏休みになると、従弟たちが広島から島に来ました。
お盆に、おじさんやおばさんが来て一緒に帰りました。
年下の従弟たちのお守は、私の役目でした。
昼寝させるのに、図書館で借りてきた風土記を読み聞かせていました。
食事の準備も自分の役目でした。
広島は都会で、田舎の暮らしに慣れるまで少し時間がかかりました。
おばさんはよく知っていて、佃煮も一緒に持たせてくれました。
佃煮のお茶漬けはよく食べました。
島での遊びは、お茶漬けでは持たないので、段々と我が家の食事も食べるようになりました。
もうすぐお盆です。
孫が来て嬉し、帰って嬉しです。
大企業ほど、お盆休みをずらして社員は休みをとります。
8月初めからお盆まで、どこの行楽地もにぎわいます。
ドイツでは、半強制的に2週間以上の夏休みをとらせます。
ここでは、まだお盆休みに休暇を取って家族が集まります。
カフェも忙しくなるぞと、定休日も開店しました。
さっぱりでした。やはり、家族と一緒に過ごすのでした。
故郷の島では、竹と紙でできた灯篭を持って墓参りをします。
灯篭の中に芋でこさえた台座にろうそくをたてます。迎え火でしょうか。
風の強い年は、これが山火事の原因となりました。
お盆が終わった後、子供たちは、燃え残りのろうそくを集め冬の隠れ家での灯としました。
商店会でお盆祭りを盛り上げる企画を作りました。
毎年やっている子どもたちが絵を描いてくれたペットボトル製の灯篭を道の両側に置きます。
お寺の門に商店会の看板を設置します。
駐車場の白線引きとプラスチック製の花を電柱に取り付けます。
浴衣の貸し出し、地域の懐かしい写真の展示、生ビール販売などなど。
盆踊りを三日間続けているのは珍しい。
一日だけとなり、それも途切れてしまった地域が多くなってきました。
私達は、お盆を外して故郷広島や子供の住む横浜の家に帰ります。
大人の休日俱楽部で買える割安切符(3割引き)が、お盆の時期は買えないからです。
少しだけ、親孝行をし、子どもと過ごします。
子供の頃や働いている時ほど、楽しみではなくなりました。
それでも、お盆と聞けばほっとする。
同窓会の予約もあるかもしれません。
カフェを開けることにしました。
お盆玉 あげたいけれど 孫遠し
2019年7月31日

絵のタイトルは、「素」です。
ボーイッシュなクールビューティーです。
今日のテーマは、「私にも与えるものがある」です。
子の恩返しは、4歳までに完了している。
それ以上の恩返しは、求めない。対等な人間として生きていける。
貧しい家に育った人たちは多くいる。
自分と同じ思いはさせられないと、叶えられなかった教育を子供に受けさせる。
子供は、親の言う通り順調に育ち、今の肩書と暮らしを得た。
親たちは、先輩たちは死に物狂いで生きてきた。
その体験を子供や後輩はすることがない。
それが、コンプレックスであった。
足りないものと自覚してはいるけど、死に物狂いにはなれない自分がいる。
親父は、毎晩100Kgのみかんを背負い、あぜ道を朝方まで運んだ。何度も、何度も。
それから、農業以外の現金収入のため工場に行った。
そんな真似は、到底できぬと中学生の私は思った。
100Kgを背負って同じ道を歩いたのは高校生のころで、こんなことをしてはいけないと思った。
親父が汗水たらして運んだみかんのお陰で、大学に行けた。
いただいた恩は、山ほどある。
返すことは、これっぽちもない。
そう思い生きてきた。
息子が、私の仕事(プロジェクトエンジニアー)をしたいと言い出した。
60歳を過ぎても現役で、仕事に見合う報酬を得ているのが動機であった。
息子は何度も挫折した。自分に足りないのは何だろうと思ったことだろう。
コンプレックスの塊の若者が、親から感謝される日が来る。
あきらめかけていたけど、お前の一言でまた頑張れると生き返った。
頑張った証がある。しかし、それはもう時代遅れなのである。
お父さん、あなたのこんなところが素晴らしいと、本気で息子が言った。
語る息子の目には涙が溢れている。
俺にも、親父のためになることがある。
双方、信じられない瞬間である。
「私にも与えるものがある」でした。
追いつけぬ 死ぬまでこれか 生きてこそ
2019年7月30日
<<投稿後>>
私達が越えられない壁があるとしたら、戦争体験者の苦労や戦後復興の頑張りであろう。
大きな壁と感じていた。
今の若者たちは、それはもう過去のものと思うかもしれない。
しかし、毎日生きていてちっとも楽しくない。
親父たちもきっと同じであったろうと思う。
これではいけないと、個人の責任で這い上がってきた。
私達も同じ、息子たちも似たようなものだろう。
「本気」だけが、世代を超越して感謝の言葉となるのだと感じた。
(筆者)

タイトルは、「鳥栖の女」です。
サロンパスの工場の裏にある野外美術館で見ました。
夏空に黒いブロンズ像がよく映えました。
大学生の頃、4階建ての学生寮に、しばし住んでいました。
アルバイト(地下鉄の看板付)から帰るのは、朝8時頃でした。
4階建ての最高階は、この時間から焼けるように熱くなりました。
水のシャワーを浴び続け、身体をキンキンに冷やして、勢いで寝ました。
今日のテーマは、「夏の始まりは、シャワーから」です。
昼は晴れ暑い、夜には雨が降り蒸します。
夕飯前と朝の農作業後は、水風呂でさっぱりしたい。
ヨーロッパの安いホテルや沖縄の民家は、シャワーしかありませんでした。
仕事から帰るとシャワーを使い、冷たいビールか泡盛でいっぱい。
つまみは、ソーメンチャンプルーか島豆腐のやっこ。
ヨーロッパでは、チーズでした。
汗っかきの私は、日に何度もシャツを着替えます。
そして脱いだものがかびないように何度も洗濯をします。
洗濯をすれば干し、夕方には取り込み畳み、タンスの元の位置へ戻します。
出張中もホテルの流しで洗い、バスタオルで水気を切り、ありたけのハンガーに干しました。
ある年、沖縄に台風が来ませんでした。
民家は断水になりました。ホテルは使い放題でしたが、自粛しました。
パキスタンの宿舎では、タンクの貯水がなくなるとシャワーはあくる日まで使えませんでした。
畑から帰った両親は、まず水風呂を浴びて昼食をとり昼寝をしていた。
島の子供は昼寝をすることもなく、海に飛び込み唇が紫になるまで、水と遊んでいた。
我が家にはシャワーがありません。
朝シャンがわりに、水風呂です。昨夜の風呂が冷め丁度よいのです。
夏がきました。
来たものの、いつまで続くのでしょう。
まだあるな 暑さ寒さも 彼岸まで
2019年7月29日
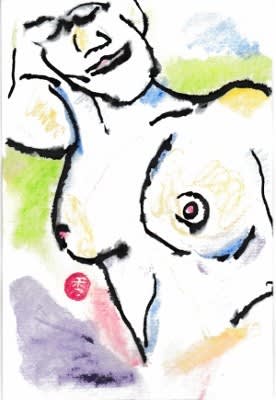
タイトルは、「笑う女」です。
出会った時の喜びを忘れてしまう。
これでは情けない。
磨き上げなければ。
誰も期待していないのに、萎縮したり緊張をする。
普段通りのプレーができない。
前に進もうか、ここらで一休みしようか迷っています。
若い時のできないかもしれないという不安。
身体が言うことをきかなくなってからの不安。
3年先の約束(保証)をためらっています。
できることを、できるときにすればよい。
できることは、年々少なくなってきたように感じています。
やれば、かかれば何となくできそうなんです。
時が重くのしかかってきます。
周りの気がかりにかまけてばかりで、本丸に行けないような戦闘状態です。
言ってみれば、日々生きることで精いっぱいです。
都会で会社員をしていた頃も同じでした。
ということは、年齢には関わらないことなのです。
できないことを棚に上げて、応援とか社会の仕組みだとかに不満を持つ毎日です。
ここにきて三年半が経ちました。
明日やろうとしたことを、誰かが担当だと決めていたことをやれるようになりました。
ごみを見て見ぬふりをして通り過ごしていました。
今は、今だけと拾えるようになりました。
積もり積もって片づけるのが怖いのかもしれません。
ごみに埋もれるのが不快なのです。
今の悩みは、さらにゴミの山を目指せないことなのです。
ここにきて、半年間毎日空き家のゴミを捨て、荒れた土地を開墾し、伸びた庭木の剪定をしました。
捨てられていたカフェを、これも半年間かけて再生しました。
今は、カフェの周りの空き家の草刈をしています。
二週間も経つと、同じ場所の草刈です。
見かねて空き家の梅の木を剪定しました。
剪定までは勢いでできました。
伐った草や枝の片づけができないのです。
戦線を拡大したのかな。
草刈も片づけも仕事と思っていました。
仕事だから苦労するのは当たり前でした。
仕事ではなくなってからができなくなりました。
炊事、洗濯と掃除で精いっぱいです。
この地をよくしたい。
素晴らしい暮らしや営みを知らせたい。
この感情を維持したり、湧き立たせるものは何でしょう。
放置された畑や山の道を整備したい。とにかく風を通したい。
できないことを数えるのをやめにしなければならない。
残されたできることを評価しよう。
進まないけど、少しずつ陽の光が届くようになっています。
この辺りの方は、一雨ごとに伸びる草との競争だと言われます。
生きている限り、やめられない。
きっと、こんなことが与えられた仕事なんでしょう。
人にやらせてなんぼ、ではないのです。
自ら汗をかくしかないのです。
業の種 こさえて腐り 浮気した
2019年7月28日
<<投稿後>>
モチベーションの維持が、目下の課題です。
弱気になると、人を貶めようとします。
自らが偉くなることはないのです。
それでもそうする自分を恥じる。
(筆者)

女木島の「オーテ」です。
冬の瀬戸内の強い風から暮らしを守るために築いたものです。
オーテのなかは、冬でも春のようでした。
私達は、あきらめていませんか。
どうせ、頑張ったって無理だな。
だから、このくらいでいいんじゃない。
毎日、厳しい。
少しずつしか頑張れない。
満足より、不満が多い。
今日のテーマは、「良さを伝える」です。
今月は、予約が11回(22日営業)ありました。
3人の編み物をする会。4人のパンを作る会。3人の古文書を読む会(公民館)の合間の食事会。
ビアガーデンが6組(6人~19人)。などなど。
すべてメンバー(人数、参加者)が異なります。
あえて、また従ってメニューを変えます。
私達はプロフェッショナルの料理人ではありません。
7月は、昨日まで162人(19日営業)の胃袋を満たしてきました。
美味しかった。また、来たい。と思ってもらえるのが、唯一の目標です。
毎食、手を抜かない。
草を刈るのも剪定するのも、すべて満足のためです。
ひょっとしたら、自己満足なのかなとも思います。
「良さを伝える」ことは、なかなかできないものです。
金額を抑えるためには、美味しいを作るためにはと、格闘しています。
賞味期限、野菜の出来栄え、納得の品質の小麦粉と食材を気にしています。
在庫管理をし、新しく挑戦する料理の値段を決めます。
「おもてなし」のプロフェッショナルになりたいと思っています。
ここで少しの時間を過ごすことが、楽しい。
少しでもそう思ってもらいたい。それが、毎日続きます。
こうしたいと思っていることは、いくつかあります。
カフェの裏の畑の篠竹を刈りたい。刈った草を片づけ、剪定した枝を片づけたい。
前の空き家を少しでもきれいにしたい。
帰ってこられなくなって空き家になった家を利用し民泊を始めたい。
なんの変哲もない田舎です。
鳥のさえずりが聞こえ、木々から漏れる日差しや流れる雲を見て欲しい。
人々の明るさと優しさに接してほしい。
自分たちが美味しいと思うものを作り続けておられます。
これを伝えたい。
伝えるためには、自分がどうしたいと思わなければ始まりません。
熱量です。もどかしいけど、高みを見るしかない。
どの人にも素晴らしい表情がある。
それを伝えたいと筆を握る。その時間を作りたい。
義兄の死から多くのことを学んだ。
都会の一軒の空き家の始末。無縁墓の継承。
息子たちから理解を得て、応援してもらっています。
人は生きる権利がある。貧しくても楽しいことがある。
誰かが少しだけ応援することで、それはできるかもしれないと義兄を支えてきた。
私が助けられた。
生きていていいんだよ。
生きることは、こんなに素晴らしいことだよ。
営々と築いてきた暮らしがある。
そこにも、ここにも。
そんな些細な一生懸命を伝えたい。
汗と汗 ぶつけ合って 生きてきた
2019年7月27日