■罪の轍/奥田英朗 2021.4.12
『罪の轍』 を読みました。
幼児誘拐をテーマにした面白いミステリです。
登場人物が、生き生きと描かれています。
山谷で簡易旅館と食堂を営業している町井福子とその娘のミキ子。
警察嫌いで、「警察」と聞くと突如、頭に血が上る、福子。
気っ風のよい、明るくものに動じないミキ子。
いぶし銀のような老刑事、大場茂吉。
時代を彷彿させる、山谷労働者連合会。
昭和の時代を懐かしく懐古させる当時の雰囲気。
大変面白く、懐かしく読みました。
淡々とした性格の宇野寛治の犯行には、少し意外感がありました。
五十代半ばの大場茂吉は古株の刑事である。かつては捜査一課に長く所属していた。
大場は昌夫を睨み据えて言う。見るからに昔気質の刑事で、浅黒い顔には深い皺が刻まれていた。
「熱海はホシがよく逃げ込むんだ。不思議なもんでな。東京で金を手にした犯人は、みんな判で押したように熱海の温泉に行きやがる。そんなもんだから、おれも何回か熱海に足を運ぶうちに、熱海の刑事たちとも懇意になったわけさ」
品川を通過すると、線路帯が急に広くなった。何台ものブルドーザーがうなりを上げ、ヘルメットを被った大勢の人夫がつるはしを振るっている。その規模の大きさに昌夫は唖然として眺めながら、ああ新幹線工事なのかと納得した。東海道新幹線の開通は来年秋で、今から一年後は、ちょうど東京オリンピックの開催期間である。
蛍光灯が一本だけ灯ったままの天井を見上げ、じっとしていたところ。すぐに睡魔がやって来て、寛治は目を閉じた。気づいたときは明るかったので、よく眠れたのだろう。北海道でも留置場を経験していたので、緊張することもなかった。何よりも寒くないというのがいい。東京はやっぱり住みやすい。
「それもおれは知らん。ただし刑期を終えた人間は、たいてい地元に戻るものだがな。土地勘がないと怖いんだろう。犯罪をすると飛ぶくせに、終わると戻って来る。犯罪者は気が小さいんだよ」
横丁カフェ 『罪の轍』 奥田英朗
『 罪の轍/奥田英朗/新潮社 』
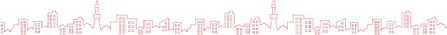
東京オリンピック 1964年(昭和39年)10月10日
吉展ちゃん事件 1963年3月31日
吉展ちゃん誘拐殺人事件
ぼくの少年時代に起こった、全国を震撼させた大事件。
事件の記憶は、ある。 だが、犯人は誰だったのか、全然覚えていない。
犯人逮捕まで、少し間があったせいかもしれないが。
そこで、本田靖春の 『誘拐』 を読んでみた。
解説 貧しきものたちへの視線 鎌田慧
このドキュメントでは、小原保が証拠不十分で逃げ切ろうとする寸前に、捜査陣を一新して自供に追い込んだ刑事の執念が描かれている。テーマも事件解決にむかう息詰まるような、スリリングな人間ドラマにおかれているのだが、それを越えて普遍性があるのは、貧しいものたちが、ささやかな欲望のために破滅に迫いやられる、その拙ない人生に、著者の思いが託されているからてある。
小原が誘拐を思い立った、という黒沢明の「天国と地獄」の身代金は、三千万円である。ところが、小原の要求は、五十万円でしかなかった。......
この金額は、すべて小原の借金の返済に消えた。いわば、借金の返済に行き詰まった末の凶行といえる。小原は五十万円を強奪したあと、せっせと返済にまわってあるいている。なんと律儀でいじましい犯罪者なのであろう。
1964年当時と比べると捜査で使われる科学技術や都市環境など、想像できないほどの進歩をとげている。しかし、どんなに時代が進もうとも変わらないものが、人々の生活のなかに厳然として存在する。
このドキュメントを読んで、考えさせられたことがある。
他人に対する過剰なまでのお節だ。
なぜ、そっとしておいてあげることが出来ないのか。
いたずら電話は、春が過ぎ、夏が来て、秋になっても、一向に跡を絶たず、日に三、四回はきまって彼らの心を乱した。
その堀も一課暮し三十年を越えて、髪は白く、最ベテランになってしまった。
手元に残る一冊の古びた大学ノートに、彼の半生が凝縮されてある。事件を手掛けるたび、堀はそのノートに、捜査の概略を細い字で記して来た。解決したものには、末尾に犯人の氏名が朱で書いてある。そのほとんどが、いわゆるコロシであり、彼は戦後の大事件にあらかたかかわって来た。
人が人を殺す。あるいは、人が人に殺される。これ以上ない異常の中に自分の日常を置いて、ノートの余白を埋めて行くごとに、堀の内側で深まる思いがあった。
動機ある殺人といわれるものを堀から見れば、被害者には「くるべきものが来た」のであって、彼は「殺されて当然」の人間なのである。そうとしか受け取りようのない事例を、堀はあまりにも多く見過ぎた。そして、それをいうときの心情は、はっきり殺人者の側に傾いている。......
畢竟、人間というやつは、他のだれかを圧迫しないと生きられない存在なのであって、犯罪者というのは、社会的に追いつめられてしまった弱者の代名詞ではないか。
捜査一課で三十年を費やして、堀が得たものといえば、そういう考え方であった。
後に平塚は、そのときの心境をサンケイ新聞社会部の佐々木嘉信にこう語っている。
その意図ってのはな、幹部はいつでも出来上ったもの(捜査報告書)ばかりいただいてる。つまり、机上と現場はピタリ一致していねえってことだ。
そうだろう、幹部には張込みのデカがつかまった話なんか伝わってねえ。完璧な布陣だってことになって報告されたわけよ。おれが組織捜査が嫌いだってのは、現場の意見がまっすぐ上に届かねえで、途中でひん曲って伝わることが多いからだよ、組織ってのは。
ついでにいっちまえば、組織にのっかると肝腎のホシ(犯人)を追うのを忘れて、肩のホシ(階級)ばっかり増やすことを考えるのさ。デカが肩のホシを追うようになったら、おしまいさ。この気持、わかるだろう。
私は十六年間の新聞社勤めの大半を社会部記者として過ごした。そして、その歳月は、犯罪の二文字で片付けられる多くが、社会の暗部に根ざした病理現象であり、犯罪者というのは、しばしば社会的弱者と同義語であることを私に教えた。
もとより新聞は「法と秩序」を否定するものではないが、記者に与えられた役割りは、捜査員の職務とはおのずから別物である。
「鹿を追う猟師山を見ず」のたとえは平凡に過ぎようが、かつての私を含めて、事件報道にたずさわる記者たちにそのきらいがあったことを否めない。
社会が多様化すればするほど、問題の所在も複雑多岐にわたる。......こういう時代こそ......事件をより広い視野でトータルに捉え、そこにからまる問題を深く掘り下げ、社会全般にわたる関心事として受け手に渡す作業が、記者の一人一人に求められているはずである。
小原保の辞世の短歌
世をあとにいま逝くわれに花びらを降らすか門の若き枇杷の木
『 本田靖春集1 誘拐/旬報社 』
『罪の轍』 を読みました。
幼児誘拐をテーマにした面白いミステリです。
登場人物が、生き生きと描かれています。
山谷で簡易旅館と食堂を営業している町井福子とその娘のミキ子。
警察嫌いで、「警察」と聞くと突如、頭に血が上る、福子。
気っ風のよい、明るくものに動じないミキ子。
いぶし銀のような老刑事、大場茂吉。
時代を彷彿させる、山谷労働者連合会。
昭和の時代を懐かしく懐古させる当時の雰囲気。
大変面白く、懐かしく読みました。
淡々とした性格の宇野寛治の犯行には、少し意外感がありました。
五十代半ばの大場茂吉は古株の刑事である。かつては捜査一課に長く所属していた。
大場は昌夫を睨み据えて言う。見るからに昔気質の刑事で、浅黒い顔には深い皺が刻まれていた。
「熱海はホシがよく逃げ込むんだ。不思議なもんでな。東京で金を手にした犯人は、みんな判で押したように熱海の温泉に行きやがる。そんなもんだから、おれも何回か熱海に足を運ぶうちに、熱海の刑事たちとも懇意になったわけさ」
品川を通過すると、線路帯が急に広くなった。何台ものブルドーザーがうなりを上げ、ヘルメットを被った大勢の人夫がつるはしを振るっている。その規模の大きさに昌夫は唖然として眺めながら、ああ新幹線工事なのかと納得した。東海道新幹線の開通は来年秋で、今から一年後は、ちょうど東京オリンピックの開催期間である。
蛍光灯が一本だけ灯ったままの天井を見上げ、じっとしていたところ。すぐに睡魔がやって来て、寛治は目を閉じた。気づいたときは明るかったので、よく眠れたのだろう。北海道でも留置場を経験していたので、緊張することもなかった。何よりも寒くないというのがいい。東京はやっぱり住みやすい。
「それもおれは知らん。ただし刑期を終えた人間は、たいてい地元に戻るものだがな。土地勘がないと怖いんだろう。犯罪をすると飛ぶくせに、終わると戻って来る。犯罪者は気が小さいんだよ」
横丁カフェ 『罪の轍』 奥田英朗
『 罪の轍/奥田英朗/新潮社 』
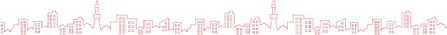
東京オリンピック 1964年(昭和39年)10月10日
吉展ちゃん事件 1963年3月31日
吉展ちゃん誘拐殺人事件
ぼくの少年時代に起こった、全国を震撼させた大事件。
事件の記憶は、ある。 だが、犯人は誰だったのか、全然覚えていない。
犯人逮捕まで、少し間があったせいかもしれないが。
そこで、本田靖春の 『誘拐』 を読んでみた。
解説 貧しきものたちへの視線 鎌田慧
このドキュメントでは、小原保が証拠不十分で逃げ切ろうとする寸前に、捜査陣を一新して自供に追い込んだ刑事の執念が描かれている。テーマも事件解決にむかう息詰まるような、スリリングな人間ドラマにおかれているのだが、それを越えて普遍性があるのは、貧しいものたちが、ささやかな欲望のために破滅に迫いやられる、その拙ない人生に、著者の思いが託されているからてある。
小原が誘拐を思い立った、という黒沢明の「天国と地獄」の身代金は、三千万円である。ところが、小原の要求は、五十万円でしかなかった。......
この金額は、すべて小原の借金の返済に消えた。いわば、借金の返済に行き詰まった末の凶行といえる。小原は五十万円を強奪したあと、せっせと返済にまわってあるいている。なんと律儀でいじましい犯罪者なのであろう。
1964年当時と比べると捜査で使われる科学技術や都市環境など、想像できないほどの進歩をとげている。しかし、どんなに時代が進もうとも変わらないものが、人々の生活のなかに厳然として存在する。
このドキュメントを読んで、考えさせられたことがある。
他人に対する過剰なまでのお節だ。
なぜ、そっとしておいてあげることが出来ないのか。
いたずら電話は、春が過ぎ、夏が来て、秋になっても、一向に跡を絶たず、日に三、四回はきまって彼らの心を乱した。
その堀も一課暮し三十年を越えて、髪は白く、最ベテランになってしまった。
手元に残る一冊の古びた大学ノートに、彼の半生が凝縮されてある。事件を手掛けるたび、堀はそのノートに、捜査の概略を細い字で記して来た。解決したものには、末尾に犯人の氏名が朱で書いてある。そのほとんどが、いわゆるコロシであり、彼は戦後の大事件にあらかたかかわって来た。
人が人を殺す。あるいは、人が人に殺される。これ以上ない異常の中に自分の日常を置いて、ノートの余白を埋めて行くごとに、堀の内側で深まる思いがあった。
動機ある殺人といわれるものを堀から見れば、被害者には「くるべきものが来た」のであって、彼は「殺されて当然」の人間なのである。そうとしか受け取りようのない事例を、堀はあまりにも多く見過ぎた。そして、それをいうときの心情は、はっきり殺人者の側に傾いている。......
畢竟、人間というやつは、他のだれかを圧迫しないと生きられない存在なのであって、犯罪者というのは、社会的に追いつめられてしまった弱者の代名詞ではないか。
捜査一課で三十年を費やして、堀が得たものといえば、そういう考え方であった。
後に平塚は、そのときの心境をサンケイ新聞社会部の佐々木嘉信にこう語っている。
その意図ってのはな、幹部はいつでも出来上ったもの(捜査報告書)ばかりいただいてる。つまり、机上と現場はピタリ一致していねえってことだ。
そうだろう、幹部には張込みのデカがつかまった話なんか伝わってねえ。完璧な布陣だってことになって報告されたわけよ。おれが組織捜査が嫌いだってのは、現場の意見がまっすぐ上に届かねえで、途中でひん曲って伝わることが多いからだよ、組織ってのは。
ついでにいっちまえば、組織にのっかると肝腎のホシ(犯人)を追うのを忘れて、肩のホシ(階級)ばっかり増やすことを考えるのさ。デカが肩のホシを追うようになったら、おしまいさ。この気持、わかるだろう。
私は十六年間の新聞社勤めの大半を社会部記者として過ごした。そして、その歳月は、犯罪の二文字で片付けられる多くが、社会の暗部に根ざした病理現象であり、犯罪者というのは、しばしば社会的弱者と同義語であることを私に教えた。
もとより新聞は「法と秩序」を否定するものではないが、記者に与えられた役割りは、捜査員の職務とはおのずから別物である。
「鹿を追う猟師山を見ず」のたとえは平凡に過ぎようが、かつての私を含めて、事件報道にたずさわる記者たちにそのきらいがあったことを否めない。
社会が多様化すればするほど、問題の所在も複雑多岐にわたる。......こういう時代こそ......事件をより広い視野でトータルに捉え、そこにからまる問題を深く掘り下げ、社会全般にわたる関心事として受け手に渡す作業が、記者の一人一人に求められているはずである。
小原保の辞世の短歌
世をあとにいま逝くわれに花びらを降らすか門の若き枇杷の木
『 本田靖春集1 誘拐/旬報社 』














