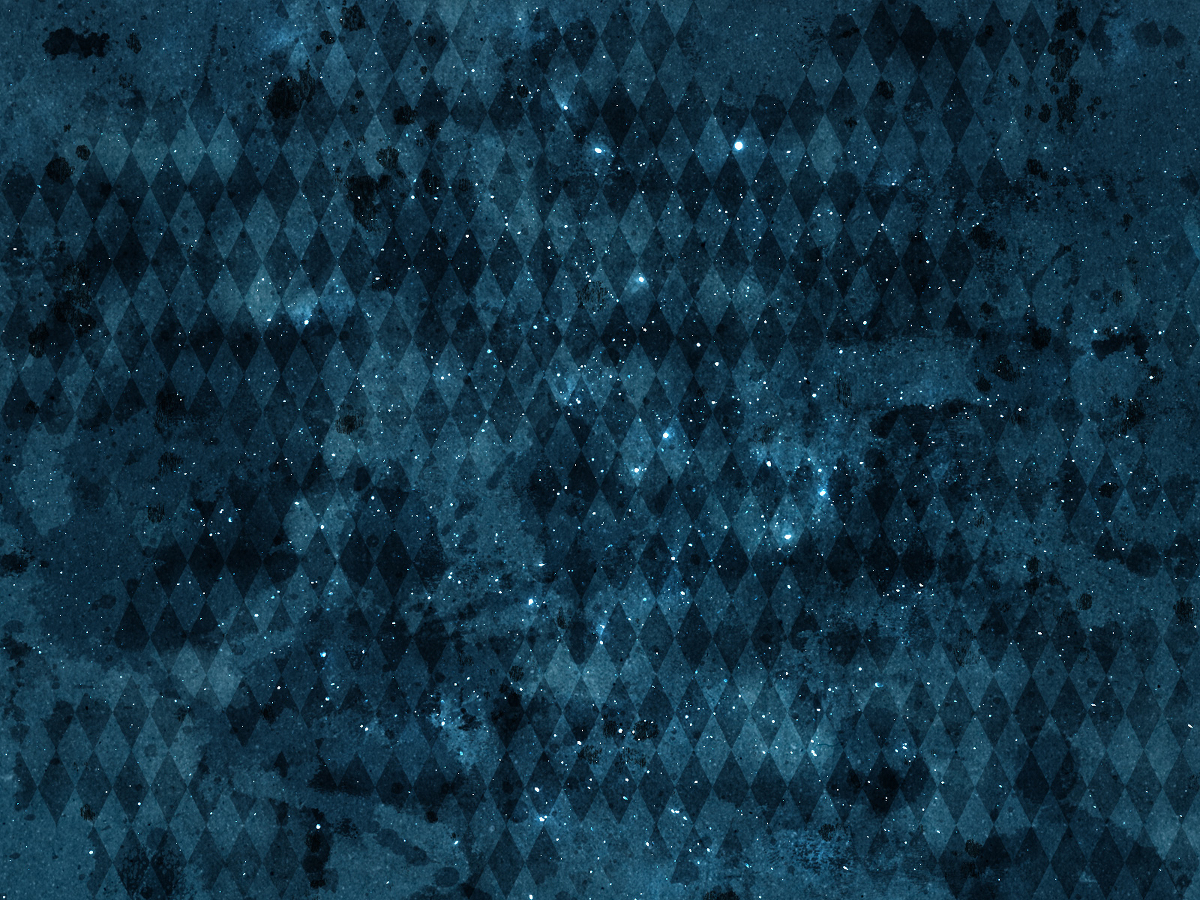
素材は、めばる様からお借りしました。
「天上の愛地上の恋」二次小説です。
作者様・出版社様とは一切関係ありません。
二次創作・BLが苦手な方はご注意ください。
しんしんと、静かに雪が降り始める音を聞きながら、アルフレート=フェリックスは宝石のような美しい翠の瞳を開け、ベッドから出ようとした。
しかし、隣で寝ているルドルフに、シーツの海の中へと引き摺り込まれた。
「まだ寝てろ。」
「いけません。」
金褐色の彼の髪が、アルフレートの胸元をくすぐり、アルフレートは思わず笑ってしまった。
「さてと、わたしはもう行きますからね。」
「一緒に居てくれないのか、お兄様?」
ルドルフは、少し拗ねたような顔をした後、アルフレートの唇を塞いだ。
「もう・・」
アルフレートは、そっとルドルフを自分の前から押し退けると、寝室から出た。
(相変わらず、お兄様は厳しいな・・)
ルドルフは溜息を吐きながら、恋人の温もりが残るシーツの海の中へと再び潜った。
「アルフレート、おはよう。」
「おはようございます。」
自宅を出てバスに乗って職場に出勤したアルフレートは、今ルドルフがどうしているのかと思いながら、仕事に集中した。
「ふぅ・・」
この北の大地に来て早5年、全てを捨ててここに来て右も左もわからずに居た頃から漸く地に足の着いた暮らしを送れるようになった。
「そのお弁当、ご自分で作ったんですか?」
「はい・・上手く作れたかどうか不安なのですが・・おひとつ、如何ですか?」
「いいんですか!?」
「どうぞ。」
同僚達とアルフレートがランチを囲んでいる頃、ルドルフは漸くシーツの海から抜け出し、浴室でシャワーを浴びた後、アルフレートが作った朝食を食べ、彼が作った弁当を持って大学へと向かった。
(寒いな。まるで、“あの日”のような寒さだ。)
白い息を吐きながら、ルドルフは、“あの日”―自分が“死んだ”日の事を思い出してしまった。
ドイツの陰謀に踊らされ、オーストリアの皇太子であったルドルフは、年端のいかない哀れな小娘を道連れに死を選ぶ―筈だった。
ルドルフの口から真実を知った哀れな小娘―マリーは、自分で頭を撃ち抜いて死んだ。
『さぁ、この引き金を引けば全てが終わる。』
忌まわしい声がルドルフの耳元で死を唆した時、最愛の天使が自分の元に戻って来てくれた。
―わたしの地上の神は、あなたです、ルドルフ様。
ルドルフは天使の腕の中で、正気を失った。
再び彼が“目覚めた”のは、南米のコーヒー農場が軌道に乗り始めた頃だった。
―ただいま、アルフレート。
―お帰りなさい、ルドルフ様。
南米で、ルドルフはアルフレートと共に、ハプスブルク帝国の終焉を見届けた後、彼に看取られながら穏やかに息を引き取った。
―アルフレート、また会おう。その時は、ずっと一緒だ。
―はい。
天の神か黄泉の帝王の計らいなのかはわからないが、ルドルフとアルフレートは転生し、互いの星が瞬き合うかのように、再び巡り会った。
「アルフレート、ご挨拶なさい。こちらがあなたの腹違いの弟よ。」
「は、はじめまして・・」
アルフレートと“再会”したのは、彼の両親の葬儀の席だった。
彼の、宝石のような美しい翠の瞳に見つめられた時、ルドルフは堪らず彼を抱き締め、涙を流した。
ルドルフの反応に周囲は慌てふためいたが、アルフレートだけは彼に慈愛に満ちた笑みを浮かべ、彼の耳元でこう囁いた。
「今度は、絶対にあなた様の手を離しませんから。」
それはルドルフが9歳、アルフレートが12歳の時だった。
前世ではすれ違いばかりで、互いに傷つけ合ってばかりだったから、転生した二人は、ウィーンから遠く離れた日本で、徐々に愛を育み合っていった。
そんな二人に転機が訪れたのは、ルドルフが、アルフレートが通う中高一貫の男子校に入学した時だった。
ルドルフを、突然病魔が襲ったのだった。
















