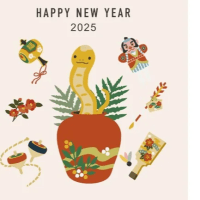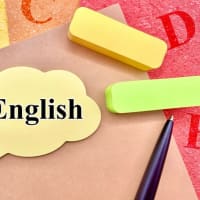前回書いた本の続きの話になるが、
作家夏目漱石がデビュー作『吾輩は猫である』を1905年1月1日に雑誌「ホトヽギス」に発表して有名になってもまだしばらくは現在の東大や当時の一高で英語を教えていた。
というのも、漱石は2年間の官費留学(ロンドンへ)の代償で1907年の3月まで教えなければならない義務があったのと東大と一高から合わせて1500円の給料をもらっていたがその金がないと生活に困るからであった。
しかし、『坊っちゃん』により名声が高まると、東京朝日新聞社が月給200円という高給を提示し、1907年3月で教壇をさることになった。
漱石は、留学前に熊本の五高でも教鞭をとっていたらしいが、当時はとても厳しい教え方で予習してこないと生徒を大変叱ったようである。しかし、帰国後は温和な授業だったらしい。また、教え子に就職の世話などもよくしたらしい。
そんな漱石が一番気にしていたのは、「英会話力の低下」ということで、
英会話力が20年前より低下したのは教師に外国人をあまり使わないのと教科書の英語をそのまま暗唱することが行われなくなったことが原因としている。
そして、「会話は学問ではなく技術だから、反復練習以外に修練できない」と言っている。
さて、堅い話はこれくらいにして、タイトルの髭のことであるが、よく出てくる漱石の髭のような鼻の下で大きく左右に広がっている髭は「カイゼル髭」と呼ぶらしい。
呼称の由来はドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世がこの髭をたくわえていたことからそう呼ばれるようになったようで、当時のはやりだったそうだ。
はやりと言えば、「ハイカラ」という今や死語に近くなった言葉があるが、当時の漱石も高い襟(highcollar)の服を着ていたらしい。(ハイカラと聞いて今の世代はハイボールと唐揚げを想像するらしい(笑))
その他この本で知ったこととして、書いておきたいのは、
1 16歳の時、夏目漱石(旧千円札の肖像)は新渡戸稲造(旧五千円札の肖像)と同じ学校で隣の席にいたことがある。
2 漱石が東大の講師になる前任者はラフカディオハーン(小泉八雲)だった。
3 漱石は芥川龍之介の『鼻』を絶賛したが、龍之介は漱石の弟子で1年間くらい交流があった。
4 その龍之介も生計のために英語教師をした時期が2年以上あり、大阪毎日新聞に入社したこともある。
ということである(以上、間違っていたら、ごめんなさい)
あ、それから、漱石には鏡子夫人との間に3人の子供がいて純一と伸六という男の子と筆子という女の子がいたということである。(筆子さんて最近私が紹介した本の作者と同じ名前でびっくりしました。)