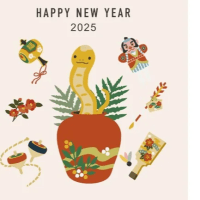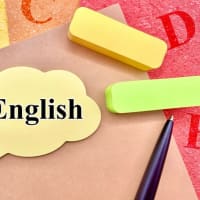勇壮に練り込み 島ヶ原・正月堂の「修正会」
今年も2月11日、快晴のもと、正月堂で修正会(地元では「せきのと」、または「えしき」と呼ぶ)が行われたので、見に行ってきた。
 (正月堂本堂)
(正月堂本堂)
この行事は752年(天平勝宝4年)から、実に1260年以上続けられている行事で、東大寺二月堂の修二会に先駆けて行われるものである。
 (鬼頭を本堂へ運ぶ様子)
(鬼頭を本堂へ運ぶ様子)
 (本尊の前に勢揃いしたお供えもの)
(本尊の前に勢揃いしたお供えもの)
この行事では、シュロの皮で作ったこの鬼頭以外に1枚8kg程度(昔は20kg)もある大きな餅を5枚、サクラの木におもちを飾り付けた成花(なりばな)、いばり栗、五枝の松、衣巻き、俵など、本堂に安置されている33年に一度の御開帳である本尊十一面観音(この御開帳については、昨年11月の私のブログ参照)に供えるものがたくさんある。
実は、このお供え物を準備するのが大変なのだ。
このお供え物は本来○○方とか××堂などと呼ばれる組(昔は20~30軒くらいで構成)で1年かけて準備をする。
例えば、一番見つけるのが難しいのが成花に使う桜の木。
大きさや形がある程度決まっているのである。松や栗の木も形が決まっていてなかなか見つからない。
また、さきほど紹介した大きな餅(「だいひょう」という)も簡単にできるものでなく、正式には千本杵でつく。
今では機械でついているところがほとんどだが、それでも1回の餅では量が足りないので、大きな器(桶がわという)に入れて併せて作る。
また、それぞれの木には半紙などで飾りもつけるし、鬼の頭(「おにがしら」という)には角がにんじん、耳が大根、鼻と口が栗、目はみかんなど決まっている。それぞれの鬼の顔は全て違う。
更に細かいことを言えば、いばり栗にはつばめの飾り(たぶん夫婦円満・子孫繁栄を願う)もついているはず。
こうした準備が大変なことから近年、正式な組がどんどんなくなり、今では伝統の名前を残すところは3つになってしまった。
しかし、写真で見ればわかるように今でも7つある。
新しくできた4つは有志が集まって作っているものである。
また、全ての奉納が終わった後とお昼過ぎにここ12年続いている餅まきがある。
 (餅まきの様子)
(餅まきの様子)
私もこの餅作りに少し参加した。合計2000個以上(1回で1000個ほど)まくのだが、人が多くて1つも拾えなかった。
この餅まきの餅をつくるのも有志である。餅をついて丸めるのと、袋詰めを別々の日で行うのだが、これもなかなか大変である。
以上、この行事を単に見に来ただけではわからないことを解説したが、このことを参考に見てもらいたい。
youtubeのものは3年前のものなどで、今年とは少し違うが、ほぼ同じである。
また、この儀式は2月11日だけでは終わらず、翌12日にも午後からほらいがいを吹いて五体投地で祈りを捧げ、水天と火天による韃靼の業法などがある。
別のyoutubeで見てもらいたい。
また、この儀式の古来のものも次のサイトでアップされているので見ていただきたい。(「修正会を守る人々」というタイトルのもの)
どうしても、うまくリンクできませんでした。恐れ入りますが、グーグル等で「地域文化資産 正月堂」で検索してください。
誠に神聖かつ伝統を守るのが大変な行事だと言うことがわかってもらえると思います。
このビデオは30年くらい前まで続いていたものを20年くらい前に正式に再現した物で、
私(ブログ作者)もちょこっと登場しています。
今年も2月11日、快晴のもと、正月堂で修正会(地元では「せきのと」、または「えしき」と呼ぶ)が行われたので、見に行ってきた。
 (正月堂本堂)
(正月堂本堂)この行事は752年(天平勝宝4年)から、実に1260年以上続けられている行事で、東大寺二月堂の修二会に先駆けて行われるものである。
 (鬼頭を本堂へ運ぶ様子)
(鬼頭を本堂へ運ぶ様子) (本尊の前に勢揃いしたお供えもの)
(本尊の前に勢揃いしたお供えもの)この行事では、シュロの皮で作ったこの鬼頭以外に1枚8kg程度(昔は20kg)もある大きな餅を5枚、サクラの木におもちを飾り付けた成花(なりばな)、いばり栗、五枝の松、衣巻き、俵など、本堂に安置されている33年に一度の御開帳である本尊十一面観音(この御開帳については、昨年11月の私のブログ参照)に供えるものがたくさんある。
実は、このお供え物を準備するのが大変なのだ。
このお供え物は本来○○方とか××堂などと呼ばれる組(昔は20~30軒くらいで構成)で1年かけて準備をする。
例えば、一番見つけるのが難しいのが成花に使う桜の木。
大きさや形がある程度決まっているのである。松や栗の木も形が決まっていてなかなか見つからない。
また、さきほど紹介した大きな餅(「だいひょう」という)も簡単にできるものでなく、正式には千本杵でつく。
今では機械でついているところがほとんどだが、それでも1回の餅では量が足りないので、大きな器(桶がわという)に入れて併せて作る。
また、それぞれの木には半紙などで飾りもつけるし、鬼の頭(「おにがしら」という)には角がにんじん、耳が大根、鼻と口が栗、目はみかんなど決まっている。それぞれの鬼の顔は全て違う。
更に細かいことを言えば、いばり栗にはつばめの飾り(たぶん夫婦円満・子孫繁栄を願う)もついているはず。
こうした準備が大変なことから近年、正式な組がどんどんなくなり、今では伝統の名前を残すところは3つになってしまった。
しかし、写真で見ればわかるように今でも7つある。
新しくできた4つは有志が集まって作っているものである。
また、全ての奉納が終わった後とお昼過ぎにここ12年続いている餅まきがある。
 (餅まきの様子)
(餅まきの様子)私もこの餅作りに少し参加した。合計2000個以上(1回で1000個ほど)まくのだが、人が多くて1つも拾えなかった。
この餅まきの餅をつくるのも有志である。餅をついて丸めるのと、袋詰めを別々の日で行うのだが、これもなかなか大変である。
以上、この行事を単に見に来ただけではわからないことを解説したが、このことを参考に見てもらいたい。
youtubeのものは3年前のものなどで、今年とは少し違うが、ほぼ同じである。
また、この儀式は2月11日だけでは終わらず、翌12日にも午後からほらいがいを吹いて五体投地で祈りを捧げ、水天と火天による韃靼の業法などがある。
別のyoutubeで見てもらいたい。
また、この儀式の古来のものも次のサイトでアップされているので見ていただきたい。(「修正会を守る人々」というタイトルのもの)
どうしても、うまくリンクできませんでした。恐れ入りますが、グーグル等で「地域文化資産 正月堂」で検索してください。
誠に神聖かつ伝統を守るのが大変な行事だと言うことがわかってもらえると思います。
このビデオは30年くらい前まで続いていたものを20年くらい前に正式に再現した物で、
私(ブログ作者)もちょこっと登場しています。