2021/10/14(木) 22:40
>宇宙の過去が無限にあるということが、物理的に何を意味しているのかも、まだよくわかりません。
>とはいえ、宇宙に始まりがないということは、少なくとも数学的には可能なことなのです。
時間と空間の起源
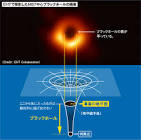
宇宙はビッグバンによって始まり、それ以前は「無」だったというのが現在の定説となっています。
けれど、もしかしたら私たちの宇宙は常に存在していて始まりはなかった可能性が、新たな量子重力理論によって示されました。
イギリス・リバプール大学(University of Liverpool)の研究チームは、因果集合理論(causal set theory)と呼ばれる量子重力の新しい理論を使い、宇宙の始まりについて計算したところ、宇宙に始まりはなく無限の過去に常に存在していたという結果を得ました。
この結果に従うと、ビッグバンは宇宙が遂げた最近の進化の1つでしかないということになります。
この研究成果は、9月24日にプレプリントサーバー『arXiv』で公開された論文に掲載されています。
物理学が未だに説明できていない問題
現在、物理学にはまったく異なる2つの理論が存在し、どちらも大きな成功を収めています。
その2つの理論とは、量子力学と一般相対性理論です。
量子力学は、自然界を支配する4つの基本的な力のうち、3つの力(電磁気力、弱い力、強い力)を微小な世界で記述することに成功しました。
ただ、重力についてはまだうまく説明することができていません。
一方、一般相対性理論は、これまで考案された中でもっとも強力で完全な重力の記述方法です。
しかし、一般相対性理論にも不完全な部分があり、この世界で2つのポイントについてだけ理論が破綻しています。
それが「ブラックホールの中心」と「宇宙の始まり」です。
ここについては、一般相対性理論でも計算が破綻してしまい、信頼できる結果を得ることができません。
そのため、これらの領域は「特異点」と呼ばれていて、現状の物理理論が及ばない時空のスポットとされています。
これは、一般相対性理論が数学的につまづいているポイントでもあります。
この2つの特異点で、一般相対性理論がうまく機能しない理由は、この場所では重力が非常に小さなスケールで非常に強くなっているためです。
一般相対性理論はマクロな世界を記述する古典物理学の理論のため、微視的な世界の重力をうまく取り扱うことはできていません。
一般相対性理論は重力を時空の曲率として表現しています。
投げたボールが地面に落ちるのは、地球が歪めた空間に沿って、ボールが軌跡を曲げ、それが地面と交わるためです。
しかしあまりに微視的な世界では、空間が歪むだけでは重力を記述できません。アインシュタインも生涯この問題に悩んでいました。
そのため、この微視的な世界の強い重力を記述するための新しい理論が必要となります。
そこで、現在考えられているのが「量子重力理論」です。
ただこの理論も「超ひも理論」や「ループ量子重力」など、さまざまな候補が存在していますが、まだ完成されていません。
しかし、そのすべてが同じような方向から問題のアプローチをかけています。
それが「時間と空間というものがなぜ存在するのか?」「どこから生じているのか?」「そもそも時空のもっとも基本的な構造とはなんなのか?」ということです。
量子重力理論を考えたとき、いずれの候補理論も、時間と空間がもっと根本的な何かから生じているということを考慮しないとうまく話が進まないのです。
そして、この疑問に対処する、新しいアプローチが登場しています。
それが「因果集合理論」です。
時間と空間とはなんなのか?
今回の研究チームの一人、英国リバプール大学の物理学者ブルーノ・ベントー氏は時間の本質について研究を行っています。
彼は宇宙の始まりを考えるという今回の研究において、「因果集合理論」と呼ばれるものを採用しました。
あまり聞き馴染みのない理論ですが、「因果集合理論」とはどのような理論でしょうか?
現在の物理学では、時間や空間はなめらかに連続した布のようなものとして捉えられています。
こうした連続した時空では、2つの点は空間的に可能な限り近くに存在し、2つの事象は時間的に可能な限り近くで発生します。
しかし、「因果集合理論」では空間と時間をなめらかな連続につながったものとは考えていません。
この理論では、時空を極限まで分解していくと原子のような離散的(飛び飛びの値で変化する)な塊になると解釈しています。
つまり、時空には最小の基本単位が存在するというのです。
"映像が小さな画素の集合であるように、時空間も最小単位が因果で結ばれた集合かもしれない"
;映像が小さな画素の集合であるように、時空間も最小単位が因果で結ばれた集合かもしれない
今この記事を読んでいる画面も、なめらかな一枚の画像に見えるでしょうが、当然虫眼鏡などで拡大すれば、それは小さな1ピクセルの画素が並んでいるものだとわかります。
空間も同様に分割されていて、その最小単位以上にはお互い近づくことができないかもしれないというのです。
この考え方の何が重要なのかというと、この理論に従った場合、ビッグバンやブラックホールのような特異点の問題がきれいに取り除くことができるからです。
なぜなら、この理論では時空を無限に小さく圧縮することが不可能だからです。
時空には最小単位の「時空の原子」があり、その大きさを超えて小さくなることはありえないため、特異点が存在しなくなるのです。
では、ビッグバンに特異点がない場合、宇宙の始まりはどのようなものになるのでしょうか?
ビッグバンは通過点に過ぎない
ベントー氏は、因果集合理論が宇宙の最初の瞬間をどのように表現するか、インペリアル・カレッジ・ロンドンのスタブ・ザレル氏と共同で研究を勧めました。
従来の因果集合理論では、因果集合は無から生じて現在の宇宙まで成長したとされています。
しかし、彼らは、そもそも因果集合に始まりが必要かどうかということを検討しました。
すると、彼らの研究では、因果集合は過去に向かって無限に続き、常に前に何かがある状態となり、ビッグバンという始まりは存在しないことがわかったのです。
彼らの理論によれば、私たちがビッグバンと認識しているものは、この常に存在する因果集合の進化における特定の瞬間に過ぎず、真の始まりではなかった可能性があるとのこと。
ただ、この理論はまだ少数の物理学者が注目する理論でしかなく、論文も査読付き科学雑誌への掲載はまだ決まっていません。
宇宙の過去が無限にあるということが、物理的に何を意味しているのかも、まだよくわかりません。
とはいえ、宇宙に始まりがないということは、少なくとも数学的には可能なことなのです。


























