
■■■■■■■NPOに明日はあるのか?■■■■■■■
■「難しい局面」
●高齢者人口 3350万人、日本は4人に1人が老人という 世界
に冠たる超高齢国家である。 かく言う私もその一人である。
そしていま、そのシニアの大半が退職したとはいえ、ひとりひとり
の去就が、わが国の命運を左右することになる。



■「衝撃の現実」
それを裏ずける新聞や経済誌の衝撃的な見出しがある。
・「65歳定年の衝撃」 (週刊東洋経済)
・「社会保障の国民負担率4割に」
・「老後の3大不安」、(お金、健康、生きがいは、みつかるか)
・「リタイア後の生きがい」
・「金持ち老後、貧乏老後」 (ビンボウ家計簿調査)
・「老後を豊かに」 野村がセミナー
・「眠る1700兆資産を生かす狙い」
・「個人対象の証券セミナー」 続々
・「シニア消費100兆円」 日本の全体消費の4割を占める。
・「シニア消費の実態」 女性はひとりで 男性は夫婦で
・「消費、団塊特需の兆し」 シニア依存が一段と高まる。
・「中高年 消費の主役」 (コンビ二、ネット通販、海外旅行)、
・「シニア向け大型店全国100店」 習い事の発表会 イオンの戦略
・「シルバー株上昇」 元気な消費を取り込め。
・「今の70歳は、昔の49歳」
・「終活できず、最後の安心」(遺影撮影3万円)
・「未来の年表」、河合雅司著(講談社現代新書)
・2021年 介護離職が大量発生、
・2024年 3人に1人が65歳以上の超高齢者大国へ
・2026年、認知症患者が700万人に
・深刻な火葬場不足に 死亡者129万人、40年には167万人
・「老人世代、引退にはまだ早い」 曽野綾子著
・「プラチナ世代の生き方」 渡辺淳一著
・「定年後、50歳からの生き方、終わり方」 楠木新著(中公新書)


■「退職シニアの動向」
●65歳まで雇用延長を企業に義務付ける 「高年令者雇用安定法」
の改正が、一昨年4月に決まった。
之によって、戦後の日本企業の就業形態が大きく変わることになる。
本来なら定年後ゆっくり余後をすごすはずの定年前世代の人たち
が、いつになく、退職後の居場所を求めて動き始めた。
●「日経新聞のシニア世代1千人調査」によると、定年後男性シニア
3人に1人が「地域貢献」 4人に1人が「社会貢献」したいという。
但し、内容を精査すると、既存のNPOなどに参加して地域貢献した
り、社会貢献するという 定年後の自分の居場所ずくりのための「腰
掛け的参加」が多いのが気に懸かる。
17年前のNPO発足当時の起業型シニアの人たちとは いささか
意気込みが違うし、迫力にも欠ける。
■「NPOの誕生」
●NPOが法制化されたのは、今から19年前の1998年のこと。
阪神大震災から5年を経て、社会事業法制の不備と、社会貢献事業
の活性化が叫ばれていた。
おりしも経済界の起業ブームもあって、心ある定年シニアの人たちは、
国際交流や地域活性化のために、こぞって同志を募り、社会貢献事
業の研究会を開き、NPOの法制化の実現を待って NPOを立ち上げ
た。、
私どものNPO 日タイ国際交流推進機構(JTIRO)も、全く同じ思いで
産声を上げたNPO団体の先駆けである。
1998年は、日本のボランティア元年というにふさわしい素晴らしい年
だったと記憶している。


■ 「タイの寄進扶助文化に学ぶ」
●仏教国タイには、タムブン(托鉢)という伝統的な相互扶助の文化が
ある。そのタンブンの主な教条にはーーー、
・まず隣人を助ける心、
・困った人に手を差し伸べる心。
●社会貢献事業に詳しい識者の話によると、ーーーー
ベトナム戦争の傷病兵の看護を受け入れたタイ王国での出来事。
チェンマイでの毎朝の托鉢をみて感動した米国の傷病兵が帰国した
後、民間人として、世界の隣人を助けるためのNPOを発想提起して、
後にその思潮が日本にももたらされ、NPOの法制化が実現したという。
余り知られていない事実だが、NPOの原点がチェンマイの托鉢だった
とは、日タイの奇しき因縁を感じる。
■「高齢化するNPO」
●NPOの発足から19年、NPO起業のシニアたちは こぞって高齢化
したが、総じて後継者が育たず組織は成熟化して、活動は低迷した。
●途中2007年には、団塊世代700万人の退職期が到来し,その受け
皿として NPOが脚光を浴びたが、その退職期が延期されたために
巨大プロジェクト自体が後退し、NPOへの期待は不発に終つた。
そして2012年、再び団塊世代によるNPO活性化の動きがあったが、
初の民主党政権下で、景気が低迷したため、これまた不発に終わっ
た苦い経緯がある。。
●健闘するNPO団体の代表に、最近の退職世代の動向について
聞いた。
「後継世代の団塊の人たちに期待したい事は、現職時に培った経営
経験(スキル)と、不屈の使命感だ。 しかし従来は大企業にいたという
事を標榜するだけで、その経験能力を生かして活動に貢献できる人
は極めて少なかった。
・自分から活動を買って出る人、
・持ち前の発想力で、団体の活路を拓く人、
そんな人材が欲しい。
「自分の居場所探しのためNPOに参加したり、時間つぶしのために参
加する人はもういらない」 と手厳しい。
●しかしいま、NPO団体自体も、成熟化による低迷の波に晒されようと
ている。
■「NPOの実情」(内閣府NPO認証データ)29年6月現在
(主な府県)(認証数) ( 解散数)そのうち(認証取消数)
(主な府県) 団体数 団体数 団体数
東京都 9478 3126 730
大阪府 1764 684 111
京都府 530 167 16
兵庫県 1426 434 51
(府県計) (40314)(110603) (2487)
(主な指定都市名)
大阪市 1553 436 16
京都市 845 136 0
神戸市 774 174 40
全国計 (11310) (2361)そのうち( 635)
全国総計 (51629) (13964) : (3122)
■「NPOの退潮と新しい起業動向」
●上記のデータは、内閣府が管掌するNPOの現況である。
「社会貢献のためのNPO団体が、ついに5万社を超えた」という政府
広報や、話題の新聞報道をご覧になった事があると思う。 しかし、
「NPO団体の解散が1万4千社、全体の27% 解散は過去最高」
こんなマイナス情報は、全く伝わってこなかった。
●だからNPOは、今も伸び続けているとばかり思っていたが、実情は、
この3年来、解散団体が増え続けていたことが解ってきた。
その後退の理由はーーーー、
・役員や会員の高齢化、
・進まない世代交代、
・経済環境の停滞
など、様々な要因が考えられるが、海外ロングステイ同様、大きく後退
し始めたことは否めない。
●最近の定年後シニアの起業では、NPOにとって代わって、設立手
続きや運用が簡便な社団法人が、急速に伸びている。
また起業を目指す定年後シニアの中には、敢えて資本金と法人税が
必要な株式会社を設立して 自前の発想力でブル―オーシャン(新規
市場)を目指す、いわゆる「ファーストペンギン」が増えているという。
●因みに 多彩な団体組織の起業条件を簡単に比較するとー
【種別名) (申請費用) (理事他) (資本金) (運営)
・NPO法人 ほぼ無料 最低5名程度 不要 決算を申告
・社団法人 要申請登記費用 2名から可能 不要 申告不要
・株式会社 要申請登記費用 最低役員必要 1円から可 要税務申告
●19人年前のNPOの法制化以降、政府は、経済構造の 拡大化を
目指して 起業の規制を緩和し、様々な起業形態や 簡便な手続や
運営の仕組みを導入してきた。
やる気のある人々のために、起業の規制の敷居を下げて より簡単に
し、利便性を高めてきたと言っていい。。
その反面 起業する以上 組織の形態に拘わらず 「ヒト、モノ、カネ」な
ど経営の基本理念を打ち出し、責任ある運営に当たる理事の社会的
責任を明確にしてきた。
■「なお漂流する日本社会」
●特に欧米のように宗教的な心の連鎖がない日本社会。かっての家
族制度が崩壊し、人は人、自分は自分、変な個人主義が跋扈して、
組織では、経営トップの意識の喪失が目につく。
加えて右傾化主義や、正当らしく理屈をつけて相手を追い込むフェ
イク・ニュースの台頭など、見逃せない傾向が目に余る。
●世界第3位の経済大国とは言え、いま格差は随所に広がりつつあ
る。少子高齢化、成熟化、政治不信など、純粋な人々の心まで虫ば
んできた事は確かだ。力を合わせて、人々の初心への回帰を修復せ
ざるを得まい。
■「人生百年時代をどう生きるか」
●最近100年人生時代の生き方について書かれた 英国のビジネス・
スクールのリンダ・グラットン教授の「ライフ シフト」が東洋経済新法社
から翻訳出版され大きな注目を集めている。
そのユニークな生き方の主旨は、「来るべき超高齢化社会に向けて
従来の「教育→仕事→引退」の3ステージの人生ではなく、生涯にお
ける 複数のキャリアを持つ「マルチステージの人生」を目指すべきだ
と謳う。
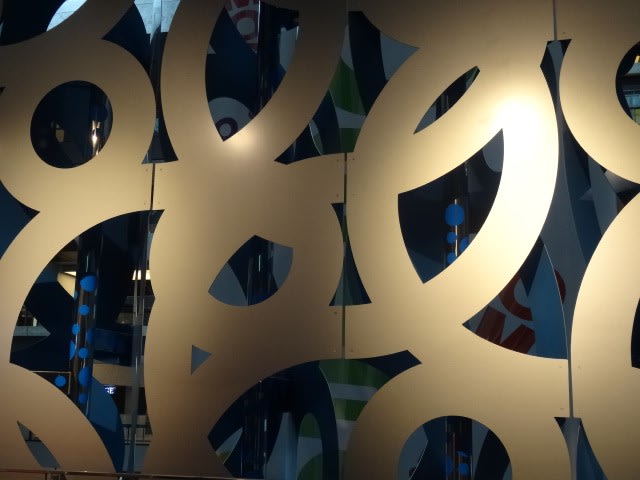
■「NPOに明日はあるのか」
●成熟化は 経済社会の常、どんなことも歳月が経過すると退化する。
グラットン教授は、余後のシニアこそ人生のリスクを感じ取って多彩な
複数の人生ステージを持つべきと指摘する。
そしてキャリアを生かす社会貢献活動は,シニアの最も適切な働き場
所であり、居場所であるという。そして、その選択の成果は、超長寿社
会をどう生き抜くかという本人の気迫が、全てを決めるという。
●日本のNPOについては、いま低迷してはいるが、 シニアの社会貢
献活動の場としては、最高の働き場所と言える。 NPOのの低迷理由
は、人為的な問題、即ち人的な運営上の欠陥が大きい。
NPO 団体5万1000の中から、1万4000団体の解散があった事は、まさ
しく厳然とした事実だが、この現実をどう読み取るかが必要だという。
●非営利のために、競争原理が働かないという 誤まった団体の経営
意識の甘さが、経済の大きな流れ(トレンド)から脱落する事例も多い。
確かに活動の成熟化もあろうが、一般企業に比べてNPOの経営能力
は、全般的に低いと言われる。
また 非営利を標榜するNPOには、金銭的なリスクが少ないから 運営
(経営)が甘くなるという説もある。
併せて人材育成の遅れから後継者が育たず、必然的に解散に追い込
まれる事例も多い
●総じて言えることだが、NPOが活性化するには、激動する経済社会
の中で、常に競合して勝ち抜いて行くという たくましい経営能力が不
可欠だろう。
だから、今回のNPOの解散の増大は、市場原理的に見て自然淘汰の
結果とみればいい。
■「NPO第2世代へ」
●社会が成熟化すればするほど、政府がいう行政ではできない分野
の社会貢献事業のニーズが増大する。 NPOを含め社会貢献団体の
活動領域は、今までになく広がる事は確かだ。
勿論、そのNPOを支えるのは人である。当然、参画する人々の意識の
変革も求められる。
出来れば、在職時代に培ったスキルを活かしてより意欲を掻き立てる
定年後の就業組織があれば、なお素晴らしい。
●選別に勝ち残った精鋭のNPO団体は、益々切磋琢磨して、本来の
力量を発揮して欲しい。一度後退を経験すると、組織は奮発して前進
する。その推進力は、やがて団体の魅力に昇華する。
●加えて、NPO団体が活性化するためには、欠かせない要件がある。
いわゆる「広報力」である。
戦後の感性消費時代を過ごしてきた団塊世代以降の新世代を対象に
するとすれば、情報や、団体イメージを含めて、時代の先端を行く、視
覚的なスマートさ(恰好良さ)が、不可欠になってくる。
一般消費市場で、差別的なイメージの市場商品が、安定的に売り上げ
を伸ばすのと、同じ考え方である。
・団体名のネーミング
・団体名のロゴタイプ
・団体の訴求媒体(ブログ&ホームページ)
・団体の印刷物、(パンフレット)
など、感性的に心なごむ、差別的な視覚表現で統一される必要がある。
加えて、先端的な情報発信力が、団体のイメージを高く確立する。
●まさに、社会貢献事業の非営利団体だから「バンカラ」でもいい時代
は去った。
高感度の感性訴求こそ、時代の先端を往くNPOのイメージ戦略そのも
のである。
●2020年のオリンピック、2015年の大阪万博など国際的な大
イベントが目白押しだが、日本の社会貢献事業のニーズは、内外とも
に格別の伸展が予測される。
●来年は、去る1998年のNPO法制施行から20年、いよいよ飛躍
のための「NPO第2世代」が始動する。NPOの輝かしい明日に期待
たい。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます