
■■■■■■■■■■■■[菜の花]■■■■■■■■■■■■
■「司馬遼太郎記念館」
●立春の日、大阪郊外 近鉄沿線小坂にある司馬遼太郎記念館を訪ねた。
暦の上ではもう春だが、まだま肌寒い冬日の午後だった。記念館の建物
は、大阪が生んだ 世界的な建築家安藤忠雄氏が 設計したコンクリ
ート討ちっ放しの白亜のたたずまいである。
通路には春を告げる菜の花が咲き誇り、それはもう見事なばかり。


(●司馬遼太郎記念館の外部と内部)
●「菜の花」は、俳句の春の季語だが、離接する書斎の前庭にも司馬さん
がこなく愛したという菜の花が咲き誇っていた。
司馬作品の題名には [菜の花の沖] 「菜の花の国」など,菜の花に因んだ
ものが多い。そして司馬さんの命日の2月12日は「菜の花忌」となずけられ、
毎年盛大な催しが開催される。


(菜の花に彩られた司馬遼太郎さんの書斎)
■「子規と真之」
●久しぶりに記念館を訪れたのは 俳人正岡子規を生涯支えた 明治の
ジャーナリストで新聞「日本」の主筆、陸羯南(くが、かつなん)(1857~
1907)の企画展を見るためだった。
●俳人芭蕉とも親しかった子規は「日本」の記者として随筆「病床六尺」を
「日本」に連載した。 そして、物心両面で子規を支え続けた陸を「これ以上
徳のある人はいない」と終生畏敬したが、その 陸の魅力を求めて、多くの
言論人や文人が集ったという。
●「まことに小さな国が 開花期をむかえようとしている」
これは、司馬遼太郎の代表作「坂の上の雲」の一節だが、愛媛県松山出身
正岡子規と 友人の秋山真之、好古兄弟を中心にして、開花期明治の日本
の全貌を事実に基いて描いた不朽の長編歴史小説の大作である。
そこでは、3人の主役を縦軸に、周辺1000人の登場人物の人生を横軸に
して、日本が近代国家に開花していく過程を描いたまさに日本史の一篇で
ある。司馬さんは、この作品を書くために40歳台の10年間を費やしたという。
●秋山真之は 日本海海戦で東郷元帥の戦艦三笠の参謀として世界最強の
ロシアバルチック艦隊を打ち破った。そして秋山真之の兄、好古は陸軍大将
として、ともに当時東洋一小国だった日本を亡国の危機から救つた。
そして子規と真之は、松山中学の幼馴染として、ともに東京大学予備門に進
み、同宿するほどの仲だったという。しかし不運にも子規は34歳で夭折する。
●通信もない、鉄道もない、開国間もない明治初期に、東京から遠く離れた
四国松山の3人の少年達が、東京をめざし、その後それぞれ道は違えど主要
な分野で、小さな国、日本の開花に尽きせぬ貢献をす事になる。まさに事実
は小説よりも奇なり。く
司馬さんは、自分の足で隠れた明治の史実を探り、世紀の感動を呼び起こす
ことに成功したのである。
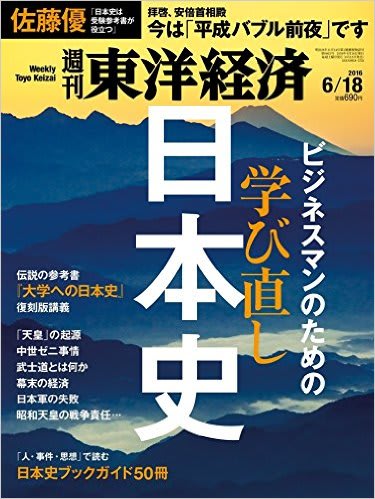

■「日本史の学び直し」
●いま日本は、空前の日本史ブームである、その背景には、ナショナリズムや
保護主義が跋扈する時代の流れのなかで、これからの世界の行方を探ろうと
する人たちが、増えているからだろうか。
いま「坂の上の雲」「竜馬が往く」など明治を拓いた人達を描く司馬作品が
改めてブームになっているのは、日本史ブームと大いに関係がありそうである。
■「日タイ修好130年の起源を探る」
●今年は、日タイ修好130年だが、司馬さんにあやかって、その当時の日本を
探ってみたい。
■「明治時代」 ■日本国の出来事」 ■「タイ国の出来事」
・明治元年(1868) ●明治と改元
●明治天皇が即位 ●(ラーマ5世即位)
・明治2年(1869) ●江戸を東京と改称 (四民平等)
・明治4年(1871) ●廃藩置県 3府72県に統合
・明治4年(1871) ●郵便制度始まる〒 久保利通ら欧米視察団
・明治5年(1872) ●義務教育、小学校(学制)
●電信、東京ー大阪開通
●太陽暦を採用
・明治6年(1873) ●徴兵令
●地租税(3%)公布
・明治10年(1877)●西郷隆盛、西南戦争起こす
・明治14年(1881)●国会開設の詔(1890年議会開催を予定)
・明治17年(1885)●内閣制度が確立
●伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任
・明治19年(1887)●東京に電灯がともる。 ●日タイ修好条約締結調印、
●日タイ国交開始
●鎖国状態の中でぺりーが来航し、初の5ケ国修好条約が締結されてから、わ
ずか15年で幕府が倒れ、明治政府が誕生。そして日本の近代化が始まった。
れから16年後には、日タイ修好条約が締結され、日タイ国交が始まる。それは
歴史に残る画期的な新しいアジアのスタートだった。


■■■■■■■■■■■「余談往来」■■■■■■■■■■■
■「小さな国のパワー」
●司馬遼太郎の偉業は、凄いの一語に尽きるが、改めて日本の明治に思い
を致たすと、やはり明治は、近代史日本の原点だといえる。
今年は、日タイ修好130年だが、何しろ鎖国が続いた日本が開国して明治に
なって・わずか5年で・務教育の小学校学制の採用・次いで陸海軍の編成、
・14年には内閣制度の発足・19には・日タイ修好条約の締結。
・そして明治22年には、ジャーナリストの陸さんが新聞「日本」を創刊、
正岡子規が記者として、文筆を奮うことになる。
●今に生きる私共が、当時のことを知るためには、文献や資料に頼るしかないが、
開国後、わずか20年足らずでタイをはじめ海外列強と国交締結が出来たという
事実は まさに奇跡というか、驚きという他ない。
司馬さんが探ったように、そこには地政学的に見た日本人の優れた英知と知恵が
あったとみていい。

■「島国の着想と好奇心」
●いつもの事ながら、海外から帰国するたびに、小さな日本の国の素晴らしさ
を実感する。 その主な理由は、なんといっても日本の地政にある。
・四囲が海である事、
・国境を接する隣国がない事、
・四季がある事、
・そして2000年の長きにわたり伝統的な単一民族国家である事、
などである。その他の利点は、枚挙にいとまがない。
●例えて外国と類推するとーーーーー
タイは素晴らしい国だが、陸地の周囲を隣国に囲まれ国境警備だけでも大変。
人口は日本の半分ながら、国境警備を含め、国防にあたる国軍(陸軍)は19万人、
日本の自衛隊(14万人)よりも、はるかに多い。
米国は素晴らしい巨大国家だが、国土は日本の25倍、人口は約2,47倍、行政
統治的にも国が大きすぎて、これまた大変である、トランプさんのご苦労も解らない
でもない。


●これらは日本の地政的な見地から見た対比事例だが、日本の利点を知らずに、
日本に暮らす日本人が、あまりにも多すぎる。
・海は宝 ・豊かな自然 ・島国の叡智 ・独創的な着想 ・日本人の好奇心
司馬さんも多くの著作で、日本の地政と日本人の素晴らしさを指摘しているが、私
たち日本人として、トランプさんとは、次元の異なる意味での 「ジャパン、フアース」
を標榜して、内外に日本の素晴らしさを、前向きに伝えていきたいと考えている。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます