
■■■■■■■■■■■■教育発達■■■■■■■■■■■■
松本光弘
・筑波大学名誉教授 ・元 日本サッカー協会理事 ・元 筑波大学蹴球部監督
■「躾(しつけ)」
●今回の内容は少々専門的になる。前回のサキの話に出てきた「躾は”つ”
の付く年齢までに終わらなければならない」。これは私の知人の小学校・
中学校の教師を長らくしていたベテラン教師が 私に教えてくれたもので
ある。
その根拠は? 多分これは彼らが教育の対象としている小・中学校の児童
生徒の発育発達を日々観察することから導き出されたものであろうと推察
する。なぜこのよう曖昧模糊とした言い方しかしないのか。これは「躾」
の内容がはっきり確実に説明できるものではないことが大きな原因と考え
る。
●私がいつも物事を考える時5W1Hがある。
いつ、どこで、だれが、何を、なぜ、どのようにして・ これを英語では
When,Where,Who,What,Why,How to となる。
これらの英語の頭文字が5W1Hである。では、躾とは何か?いつ、どこで、
だれが、なぜ行うのか?この疑問に答えるのはそう簡単ではない。
私が1973年にイランのテヘランで3カ月の期間で開催されたFIFA(国際サ
ッカー連盟)主催のアジアコーチングスクールに参加した時のことである。
イラン人の教育学の講師が開口一番いきなり「教育とは何か?」との問い
かけを私たちにしてきた。
受講生が即座に回答ができないでいると「教育とはヒトを変える事である」
と言い切った。あまりにもはっきりと断言したので私自身は圧倒された事
を覚えている。

●今回は「躾は”つ”の付く年齢までに終わらなければならない」この言葉
が意味することについて もう少し深堀したい。
子供たちが年齢とともに身体が大きくなったり、記憶力が旺盛になったり
することを「発育発達」と専門用語では言う。
では発育と発達はどこが違うのか。簡単にいってしまうと発育とは量的変
化をいい、発達とは機能的変化をいう。子供が身長が高くなる、体重が重
くなるなどは発育である。
これに対して発達はジャンプして高く跳べるようになる(走り高跳び)、
重いものが持ち上げられるようになる(重量挙げ)などは機能的変化をいう。

・ハイハイができるようになる、
・両足で立てるようになる、
・歩けるようになる、
などは発達の顕著な表れである。。
この発育と発達の間には深い関係がある。生まれたばかりの赤ちゃんは、
ほとんど動作発揮の源である筋肉を持ち合わせていない。動こうとしても
動けない。わずかにおっぱいを求める泣き声を発する筋肉か、後の身体全
体の筋肉の発育のための準備となる 手足のわずかな動きをつかさどる筋肉
しか持ち合わせていない。
これは私たちの眼では観察することができない子供たちの頭脳の中でも引
き起っているのである。筋肉、脳の他には骨、内臓、血管、リンパ、ホル
モンなど人間が成長するということは驚くべき神秘がそこには存在する。
この神秘に出会うとき私たちは生命の尊さをつくつ”く感じるのである。
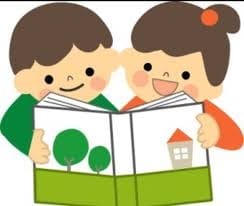
■「発育期の教育」
●この出生から大人になるまでの身体の量的変化を科学的に研究したのが
私たちが中学校や高等学校の保健の授業や理科の授業で出会う「スキャモ
ンの発育曲線」である。

(図1、スキャモンが1930年に発表した)
●これは大きく分けて
・一般型(骨格、筋肉、内臓など)、
・神経型(頭脳、神経など)、
・生殖型(ホルモン、一部器官など)、
・リンパ型(リンパ、一部器官など)
の4つに分けられている。
0歳の出生から20歳を人間の完成時と定め、その間の4つの型の量的変
化を年齢とともに測りまとめたものである。
これを見ると誕生から成人(20歳)になる過程で人間は右肩上がりに直
線的に発育していくものではないことが一目瞭然である。

●一般型いわゆる身長や体重の変化は出生とともに急激に発育し、10歳
前後で一時停滞し、その後成人に向けて一気にスパートする。
この第二次性徴期の急激な体格の変化を私たちは中学生高校生時期を中心
とした青年たちに観察する時その発育の速さと変化に驚かされるのである。

●この一般型に比較して生後間もなく急速に成人と同じレベル(100%)に
まで発育するのが神経型である。
これはその後人間が人間らしく生きる脳の発育を意味している。成人の脳
を中心とした全神経の80~90%が10歳以下で形成されるということを私た
ちはこのスキャモンの発育曲線から確認することができる。
この神経系の発育の早さは一般的な私たちの想像をはるかに超えている。

●次に誕生したての時のほとんど量的には観察できなかった生殖型の発育
曲線を見ると、”つ”の付く年齢が終わったころから急激に増加し20歳の人
間の完成時に向けて急速に大人の仲間入りをする。この生殖型が先の躾と
何か関わるような気がする。
男女の関係、俺は俺、私は私、なかなか扱いにくい年齢となる。
好き嫌い、好むと好まない、合う合わない、
フィーリング、感じ方、魅力、嫌悪、
大人の世界でもなかなかややこしい課題が多く、この年代から始まる。

●最後に残されたリンパ型がある。
これは私の独断と言っても良い説明がわかりやすい。子供は母親の体内か
ら出生する時外界で出あういろいろなウイルスや病気の原因になる要因に
対する抵抗力、すなわち抗体を持って生まれる。
この抗体は母親自身のものである。母親以外のものからは抗体をもらうこ
とはできない。この母親からもらった抗体が自身の身体の中から消えて行
き自分自身の抗体を作り出す時期が来る。この母親の抗体から自分自身の
抗体にバトンタッチするときはバトンが円滑に受け渡されないとこの間に
とてつもない病原菌などが体内に入った場合命を落とすことになる。
このバトンを受け渡す時は非常時なのである。
この非常時に備えて完成期の成人の量(100%)よりはるかに量として多
いリンパ系の物質が自分の体内に用意されるのである。
この母親の抗体とさよならし、自分自身の抗体を作り上げる時期が人生の
中で最も多くなることを如実に表しているのがリンパ系である。
くしくもこのリンパ系の出現のピークと生殖型の出現の始まりがほぼ同じ
年齢であることが非常に興味深い。自分自身の抗体を獲得することができ
た暁は今度は子孫を残すための生殖型の発育がスパートしてくる。
これまでのスキャモンの発育曲線に対する読み取りからさらに深くこれら
4つの発育の型の関係を考察したのが小野剛の図2である。

(この図にはタイトルがない。内容が複合的で表現できない)
●今回は「小野剛の発育発達曲線(1996)」と呼ぶことにする。
1996年に公表されたものである。彼はこの時すでに(財)日本サッカー
協会(以降JFAという)の育成部門の中心人物であった。1994年のアメリ
カW杯出場をドーハの悲劇で逃している。その4年後の1998年フランスW
杯にアジア予選最終戦をジョホールバルで劇的勝利を収め、見事国際サッ
カー連盟(FIFA)主催ワールドカップ・フランス大会に日本代表を初出場
させた岡田武史監督の右腕としてその能力をいかんなく発揮したのが小野
剛氏である。
この図は前述のスキャモンの発育曲線を人間の動作獲得の発育発達に焦点
を当てて詳細な分析と関連研究文献を駆使して出来上がったものである。
ここで明らかにしておかなければならないことは発育と発達の関係である。
発育は量的問題であり発達は機能的問題であることは前述した。
発育の量については長さや重さで表せるので理解できる。しかし発達の機
能的問題の具体的内容と発育との関連については・・・?
以下の説明が全てを言い尽くしているとは思わないが次のように理解して
いただきたい。量が増えるとはその機能が高度になる、あるいは増加する
と考えるのが一般的である。

●今私たちが便利に使用しているコンピュータ(以下PCという)がある。
このPCの記憶装置を2つ搭載したら記憶装置は2倍に高まる。もっと至近
な例では料理の際砂糖を2倍入れれば甘さは倍になると考えるのが自然で
ある。
この原理から考えるとスキャモンの発育曲線の量的変化は機能的変化とし
て読み取ることができる。この量的変化のわずか後を追いかけるように機
能的変化がおこってくる。ほぼ同時とみることもできる。このことからス
キャモンの発育曲線は教育学や医学にとって非常に重要な内容である。
今現在、私が抱いている感想が一つある。
スキャモンがこの研究を行った1930年は今から1世紀近い昔である。この
100年の間に子供たちの発育発達は相当な進化を遂げているはずである。
事実私たちの周りの若者はみんな背が高く、脚の長さも長い。ましてやPC
のすべてを搭載したと思われる携帯電話一台ですべてを処理する彼らの頭
脳は100年まえの頭脳とは少々異なるのではないか。今現在の一人の人間
の発育について新しい研究成果が必要な気がしているのは私だけだろうか。

●図2に話を戻す。
この図(他の図も同様)はJFA指導教本から引用したものである。背景に
3人の子供の絵が置かれている。この3人は順番に体格が右肩上がりで大
きくなっている。
しかし緑色(神経系の発達 20歳を100%とした場合)はスキャモンの発
育曲線で説明できるが水色(筋・骨格系動作習得のレディネス)は途中下
がったところがあり、赤色(脳・神経系の可塑性)は右肩が下がりっぱな
しである。この訳は何か。
●まず赤色について説明したい。ここで出てくる脳や神経の可塑性とは何
か。
この脳や神経は理解できるが可塑性についてあまりなじみがない言葉であ
る。私はこのことを説明する時陶器の制作を例にして行うのが常である。
茶碗や皿、あるいは高価な茶道の器などさまざまである。


この陶器は最初土を水に溶かしどろどろの状態から出発する。この粘土の
水分が蒸発しいよいよ作ろうとする器の形を整える段階になる。
この時は作ろうとする器を変更することもできる。
その訳は粘土はまだ柔らかくどのようにでも変えることができる状態であ
る。この柔らかさを可塑と表現する。形を変えることが可能である状態と
言えばよいだろう。
柔軟で何にでも順応する。どのような形にでも変化する。この最たるもの
は「水」である。そのため水は多くの場面で哲学的意味合いで引用される
ことが多い。この可塑性は子供が誕生した時が最も柔らかく年齢が経過す
るにしたがってその柔らかさは喪失してくる。陶器作成工程では目的とす
る器の形を粘土が柔らかいうちに作り上げなければならない。
●一旦作り上げた器は形を変えることはもうできなくなる。
その後の陶器作りは、乾燥、釜炒れ、加熱、冷却、絵付け、と進んでいく。
これを人間の発達に置き換えれば、神経系の顕著な例はその子供の言語の
発達である。
言葉を覚え話す。これはとてつもない人間固有の能力である。それも日本
で育った子供は日本語を話し、中国で育った子供は中国語を話し、イギリ
スで育った子供は英語を話す。
この言語は神経系の可塑性が高い柔軟なときに獲得されるものである。
その国の言語という環境が子供たちの言語形成という、陶器で言えば器の
形を造り上げる時である。このように考えるとこの可塑性が高い時期に多
くのことを学ばせることが重要であると考えるのは当然である。
しかしすべてを早期に獲得させることができるかというとそうはいかない。
なぜなら神経系が最も柔軟な誕生直後は脳の発育発達も動作の根源である
筋肉も発育発達はほとんどしてない。
特に動作習得のもとである筋・骨格系の発育発達はハイハイから始まり、
伝わり歩き、二足歩行、そして駆けっこ、ジャンケンこ、鬼ごっこ、跳び、
転び、相手を追いかけ、相手から逃げるなどの動作となる。そのうちにあ
りとあらゆる動作を習得していく。この時自転車や一輪車の乗りこなしは
興味深い。

●可塑性が下がっていく過程で最も高いレベルにあって筋・骨格系が発育
(発達)してくる時期、それは10歳前後である。この年齢の特定は非常に
微妙であり重要である。
前回のトレーニングの5原則で解説した個別性の原理が大きなウエイトを
占める。個々の子供によって大きな違いがあるからだ。この個々の子供の
特性は早熟・晩熟の表現で理解できるはずである。他人と比較なさるな!
とよくテレビの中の教育者は言う。
●これは子供にとって最も重要な時期、神経系の発育発達が十分であり、
脳・神経系の可塑性(柔らかさ)がまだ十分残っていて、筋・骨格系が動
作習得に十分な発育発達に達した時、この時が子供たちの動作習得に最も
適した時期、専門用語ではレディネス(用意充分時期!準備万端時期!)
あるいは臨界期と呼ばれている。子供の身長、体重、身体を支配する筋肉、
その筋肉に命令する神経回路、それらがすべて一気に最高の成果をもたら
す時期、これを小野剛氏はゴールデンエイジと呼び現在スポーツ界で選手
育成では非常に重要な言葉となっている。

この根拠となる運動学の裏付けは私たちの大先輩であり大先生でもある金
子明友(筑波大学名誉教授)先生が旧東ドイツの運動学者クルト・マイネ
ルの理論書を 日本語に訳したスポーツ運動学(大修館書店)に出てくる
「即座の習得」という専門用語で表現している。
この時こそ人生で一回きり来ないあらゆる動作の習得時期でスキル獲得に
は最高の時なのである。
大人にとっては不可能と思われる一輪車乗りなどは2~3回試すだけで難な
く乗りこなしてしまうものまでいる。サッカーの技術なども見様見真似で
その場でプロ選手の技を盗んでしまう。
良い見本を見せることがどれほど大切かがわかる時期でもある。あらゆる
面の環境を整えなさい、これが私のこの年代を教える指導者に対する最大
のアドバイスである。すべての面で子供たちの能力は恐ろしいほど正直で
あり忖度がなくただ一筋である。

■「成長期の教育」
●これに対して ゴールデンエイジが終わりを迎え、そのあとに来るのは、
ポストゴールデンエイジの時期である。
これも年齢は一般的なもので個人差があり、この時期の個人の取り扱いは
非常に重要とともに難しい。
スキャモンの発育曲線のリンパ型で述べた母親の抗体から自分自身の抗体
への変換期を終えるころには自我が芽生え、男は男、女は女としてのホル
モンの発育が旺盛になってくる。この時身体の内部ではどのようなことが
おこっているのであろうか。これも私の一方的な解釈と説明で進めさせて
いただく。

今、全世界で人々の移動手段や運搬手段として用いられているのが自動車
である。この自動車の発達は地球温暖化に大きな影響をもたらしているほ
ど人類にとって欠かすことができないものである。
日本では小型で小回りの利く軽自動車黄色ナンバー(排気量660㏄以下)
をたくさん生産し利活用している。この上に白ナンバー5(排気量2000㏄
以下)、白ナンバー3(排気量2000㏄以上)がある。
もし軽自動車のボディーに白ナンバー3のエンジンを搭載しようとしても
ボディーの大きさが小さくて載せられない。それでは軽自動車のボディー
を2000㏄以上の大型エンジンが搭載できるような大きなボディーにしたの
ちに、白ナンバー3の2000㏄以上の大型エンジンを搭載することにする。
これは工場製品である自動車であるからできることであり、生身の人間の
骨格を大きく発育させ、そこに白ナンバー3に相当する肺や心臓を直ちに
用意することは不可能である。人間の発育発達にはそれ相当の栄養や休息
や運動が必要である。この発育発達にはそれ相当の時間の経過が必要であ
る。
自動車のボディーに相当する身体の骨格と自動車のエンジンに相当する心
臓や肺やその他の臓器の発育発達にはほんのわずかであるが時間的ずれが
必要であることは以上のことでご理解いただけると思う。
このボディーの発育発達は外から見て一目瞭然である。まず履く靴の大き
さが急速に大きく変化し、背丈は伸び脚は長くなり、見た目には10等身か
と思われるくらいスラっとし、かっこいい。女子などは全員をファッショ
ンモデルに採用したいくらいである。しかし、彼らの内面はそれとは大違
いで、内臓はまだ子供の時のままでありこれまでと何もかもが違う。
自分のからだには訳の分からない変化が出てきてしまう。男子は声かわり、
陰毛の出現などなど、女子は月経、胸のふくらみなどなど、恥ずかしい、
見っとも無い、いやだ、面白くない。いやに疲れる、身体があれほど上手
く支配できていたゴールデンエイジの頃の自分はどこい行ってしまったの
か。とにかく眠い、疲れる、動きたくない、このような状態を心身のアン
バランスな状態、クラムジーと呼んである。
これはポストゴールデンエイジに現れる人生の中で特別の中でも特別の時
期であり、状態である。
このことは子供を育てたことのある家庭であれば多かれ少なかれ経験して
いる子供たちの発育発達のほんの一瞬であるが重要であり大切な一時期で
ある。
この時を無難に乗り越えることは家庭教育と学校教育の双方の責任と連携
が必要であることはこの自動車のボディーとエンジンの関係と骨格の発育
と諸臓器の発育との関連でもご理解いただけるものと思う。
この時期は身体的発育発達ばかりではなく心理的発育発達に極めて重要な
時期であることは小野剛氏が水色(筋・骨格系動作習得のレディネス)の
線で右肩上がりの発育発達の中で唯一下降に線をもっていっている意味を
くみ取っていただきたい。

子供たちの発育発達は成長過程で減退や後退するはずがない。
しかし機能としての動作や行動、あるいは思考としての態度や身のこなし、
特に自分以外の者への接し方はこれまでの彼、彼女はどこに行ったのだろ
うと疑いたくなるほどの変わりようである。
この時期は、思春期、ピュバティー、反抗期、クラムジーの言葉で言い表
われている。骨格の発育が進み筋肉の発育が遅れて出現するその時間的ず
れ タイムラグ、この大人になる直前の身体的精神的アンバランス、これに
は全体より個々の個人に丁寧に対応することが肝要である。サッカーのコ
ーチングでもそうであるが「じっと待つ心」、物事が変化するのに要する
時間の確保が大切であるようだ。

■「子供たちのために」
● プレゴールデンエイジ、これは本人は気が付いていないが人生で最も
楽しい時期といえよう。次に来るゴールデンエイジの準備の時期である。
この世の中が最も素晴らしいところであることを実感してもらいたい。
家族、近隣の人々、親戚の人々、学校の友達、だれもが好意的に接してく
れる。いろいろなことを経験し自分が好ましいと思う事をたくさん見つけ
ることである。
好奇心、これは彼らの特権である。一生の宝の獲得の準備期間でもある。
まずは好きなことをたくさん見つけること、そして ゴールデンエイジで
即座の習得をたくさん獲得できる神経回路をたくさん構築する時である。
たくさんの人生の宝物を蓄える準備の時としてほしい。これが これから
未来に向かって次々に来る子供たちへの私の最大の願いである。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます