4月22日、日本サッカー協会で「障がい者サッカー協議会」の第1回の会合が開かれ記者会見も行われた。「ベクトルを合わせてやっていかなくはならないのではないか」という認識のもと、各障害者サッカーの競技7団体が一同に会し最初の一歩を歩み始めた。
私自身は2006年より障害者サッカーに関わり始めているのだが、その当時からある5団体の代表者が並んでいる姿を見るだけでもとても感慨深いものがあった。
「障がい者サッカー協議会」ではまず来年4月の統括団体(日本サッカー協会の外部団体)設立に向け準備が進められていくことになるが、日本サッカー協会と各障害者サッカー団体の具体的な関係性についてはこれからの検討課題となる。
障害者サッカー団体といっても、国内で成功裏に世界大会を開催し健常者の小学生に向けても「スポ育」を幅広く展開している日本ブラインドサッカー協会もあれば、近年立ち上げられたばかりの団体、あるいは様々な課題を抱え複数の大会が中止になった団体まで様々だ。また強化と普及の両立には各団体ともに苦労している。資金や人材etc。そういった意味では巨大組織でもある日本サッカー協会が協働してくれることへ大いなる期待がかかるだろう。日本知的障がい者サッカー連盟の小澤氏も言うように「本気で向き合っていく」能動性は絶対に必要だが、一団体ではいかんともしがたい側面があるのもまた事実であるからだ。例えば脳性麻痺7人制サッカーはプレーヤーの対象となる障害を持つ人々の多くがいわゆる普通校に通っているため、情報が行き届きにくい。ろう者サッカーの場合も普通校に通う難聴者にはなかなか認知されないという問題もある。
障害者サッカー側は与えられるだけではなく、ブラインドサッカー協会松崎氏の「障害者サッカーという観点があったおかげで多くの人がサッカーが楽しめる環境が作れたり、どんな状態の人でもサッカーをやろうと思えば親しめる。それがスポーツにとっての規範になっていき『障害者サッカーを支援してよかった』と30年後に言われるように頑張っていきたい」という言葉に代表されるように、障害者サッカー側から与えうることも少なくないはずだ。スポーツの概念そのものの変革である。
もちろんそういった長期的ビジョンそして理念はとてもとても重要だが、今現在でも各障害者サッカー日本代表の活躍は第3者に対しての訴求力を持つだろう。知的障がい者サッカー日本代表は昨年の世界大会でベスト4の成績を残したし、ブラインドサッカー日本代表の躍進は昨年地上波などでも報じられた。電動車椅子サッカー協会の吉野新会長が「アスリートとして認めてもらいたい。陽の当たる場所に出ていきたい」という選手の言葉を紹介してくれたが、“場”が確保され続けていければアスリートという言葉の概念を叩き壊してくれる存在を見ることができるだろう。
そしてまた「障がいを超えた」という陳腐な色眼鏡付きの感動物語ではなく、「サッカーで混ざろう」というブラインドサッカー協会松崎氏の言葉にもあるように、サッカーを軸として見ることで触れることで、各障害者サッカーの魅力や障害そのものの理解にも辿りつけるはずだ。
「サッカー好きな人って、なんか障害に詳しいよね。」と言われるようにならないだろうか。
東京パラリンピック開催決定後、「障がいのある人もない人も」「共に」「いっしょに」という言葉を多く耳にするようになった。もちろんその通りだが、障害を理解すること無しにそれらの言葉が使われていることも多いような気がする。障害といっても実にさまざまだ。可視化できる障害もあるが、一見してとてもわかりにくい障害もある。例えば、一つの障害者サッカーのなかでも障害的な観点でみると実に様々だ。またパラリンピックを障害別で見れば、(ごく一部の知的障害を除けば)肢体不自由と視覚障害である。障がい者サッカー協議会には、聴覚障害、知的障害、精神障害もある。また重度の肢体不自由や難病としては、パラリンピックにはボッチャしか競技種目がないが電動車椅子サッカーという激しい競技もある。つまり障がい者サッカー協議会はパラリンピックより多くの障害を対象にしていて、サッカーを通じてより多くの障害に触れることができるというわけだ。
さあそして5月5日には同時に2つの障害者サッカーを目にすることができるイベントが予定されている。知的障がい者サッカーvsろう者サッカーの試合である。ポスターのコピーで言えば、「侍、激突。」
前半は知的障がい者サッカー日本代表 vs ろう者サッカー東日本選抜、後半は知的障がい者サッカー日本代表vsろう者サッカー男子日本代表というエキシビションマッチである。会場は東京都品川区大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場、13時30分キックオフ予定。
詳しくは http://jdfa.jp/news/deafsoccer20150317_exhibitionmatch/
この対戦は以前より両団体に呼びかけていたもの、なかなかスケジュールが折り合わず実現できなかったがやっと実現した。実現できて本当に嬉しい!代表レベルの試合では史上初の対戦であり、次回見ることができるのは4年後あたりかもしれず必見!
2006年にそれぞれの代表を見た時は圧倒的にろう者サッカーの方が強い印象をもったが、その後知的障がい者サッカーの力も飛躍的にあがっているのでとても楽しみだ。障害的に言えば、見た目にはわかりにくい障害同士の対戦となる。ルールは通常のサッカーと同じだが、ろう者側がホイッスルの音が聞こえないため、主審もフラッグを持ってホイッスルとともに合図する。
ちなみに各障害者サッカーで11人制サッカーをやっているのは、現状ではこの2つの団体だけである。通常のフットサルのルールで行われているのは、ろう者フットサル男女、ソーシャルフットボール(精神障害)、ロービジョンフットサル。レベルを考慮すればこちらもガチンコ対決ができるかもしれない。他の競技は特殊ルールで行われているので、体験的な対戦はできてもガチンコ対決の実現は難しいだろう。
各障害者サッカーについては過去の記事で概観していますので参照してください。
http://blog.goo.ne.jp/kazuhiko-nakamura/e/8699010c03d17cf05d4b9094a1f53319
知的障がい者サッカーvsろう者サッカーの試合で何を着るか迷うところであるが、前半知的障がい者サッカーのシャツを、後半ろう者サッカーのシャツを着る予定。ろう者サッカー東日本選抜のみなさん、ごめんなさい。

















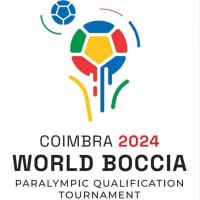

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます