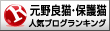愚かしい芝居は観客席から観ているのさえ耐え難い。不本意にもその場に居合わせることにでも
なったら、別のことを考えているか眠っている振りをするしかない。
だから、こと男と女の問題については、あやの優美を見る眼は醒めていた。
一人の女として見れば、優美は師でも上司でもなかった。
桐山はその後声をかけてこなかった。
優美の態度にも変化はなかつた。
あやはほっと胸をなで下ろしていた。
食事に誘われてから3カ月が過ぎ、季節は夏真っ盛りになり、店は夏物で活況を呈していた。
あやはあの誘いのことは、完全に忘れていた。桐山にとってあれは、ほんの一瞬の軽い気まぐれ
だったのだろう。
忙しいシーズンの中の休日は待ち遠しい。
それなのにあやはその日店に出た。
客からの注文品の手直しが、明日開店と同時刻に渡さなければならなくなったのだ。
休日出勤はめずらしいことではないし、自分で受け自分でなければ片付かない仕事なので止むを
得ない。
いつの間にかそんな立場であり、そんな仕事をしているのだと自覚させられる。
休日のミシン仕事は7階の工房を使う。
シャッターを下ろした店の工房に一人でいると通りの騒音は遠ざかり、自分が街から遠く離れた
別の世界に隔離された気分になる。
その感覚をあやは気に入っていた。