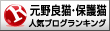私の知らないまったく別の世界が、私にかかわっているなんて考えたこともなかった。
実の父親のように私を育て支えてくれた人を、ただのジャコシカという一言で片付けていたのよ。
私、どうしたのかしらね、高さんにこんな話しばかりして、うんざりでしょう」
高志は頬杖を解いて、コーヒーカップを手にした。
残り少ない中身を大事そうに飲んでから言った。
「うんざりなんてしていないし、退屈もしていないさ。ただ一つ言わせてもらえば、鉄さんはジ
ャコシカしていたかも知れないけれど、ジャコシカではないと思う。
ジャコシカというのは、僕のような人間を言うのさ。鉄さんは大工という、立派な職業を身につ
けた職人でしょう。
流れ歩くには、それなりの理由があったと思う。僕とは違う。
僕はジャコシカしているのではなくて、ジャコシカそのものなんだ。
あやさんの話しを聞いていて、そのことを強く感じる。だからあやさんは生き方において、鉄さ
んと同じような気がする。
生き方に理由があり、目的がある」
「高さんはそうではないと言うのね」
「いつかも言った通り、僕にはそういったものは何もない」
「そうね、そう言っていたわね。私には理解できないけれど」
あやは一瞬、悲し気に高志の瞳の奥を見た。
それからカップの中を覗きこんだが、その底にコーヒーはもう残っていなかった。
所在無さ気に空のカップを両手の中に包みこみ、まさぐっていたが、やがてカチリと音を立てて
置いた。