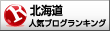「なら、そちらの方はまかせた」
高志が案じた通り鉄さんは素直に、あやの言うことは聞かなかった。それでも繰り返し訴える、
あやの根気に折れた。
「仕方がない、この際、二人に余り心配かけては、罰が当たるというもんだ」
高志が一人で漁協に行くようになってから、鉄さんは漁にも無理をしなくなった。
出漁前の空模様、海の状況判断には今までよりも時間をかけるようになり、少こしでも時化模様
の時は、あっさりと漁を諦めるか、眼の前の入江の入口あたりにまでしか、足を延ばさなくなった。
それはあやと高志にとっては、良い兆候に思えた。二人の時なら海の状況が問題なしとして出漁
しても、空模様に変化が現れると躊躇なく切り上げて帰った。
そんな鉄さんを見て、高志は逆にかって感じたことのない不安を感じた。
何だか鉄さんが変わってしまった気がしたのだ。
そんなある日、あやと二人で漁協に出荷した時のことだった。事務所を出ようとした二人に、
清子が追いかけて来て声をかけた。
「この間鉄さん宛に手紙が届いていたけれど、あれ私驚いたわ。鉄さんに手紙なんて今まで一度
もなかったことだからびっくりだった。
失礼だけれど鉄さんに手紙をくれる人がいたということが、何だか不思議な気がしたの。
私あの人はひょっこり峠に現れて影山さんに会って、それからここに住み始めた人だってことし
か知らなかったので、勝手に知人も身寄りもない人なんだと思っていたの。
だから影山さんが唯一の身内で、あやさんはあの人のたった一人の実際の子供だと思っていたの」
清子は二人を事務所の玄関脇に足止めをして、彼女としてはめずらしく長い話しをした。