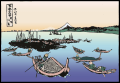六十余州名所図会 紀伊「紀伊」 和歌の浦和歌浦は大阪に接する和歌山市南部にある。本図では、和歌浦の入江から、遠景の小島までが中心に描かれている。小島は妹背山と呼ばれ、三断橋で内陸と結ばれており......
六十余州名所図会 長門「長門」 下の関山陽道の西端にある下関は、関門海峡を挟んで九州に繋がる。古くから海上交通の要として機能し、輸送船の寄港地として「西の浪華」と呼ばれるほど繁栄していた。本図......
六十余州名所図会 周防「周防」 岩国 錦帯橋周防(すおう)は山口県の東南部にあって防州(ぼうしゅう)とも呼ばれていた。岩国市を流れる錦川にかかる錦帯橋は1673年岩国藩主吉川広嘉によって創建さ......
六十余州名所図会 安藝「安藝」 厳島 祭礼之図日本三景の一つである厳島神社の鳥居は、神社と共に足元が海に晒されていることで有名である。度重なる災害に耐え抜き、現在では世界遺産として観光の名所と......
六十余州名所図会 備後「備後」 阿武門観音堂本図は、福山市の南方、沼隈町にあって、阿伏兎の瀬戸と呼ばれる田島との間にある幅500mの海峡である。潮流が速く、航行の安全を祈願する為に阿伏兎岬の突......
六十余州名所図会 備中 豪渓「備中」 豪渓岡山県総社市の近くで槇谷川の高梁川に合流する地点より上流5kmほどにある豪渓である。激しい川の流れが両岸を侵食し、荒々しく抉られた奇岩を作り出した。行き交う......
六十余州名所図会 美作「美作」 山伏谷強い風を伴った横なぐりの雨を描き、笠は飛び、天地鳴動の瞬間をとらえている。きつい雨脚を太い条帛のような描写で行い、このシリーズで最も激しい風雨の景を描き、......