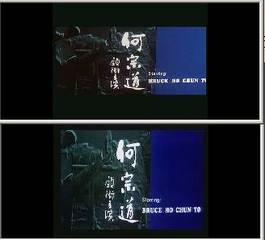寸評:
ジョン・リュウ主演の足・足・足の映画。高飛VSジョン・リュウ。やっぱり格好いいですね。(滝の上の対決は何なんだろう・・。)神腿というと別人のドリアン・タン(レオン・タン)ように思えますが、もう一人の自称(爆、神腿かな。でも真面目に演技しています。
情報:
いま本数の多い79年関係を洗っていますが、
HKMDBでは79年説もあるようなんですが、
台湾で77年に公開されているようなので77年の作品と思われます。
(『密宗神腿』と微妙に変更)
雑誌記事では銀色世界のNo91('77ー7月号)に新作紹介が掲載。
The Mar's Villa って・・・主人公の何かにまつわるお話なのかも。(役名は馬天浪だそうです。)
画像:


出演者:共演のタン・パオユン(唐寶雲)は、倉田保昭の「激怒の鉄拳」などに出演してた台湾の女優さん。どちらかというと文芸片ばかり。紅一点でしたが、よくまぁジョン・リュウと共演できましたね。
会社:大華影業はいくつかの作品を製作。(丁重)
ソフト:USA盤のDVDが発売済。

ジョン・リュウ主演の足・足・足の映画。高飛VSジョン・リュウ。やっぱり格好いいですね。(滝の上の対決は何なんだろう・・。)神腿というと別人のドリアン・タン(レオン・タン)ように思えますが、もう一人の自称(爆、神腿かな。でも真面目に演技しています。
情報:
いま本数の多い79年関係を洗っていますが、
HKMDBでは79年説もあるようなんですが、
台湾で77年に公開されているようなので77年の作品と思われます。
(『密宗神腿』と微妙に変更)
雑誌記事では銀色世界のNo91('77ー7月号)に新作紹介が掲載。
The Mar's Villa って・・・主人公の何かにまつわるお話なのかも。(役名は馬天浪だそうです。)
画像:


出演者:共演のタン・パオユン(唐寶雲)は、倉田保昭の「激怒の鉄拳」などに出演してた台湾の女優さん。どちらかというと文芸片ばかり。紅一点でしたが、よくまぁジョン・リュウと共演できましたね。
会社:大華影業はいくつかの作品を製作。(丁重)
ソフト:USA盤のDVDが発売済。