前回の(83)で書いた様に、『杉田久女句集』に添えられた高浜虚子の序文を読むと、この文章は不自然で、序文にそぐわないものに思えて仕方ありません。久女生前に序文懇願を無視したのと同じ気持ちが、まだ虚子の中にある様に感じます。
虚子は久女を「女流俳人として輝かしい存在」「群を抜いていた」と書いていて、彼女の才能を認め、その俳句作品に清艶香華という言葉を贈っています。久女俳句を見抜いた虚子ならではの言葉だとは思います。
がしかし、「久女さんの行動にやゝ不可解なものがあり」や「精神分裂の度を早めた」などとも書いていて、弟子の遺句集を世に送り出すはなむけの序文であるとはとても思えません。
虚子は久女の代表句として十句あげていますが、人にはそれぞれ好みがあるといえばそれまでですが、もっとピッタリくるものが何句でもある様な気がするのです。
例えば、楊貴妃桜の句が三句あげられていますが、久女の句を出来るだけ多く紹介するという立場で考えると、十句のうち三句までが楊貴妃桜の句というのは首をかしげたくなります。
同じ場所で詠まれた、この楊貴妃桜の三句をどうしてもあげたいならば、三句をまとめて配列してこそ、作品効果が出るのだと思います。句の順序も1番目が〈風におつ 楊貴妃桜 房のまま〉、2番目が〈むれ落ちて 楊貴妃桜 房のまま>、3番目が〈むれ落ちて楊貴妃桜 尚あせず〉に当然すべきで、なぜ、この三句の間に別の句をはさむという、こんな配列になっているのか、理解に苦しみます。
それに、2番目にあげている句の〈灌浴〉は、正確には〈灌沐〉です(これは誤植かもしれませんが)。
さらにこの序文の重大な問題点は、高浜虚子はここでもまた事実と違うこと、嘘を書いていることです。
久女の句稿の原本について、虚子は「全く句集の体を為さない、ただ乱暴に書き散らしたものであった」と序文で書いています。しかし、久女の長女昌子さんは、これは事実と違っていると述べています。
昌子さんは著書『杉田久女』に、<私は母の句稿の原本がもし紛失することでもあったらという不安と、又、その原本が墨書であり、句を巻紙に抽出したものであった、ということから、母の亡くなった直後に、原稿用紙に清記しておいたものであった。したがって虚子先生は母の句稿に目を触れられてはいないのだった。>と書いておられます。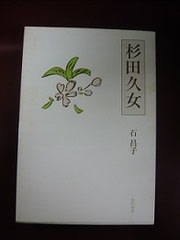 <石昌子著『杉田久女』>
<石昌子著『杉田久女』>
昌子さんは虚子に見せたのは久女の句稿の原本そのものではない、昌子さんが原稿用紙に清記したものと断言されています。当時は今日の様に簡単にコピーが出来る時代ではないので、万一久女の句稿の原本が紛失したら取り返しがつきません。なので貴重な原本そのものを、虚子に郵送したりしないのは当然でしょう。
なお、この句稿の原本は(71)の記事の写真にあるとおりで、ずっと久女の長女石昌子さんが大切に手元で保管されていましたが、現在は久女ゆかりの小倉北区の圓通寺に寄贈されています。写真を見てもわかる通り、虚子の言うように<全く句集の体を為さない、ただ乱暴に書き散らしたもの>ではないのは明らかです。
高浜虚子は「墓に詣り度いと思ってをる」という一文と同じように、この序文の中でも久女の狂気を強調したいために、この様な嘘を書いたのだと思われます。
しかし、久女の長女昌子さんは<事実と違うといっても、お願いして書いて頂いた序文を事実通り書き直して欲しいと、私には言えなかった>とその著書の中で書いておられます。それはそうでしょうね。
ですから、昭和27年10月出版の『杉田久女句集』には高浜虚子が書いた序文がそのまま載せてありますが、昭和44年7月に同じ角川書店より出版された増補版の『杉田久女句集』にはこの虚子の序文と悼句は、省かれています。この序文は久女に対する偏見を助長すると、昌子さんは考えたのだと思います。![]()
![]() ⇐クリックよろしく~(^-^)
⇐クリックよろしく~(^-^)
このカテゴリー「俳人杉田久女(考)」を「谺して山ほととぎすほしいまゝ(久女ブログ)http://blog.goo.ne.jp/lilas0526」として独立させました。内容は同じですが、よろしければ覗いてみて下さい。
久女の長女昌子さんは、生前の母から託された句集出版を何としても果たしたく、苦労の末かろうじて、高浜虚子から序文を貰い、昭和27年10月、角川書店からの『杉田久女句集』出版にこぎつけました。
私は角川書店発行の久女の句集を持っていませんので、虚子が書いたその序文を北九州市立文学館発行の『杉田久女句集』から、全文引用してみます。
「 序 」
杉田久女さんは大正昭和にかけて女流俳人として輝かしい存在であった。ホトトギス雑詠の投句家のうちでも群を抜いていた。生前一時その句集を刊行したいと言って私に序文を書けという要請があった。喜んでその需めに応ずべきであったが、その時分の久女さんの行動にやゝ不可解なものがあり、私はたやすくそれには応じなかった。此の事は久女さんの心を焦立たせてその精神分裂の度を早めたかと思われる節も無いではなかったが、併しながら、私はその需めに応ずることをしなかった。
久女さんの没後、その長女の石昌子さんから、母の遺稿を出版したいのだが、一応目を通して呉れないか、という依頼を受けた。私は喜んでお引き受けするという返事を出した。送って来たその遺稿というものを見ると、全く句集の体を為さない、ただ乱暴に書き散らしたものであった。それを整正し且つ清書する事を昌子さんに話した。昌子さんは丹念にそれを清書して再びその草稿を送って来た。私は句になっていると思われるものに〇を付して、それを返した。その面白いと思われる句は、曾てホトトギスの雑詠欄その他で一通り私の目に触れたものである様に思えた。他に遺珠と思われるものはそう沢山は無かった。試しにその句、数句を挙げてみようならば、
「 無憂華の 樹かげはいづこ 仏生会 」
「 灌浴の 浄法身を 拝しける 」
「 花衣 ぬぐやまつはる 紐いろいろ 」
「 むれ落ちて 楊貴妃桜 尚あせず 」
「 咲き移る 外山の花を めで住めリ 」
「 桜咲く 宇佐の呉橋 うちわたり 」
「 風に落つ 楊貴妃桜 房のまま 」
「 むれ落ちて 楊貴妃桜 房のまま 」
「 菊干すや 東籬の菊も つみそえて 」
「 摘み競ひ 企救の嫁菜は 籠にみてり 」
これらの句は清艶香華であって、久女独特のものである。尚この種の句は他に多い。生前の序文を書けといふその委嘱に応ずる事が出来なかった私は、昌子さんの求める儘に丹念にその句を克験してこれを返した。
昭和二十六年八月十六日
鎌倉草庵 高浜虚子
以上が高浜虚子が遺句集『杉田久女句集』に書いた序文ですが、これを読むと、どこか不自然で弟子久女の遺句集出版を寿ぎ、多くの人々からこの句集が受け入れられることを願って書いたとは思えない文章だと感じます。
それともう一つ、これは北九州市立文学館の学芸員の方から直接聞いた話ですが、高浜虚子は、(80)の記事にある自身が書いた創作「国子の手紙」を、『杉田久女句集』巻末に採録しようとしていたのだそうです。
「国子の手紙」は虚子が久女の狂気を世間に知らしめるために書いたものだといわれていますが、その創作を『杉田久女句集』巻末に載せるという行為には、死者に鞭打つことが出来る執拗さや、人間として師としての思いやり慈しみに欠ける、彼の非情な人格がかいま見える様に思います。
しかし、結果的に虚子の創作「国子の手紙」は、中央公論社の方に載ることになった為、『杉田久女句集』に載せることはなかった、との学芸員の方のお話しでした。
次の記事でこの序文について、私が感じることを書いてみようと思います。![]()
![]() ⇐クリックよろしく~(^-^)
⇐クリックよろしく~(^-^)
このカテゴリー「俳人杉田久女(考)」を「谺して山ほととぎすほしいまゝ(久女ブログ)http://blog.goo.ne.jp/lilas0526」として独立させました。内容は同じですが、よろしければ覗いてみて下さい。
秋晴れの一日、熊本県小国町下城の大イチョウを見に行った。
巨大なカルデラで知られる阿蘇山の裾野に広がる小国町。
小国杉が植林された山々が続く道を車で走る。
視界が開けて、下城の大イチョウ前に到着。
まだ真黄色には少し早いかも...。
イチョウにしては横に張っているのが珍しいかも...。
樹齢1000年以上の国の天然記念物。
その大きさ、迫力に圧倒される。
夜はライトアップされるそうで、それもすばらしいだろうな~。
大イチョウを仰ぎ見て、ふと振り返ると水の音。
何だろうと道を渡って音のする方へ。
そこには神秘的な下城の滝が白い水しぶきをあげていた。
落差50M、上から見ているので吸い込まれそう。
大イチョウと滝を見学後、小国町役場に寄ってみる。
外壁に杉材をオシャレに使っている。
素敵なデザインが、いかにも小国町らしい。![]()
![]() ⇐クリックよろしく~(^-^)
⇐クリックよろしく~(^-^)
世界最高峰と言われているヨットレース、アメリカズカップ。
その予選シリーズのワールドシリーズが、
福岡市地行浜沖の博多湾で11/19~11/20に行われています。
アメリカズカップ予選シリーズのアジアでの開催は今回がはじめてだそう。
予選シリーズでアメリカズカップの挑戦権を争うのは、
アメリカ、日本、イギリス、ニュージーランド、スエーデン、フランスの計6か国。
既に世界各国で予選が行われていて、
今回は9戦目となるそう。
地行浜は家から割合近いのでウオーキングがてらに行ってみました。
行って驚きました、和服姿の老婦人もチラホラ。
いつもこの時期、閑散としている地行浜、百道浜が老若男女でイッパイ。
競技が行われている所は、少し沖なので見えにくい。
昨日3レース、今日3レース行われ
日本艇として2000年以来の参戦となった「ソフトバンク・チーム・ジャパン」は、
6チーム中の5位だった。
(3枚目の写真はネットよりお借りしました)![]()
![]() ⇐クリックよろしく~(^-^)
⇐クリックよろしく~(^-^)
前回(81)の記事では、『杉田久女句集』出版までのいきさつについて、詳しく触れていませんので、この遺句集は比較的スムーズに出版された様に感じられるかもしれませんが、実際はそうではありませんでした。
久女の生前はいくら懇願されても久女の句集に序文を与えなかった高浜虚子でしたが、彼女の死後もそんなにすんなりとは運びませんでした。
今まで述べた様に、高浜虚子は久女の死後、『ホトトギス』やその他の雑誌に、死者に鞭打つ様な、久女叩きとも受け取れる文章を次々に発表していました。
それらの文章には、虚子が久女を同人除名した処置を正当化しようとする意図があったと思われますが、その内容は「常軌を逸していた」、あるいは「狂人」という点のみを強調し、久女が除名前から狂っていたという風説を流すものでした。
久女の長女昌子さんにとって、この様な時期の虚子に、母の遺句集に序文を書いてほしいとお願いするのは、相当大変だったと思います。
昌子さんの書かれた文章によると、出版社を決めようとすると「久女さんのものを出版すると、虚子先生からの出版物がいただけなくなる。久女さんのものは虚子先生から差し止めがあって...」という理由で断られたこともあったようです。つまり虚子は久女が彼の序文なしでの句集を出版出来ない様に、妨害工作までしていたのですね。これには驚くとともに何もそこまでしなくてもと思わずにはいられません。
色々思案した末、昌子さんのご主人、石一郎氏の師である川端康成(『伊豆の踊子』『雪国』の作者)を煩わせ、川端康成と石一郎氏が、句稿を持参して、鎌倉の虚子宅へお願いに行ったようです。
その様ないきさつがあり、久女の長女昌子さんは、苦労の末やっとの思いで、かろうじて高浜虚子から序文を貰い、昭和27年10月、角川書店からの『杉田久女句集』出版にこぎつけたのでした。![]()
![]() ⇐クリックよろしく~(^-^)
⇐クリックよろしく~(^-^)
このカテゴリー「俳人杉田久女(考)」を「谺して山ほととぎすほしいまゝ(久女ブログ)http://blog.goo.ne.jp/lilas0526」として独立させました。内容は同じですが、よろしければ覗いてみて下さい。









