
奈良公園の朝
12月、暖かな小春日和、再び春日大社お参りから

伏鹿手水所(ふせしかのてみずしょ)
巻物を銜えた鹿とご対面
巻物の端から水が流れ出ますが、鹿像の下に普通の手水舎があります

春日大社の神様にお仕えする眷属「神の使い」

今回の目的の一つ、石燈籠にも気を配って見てみましょう、です
祓戸神社(はらえどじんじゃ)前
石燈籠(室町時代初期)
六角形の石燈籠は、祓戸神社正面の前に立っている

笠上の宝珠
笠は、蕨手(わらびて)が美しく立ち上がり軒反は緩い
(手前は欠損しているのでしょうか)
軒裏に一重の薄い垂木型を作る

火袋は、火口・丸窓・壁を各二面作り

壁には鹿の姿がかすかに分かります



奈良の都は、約1300年前の710年(和銅三年)飛鳥藤原宮から平城京に遷都し
山城国長岡に移るまで74年間国政を司り、華やかな天平文化を育み栄えました
この頃の信仰の場として、東大寺、興福寺などの南都七大寺と
春日大社等の社寺仏閣が創建あるいは移築されました
12月の暖かい陽射しを浴びながら、歩いています

浮雲園地
若草山の稜線


春日野園地


興福寺五重塔

次へ移動



















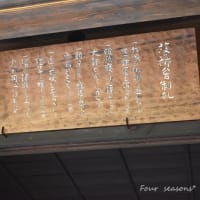







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます