黄檗(おうばく)駅で降りて
徒歩5分もかからないくらいで
萬福寺の総門に到着。

萬福寺は禅宗の一つ 黄檗宗の大本山。
開かれたのは1661年
4代将軍徳川家綱の時代。
平安京発足期に開かれた
京都の東寺のようには古くはない。

東寺より新しい臨済宗や曹洞宗のお寺は
日本風なのに
それらより新しい萬福寺は中国風(明朝様式) ↑
総門の次の門が三門 ↓

ここに伽藍の地図が掲示されている。何と広大! ↑
これを今から全部見て回る体力はないわ~。 ↓
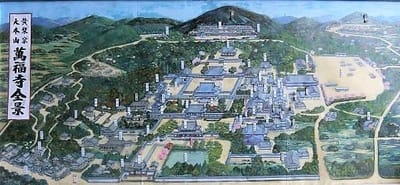
ここで拝観料を払い、リーフレットをもらい
とにかく有名な木魚を見たく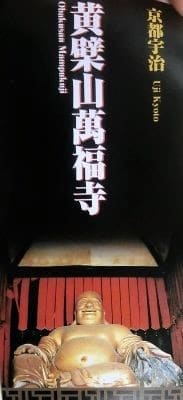
どこにあるのかを教えてもらった。
中国風のお寺に
七福神の一人、布袋(ほてい)さん? ↑
ミスマッチな感じがするが
京都府内の7カ所の寺社の七福神を巡る
都七福神(みやこしちふくじん)巡りの
巡礼札所となっているのだと。
三門の次にある、この天王堂に ↓

布袋さんがど~んと座っておられる。
↓

七福神が乗っている舟は
莫大な富を持つ倭寇舟がモデルだと
聞いたことがあり
「なるほど」と思っていたが
これによると七人の出身は
日本の土着宗教
インドのヒンドゥー教
中国の仏教・儒教
と、国際色豊かなようだ。
天王堂の前には優美な水の器

流れ落ちる水で手を洗う?
天王堂の次は大雄宝殿(本殿) ↓

↑
その正面には、完璧なほど中国風の香炉
↓

大雄宝殿の中には十六ならぬ十八羅漢が
ズラリと並んでおられる。
半数は中国・日本人的なお顔で
半数はインド・アラビア・アフリカ的。
これらを見ていると、仏教とは
遠い異国から発展しながら日本に伝えられ
日本に着いてからも
どんどん発展・進化しているのだとわかる。
大雄宝殿から右に曲がると
斎堂(食堂)があり
その回廊には萬福寺のシンボル ↓

木魚の原形となった開梛(かいぱん)
-魚梆(ぎょほう)とも-
カメラ・スマホが置ける台が置いてあり ↑
自撮りで記念撮影できるようになっている。↓

色が変わっているところを
打ち鳴らして、時を報ずるためのもので
現在も使用されている。
かなり新しいことを思うと
これまでに何度も作り直されたのだろう。
私の後ろが売店になっていて
赤い毛氈の腰かけに座って
コーヒーが飲めるようになっている。 ↑

コーヒーの紙コップにも開梛の絵が。↑
萬福寺を開いたのは
中国明の僧・隠元(いんげん)禅師で
日本における「煎茶道の祖」。
木魚だけでなく
普茶料理・インゲン豆・スイカ
レンコン・孟宗竹(タケノコ)なども
隠元禅師によって
導入・普及されたものなのだと👀‼️
境内には中国風(明朝様式)の門と
卍崩しの欄干がついた文華館。 ↓

でも、休館中のよう。コロナのため?
天王殿に戻って、左側に伸びる回廊を進むと
↓

大雄宝殿などの屋根の勾配がとても強く ↓
これも明朝様式?

回廊の途中に鐘楼があるのも明朝様式? ↓

眞空塔と書かれている塔 ↓
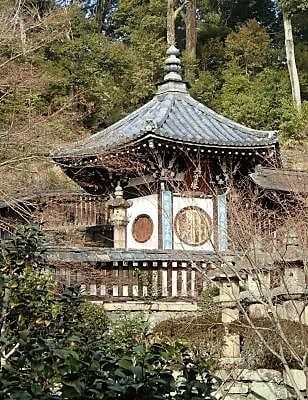
隠元禅師の像がどこかに
あるらしいが、わからなかった。
公開されていないのも?
尋ねてさらに歩き回る体力はなし。
なのに
売店や三門に生けられている
蠟梅の花が気になる。
相当大きな木でないと
大きな花をたくさんつけた枝は切れない。
きっと境内にあるはずと思って
尋ねたところ、天真院という塔頭(たっちゅう)に
あることが分かった。

ところが「観光不可」と書かれている。
が、浄財を入れ、蠟梅の木を撮影。
さすがに大きな木、花もいっぱい。 ↓

中国風のお寺には蠟梅がよく似合う。
帰ろうと、放生池のところまで来ると
望遠レンズ付きの立派なカメラを持った
高齢男性が二人「おっ、来た来た」と。
「何を狙っているんですか?」と尋ねると
カワセミだった。 ↓

私のカメラではこの程度にしか撮れず…😥
この日、人生初乗車の、京阪宇治線 ↓

中書島→丹波橋→近鉄丹波橋→生駒に帰宅。
仕事での移動時
生駒⇔京都、生駒⇔大阪 は
緊急事態宣言後も
あまり変わりなく混んでいる。
でも、お寺も電車もガラガラ。
お寺もお土産屋さんも
収入減で大変でしょうね。
徒歩5分もかからないくらいで
萬福寺の総門に到着。

萬福寺は禅宗の一つ 黄檗宗の大本山。
開かれたのは1661年
4代将軍徳川家綱の時代。
平安京発足期に開かれた
京都の東寺のようには古くはない。

東寺より新しい臨済宗や曹洞宗のお寺は
日本風なのに
それらより新しい萬福寺は中国風(明朝様式) ↑
総門の次の門が三門 ↓

ここに伽藍の地図が掲示されている。何と広大! ↑
これを今から全部見て回る体力はないわ~。 ↓
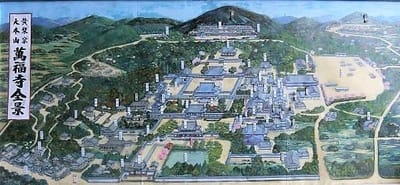
ここで拝観料を払い、リーフレットをもらい
とにかく有名な木魚を見たく
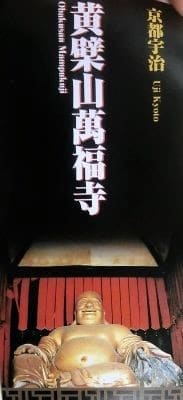
どこにあるのかを教えてもらった。
中国風のお寺に
七福神の一人、布袋(ほてい)さん? ↑
ミスマッチな感じがするが
京都府内の7カ所の寺社の七福神を巡る
都七福神(みやこしちふくじん)巡りの
巡礼札所となっているのだと。
三門の次にある、この天王堂に ↓

布袋さんがど~んと座っておられる。
↓

七福神が乗っている舟は
莫大な富を持つ倭寇舟がモデルだと
聞いたことがあり
「なるほど」と思っていたが
これによると七人の出身は
日本の土着宗教
インドのヒンドゥー教
中国の仏教・儒教
と、国際色豊かなようだ。
天王堂の前には優美な水の器

流れ落ちる水で手を洗う?
天王堂の次は大雄宝殿(本殿) ↓

↑
その正面には、完璧なほど中国風の香炉
↓

大雄宝殿の中には十六ならぬ十八羅漢が
ズラリと並んでおられる。
半数は中国・日本人的なお顔で
半数はインド・アラビア・アフリカ的。
これらを見ていると、仏教とは
遠い異国から発展しながら日本に伝えられ
日本に着いてからも
どんどん発展・進化しているのだとわかる。
大雄宝殿から右に曲がると
斎堂(食堂)があり
その回廊には萬福寺のシンボル ↓

木魚の原形となった開梛(かいぱん)
-魚梆(ぎょほう)とも-
カメラ・スマホが置ける台が置いてあり ↑
自撮りで記念撮影できるようになっている。↓

色が変わっているところを
打ち鳴らして、時を報ずるためのもので
現在も使用されている。
かなり新しいことを思うと
これまでに何度も作り直されたのだろう。
私の後ろが売店になっていて
赤い毛氈の腰かけに座って
コーヒーが飲めるようになっている。 ↑

コーヒーの紙コップにも開梛の絵が。↑
萬福寺を開いたのは
中国明の僧・隠元(いんげん)禅師で
日本における「煎茶道の祖」。
木魚だけでなく
普茶料理・インゲン豆・スイカ
レンコン・孟宗竹(タケノコ)なども
隠元禅師によって
導入・普及されたものなのだと👀‼️
境内には中国風(明朝様式)の門と
卍崩しの欄干がついた文華館。 ↓

でも、休館中のよう。コロナのため?
天王殿に戻って、左側に伸びる回廊を進むと
↓

大雄宝殿などの屋根の勾配がとても強く ↓
これも明朝様式?

回廊の途中に鐘楼があるのも明朝様式? ↓

眞空塔と書かれている塔 ↓
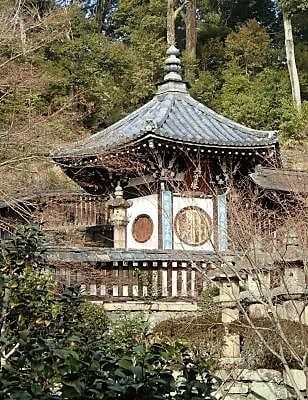
隠元禅師の像がどこかに
あるらしいが、わからなかった。
公開されていないのも?
尋ねてさらに歩き回る体力はなし。
なのに
売店や三門に生けられている
蠟梅の花が気になる。
相当大きな木でないと
大きな花をたくさんつけた枝は切れない。
きっと境内にあるはずと思って
尋ねたところ、天真院という塔頭(たっちゅう)に
あることが分かった。

ところが「観光不可」と書かれている。
が、浄財を入れ、蠟梅の木を撮影。
さすがに大きな木、花もいっぱい。 ↓

中国風のお寺には蠟梅がよく似合う。
帰ろうと、放生池のところまで来ると
望遠レンズ付きの立派なカメラを持った
高齢男性が二人「おっ、来た来た」と。
「何を狙っているんですか?」と尋ねると
カワセミだった。 ↓

私のカメラではこの程度にしか撮れず…😥
この日、人生初乗車の、京阪宇治線 ↓

中書島→丹波橋→近鉄丹波橋→生駒に帰宅。
仕事での移動時
生駒⇔京都、生駒⇔大阪 は
緊急事態宣言後も
あまり変わりなく混んでいる。
でも、お寺も電車もガラガラ。
お寺もお土産屋さんも
収入減で大変でしょうね。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます