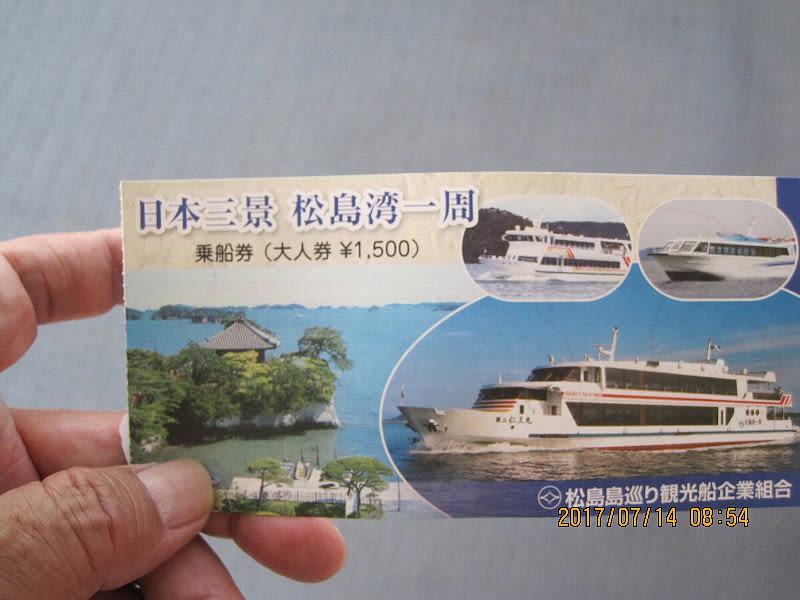令和7年2月5日(水)
松島 : 観 瀾 亭
<観瀾亭大欅>

<その説明>

観瀾亭は
文禄年中に
豊臣秀吉から伊達政宗が
拝領した伏見桃山城の一棟で、
江戸品川の藩邸に
移築したものを
二代藩主忠宗が
一木一石変えず
この地に移したもの
と伝えられている。
<タチアオイ>

<観瀾亭松島博物館の説明>

童謡「どんぐりころころ」は、
松島町出身の青木存義氏が、
文部省在職中の大正年間に
松島での幼き日を偲び
作詞したもの。
<「どんぐりころころ」の歌碑>
<「どんぐりころころ」の歌碑>


雄島へ向かう途中で、
歴史建造物・
地元の出身の歌碑
「どんぐりころころ」、
独特の形をした大欅、
そして、
○年過ぎてもまだ
復興中の様子等々
未知の遭遇!
<復興中だったなあ>
<復興中だったなあ>

芭蕉への感謝も募る
朝となる。
そして、雄島入口へ。
そして、雄島入口へ。