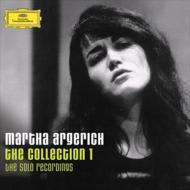
気がつけば、5月も半ば。いい季節になってましたねえ。プロ野球も交流戦が始まりました。4月から快進撃のマリーンズ。GWの9連戦では4勝5敗。いけません。勢いにもかげりが見えてきました。打線は好調なんですが、近頃投手がいけません。先発陣が今イチ。K、Oくんに頑張ってもらわないとねえ。ここが踏ん張りどころです。しかし、去年の久保、そして今年の清水直、加えて川崎などの投手を、ほぼ無償トレードで放出したあたりが痛いのではと思うのは私だけでしょうか。フロントさんはもっと考えて欲しいものですねえ。とまあ、一部のファンにしかわからないお話でした。3月から4月にかけて、ヤケ買いしたCD、なかなか聴けておりません。加えて、最近大分前に買ったCDをよく聴く傾向にありまして、周囲に聴いていないCDがたくさんあることは、妙に安心感があったりして…。当分は購入を控えようと思っています(笑)。
そんな中、前回に引き続いてバッハであります。よく音楽を職場やいろんなろことで聴いていると、たま~に「何を聴いてはるんですが?」と聴かれることがあります。そのときにベートーヴェンって答えるのは、少々気恥ずかしい。ブルックナーやマーラーではマニアックすぎる。そこで、一番相手もこっちも「ほうほう」と思える答が「バッハ」ではないかと思っています。バッハの音楽は、懐が深く、いろんなジャンルを聴く人にもなんとなく存在感は一番ではないでしょうかねえ。そんなところで、前日ちょうどバッハを聴いていたときに聴かれたので、そう答えたら、妙に気分がよかったのでありました。
そのときに、聴いていたのは、『パルティータ』第2番ハ短調BWV.826でありました。バッハの鍵盤楽器による音楽は、多くのものがあります。その中で、『イギリス組曲』『フランス組曲』ってのがありますが、それと似通った形式のものですね。演奏は、マルタ・アルゲリッチ。1979年の録音。イギリス組曲第2番、パルティータ第2番、トッカータの三曲を収録しているCDでありました。まあ、これらの鍵盤楽器の音楽は、なんといってもグレン・グールドによる演奏が大きく立ちはだかっていまして、全曲録音としては、これを凌ぐものはなかなか見当たらないのが大方の見方でしょう。しかし、個別の曲では、このアルゲリッチによる演奏は、グールドに対抗できる演奏と思っています。私は、それほどアルゲリッチの演奏は聴いていない人間なんです。それはアルゲリッチの演奏する曲と私の嗜好が合わなかったからでありました(笑)。
アルゲリッチの演奏は、6曲ある組曲の中から、2番ハ短調を単独で収めたもの。まず、これが効果的です。1番から順番に聴いていくのと違って、独立して2番だけとなると、1番から順に聴くのとはかなり違う。特に、バッハの短調の曲は、演奏によって受ける印象は大きく違うのですね。アルゲリッチの演奏は、非常に主観的な演奏で、自分の感情をバッハの曲を通して表現するようなものです。テンポや強弱の変化は他の演奏には聴けないものですねえ。バッハの演奏には、非常に客観的ものもあり、それはそれで嫌いではないのですがね。この曲、シンフォニア・・アルマンド・クーラント・サラバンド・ロンド-・カプリッチョの6曲からなってますが、急・緩・急・緩・急・急といったテンポです。特に、真ん中のサラバントの叙情的な風景は一番いいですね。アルゲリッチのピアノは急の部分では、極めてエキセントリックな表現が聴かれます。他の演奏では聴けない激しさや鋭さがあります。それはこんなバッハの世界もあったのと思ってしまいます。一方、緩のところでは表情が豊かで、しっとりとしたピアノの美しい演奏が聴けます。決して穏やかなものではなく、そこには切迫感あふれる美しさであります。私は、チェンバロによる演奏は聴いたことがないのですが、ピアノの表現力を極限までに駆使したものと言えるでしょう。この演奏を聴くと、他のはなんと緩いものかとついつい思ってしまうのでした。
このCDは「アルゲリッチ・コレクション1-ソロ・ピアノ録音」というものの1枚です。8枚組で3000円と少しでした。これも激安BOXですねえ。それにしても、アルゲリッチの演奏、他のバッハの曲でも聴いてみたいですよねえ。特に、平均律なんかを録音してもらいたい、と思うのは、私だけではないはずであります。
(DG COLLECTORS 4775870 2008年 輸入盤)
そんな中、前回に引き続いてバッハであります。よく音楽を職場やいろんなろことで聴いていると、たま~に「何を聴いてはるんですが?」と聴かれることがあります。そのときにベートーヴェンって答えるのは、少々気恥ずかしい。ブルックナーやマーラーではマニアックすぎる。そこで、一番相手もこっちも「ほうほう」と思える答が「バッハ」ではないかと思っています。バッハの音楽は、懐が深く、いろんなジャンルを聴く人にもなんとなく存在感は一番ではないでしょうかねえ。そんなところで、前日ちょうどバッハを聴いていたときに聴かれたので、そう答えたら、妙に気分がよかったのでありました。
そのときに、聴いていたのは、『パルティータ』第2番ハ短調BWV.826でありました。バッハの鍵盤楽器による音楽は、多くのものがあります。その中で、『イギリス組曲』『フランス組曲』ってのがありますが、それと似通った形式のものですね。演奏は、マルタ・アルゲリッチ。1979年の録音。イギリス組曲第2番、パルティータ第2番、トッカータの三曲を収録しているCDでありました。まあ、これらの鍵盤楽器の音楽は、なんといってもグレン・グールドによる演奏が大きく立ちはだかっていまして、全曲録音としては、これを凌ぐものはなかなか見当たらないのが大方の見方でしょう。しかし、個別の曲では、このアルゲリッチによる演奏は、グールドに対抗できる演奏と思っています。私は、それほどアルゲリッチの演奏は聴いていない人間なんです。それはアルゲリッチの演奏する曲と私の嗜好が合わなかったからでありました(笑)。
アルゲリッチの演奏は、6曲ある組曲の中から、2番ハ短調を単独で収めたもの。まず、これが効果的です。1番から順番に聴いていくのと違って、独立して2番だけとなると、1番から順に聴くのとはかなり違う。特に、バッハの短調の曲は、演奏によって受ける印象は大きく違うのですね。アルゲリッチの演奏は、非常に主観的な演奏で、自分の感情をバッハの曲を通して表現するようなものです。テンポや強弱の変化は他の演奏には聴けないものですねえ。バッハの演奏には、非常に客観的ものもあり、それはそれで嫌いではないのですがね。この曲、シンフォニア・・アルマンド・クーラント・サラバンド・ロンド-・カプリッチョの6曲からなってますが、急・緩・急・緩・急・急といったテンポです。特に、真ん中のサラバントの叙情的な風景は一番いいですね。アルゲリッチのピアノは急の部分では、極めてエキセントリックな表現が聴かれます。他の演奏では聴けない激しさや鋭さがあります。それはこんなバッハの世界もあったのと思ってしまいます。一方、緩のところでは表情が豊かで、しっとりとしたピアノの美しい演奏が聴けます。決して穏やかなものではなく、そこには切迫感あふれる美しさであります。私は、チェンバロによる演奏は聴いたことがないのですが、ピアノの表現力を極限までに駆使したものと言えるでしょう。この演奏を聴くと、他のはなんと緩いものかとついつい思ってしまうのでした。
このCDは「アルゲリッチ・コレクション1-ソロ・ピアノ録音」というものの1枚です。8枚組で3000円と少しでした。これも激安BOXですねえ。それにしても、アルゲリッチの演奏、他のバッハの曲でも聴いてみたいですよねえ。特に、平均律なんかを録音してもらいたい、と思うのは、私だけではないはずであります。
(DG COLLECTORS 4775870 2008年 輸入盤)


























このアルゲリッチのバッハ、LP時代に最初に聴いたとき
雷に打たれたように感動し、それ以来の愛聴盤です。
このアルバムを聴くと、なぜか「真剣勝負!」という言葉が脳裏に浮かびます。
とくにトッカータが好きです。